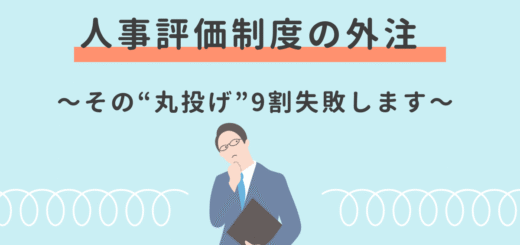人事評価制度テンプレートをDLする前に!社長が決めるべき理念とは?
人事評価制度のテンプレートをお探しの方へ。
そのExcelファイルをダウンロードする、そのワンクリックを、少しだけお待ちください。
今、あなたの手元にあるそのテンプレートは、適切に使えば会社の未来を創る設計図になり得ますが、一つ使い方を間違えれば、組織を崩壊させかねない「劇薬」にもなり得ます。
本記事では、まずその理由を徹底的に解説します。

【村井 庸介(むらい ようすけ)】
大学卒業後は株式会社野村総合研究所に入社し通信業・製造業の経営コンサルティングに携わる。その後リクルート、グリー、日本IBMに転職。その中でグリー株式会社にて人事制度設計に携わった。
2015年に独立後は、社員30名のベンチャー企業から5,000名を超える大企業まで幅広く人事制度設計や導入伴走に携わる。顧客業種は製造業、サービス、IT企業が中心。経営理念・事業戦略から逆算した人事制度構築を得意とする。
なぜ人事制度テンプレートはゴミ箱行きになるのか

多くの企業で、鳴り物入りで導入されたはずの人事評価シートが、いつの間にか誰も使わない形骸化したデータとなり、サーバーの片隅で眠っています。
あるいは、運用はされているものの、社員からは不満の声しか聞こえてこない、というケースも後を絶ちません。
なぜ、インターネットで手に入る高機能なテンプレートを使っても、このような悲劇が起きてしまうのでしょうか。
それは、ほとんどの経営者が、テンプレートという「器」に、自社の「魂」を込める作業を怠ってしまっているからです。
会社ごとに大切にする価値観や、求める人材像は全く違うはずです。
それなのに、他社のために作られた「既製品の服」を、無理やり自社の社員に着せようとすれば、あちこちで破綻が起きるのは当然のことなのです。
「魂の入った」制度の作り方を解説
この記事は、単なるテンプレートの配布サイトではありません。
テンプレートという便利な道具を使いこなし、あなたの会社の理念やビジョンを反映させた、世界に一つだけの「生きた人事制度」を創り上げるための、具体的な思考法と実践的な手順を解説します。
この記事を読み終える頃には、あなたはもう、巷のテンプレートに振り回されることはありません。
自らの手で、会社の未来を刻むための羅針盤を手に入れているはずです。
テンプレートだけで会社が崩壊する3つの理由

「とりあえず、テンプレートを導入すれば何とかなるだろう」
その安易な考えが、気づかぬうちにあなたの会社を内側から蝕んでいく危険性を孕んでいます。
テンプレートをそのまま流用することが、なぜ組織の崩壊にまで繋がりかねないのか。
ここでは、その具体的な3つの理由を解説します。
理由1:社員の不公平感を増幅させる
人事評価における社員の最大の不満は、「不公平感」です。
テンプレートの導入は、この最も厄介な感情を、かえって増幅させてしまう危険があります。
例えば、多くのテンプレートには「協調性」や「積極性」といった評価項目が並んでいます。
一見すると、誰もが納得する正しい項目に見えるでしょう。
しかし、この言葉の定義は、人によって全く異なります。
営業部のA部長が考える「積極性」と、開発部のB部長が考える「積極性」は、おそらく別物です。
明確な定義がないままテンプレートを導入すれば、評価者である管理職の個人的な価値観で評価が下されることになります。
結果として、「A部長の部署は評価が甘い」「B部長は厳しすぎる」といった、評価者に対する不満が噴出します。
これは、社員にとって「頑張っても、上司との相性で評価が決まる」という最悪のメッセージになります。
公平を目指したはずのテンプレートが、組織内に深刻な不公平感と不信感をばらまくことになるのです。
理由2:「いてほしい人材」から辞めていく
会社にとって本当に価値のある、将来を担ってほしい人材とはどのような人でしょうか。
それは、会社の理念に共感し、高い成果を出し、周囲にも良い影響を与えられる人のはずです。
しかし、汎用的なテンプレートは、そうした「本当にいてほしい人材」を正しく評価できるように設計されていません。
テンプレートの評価項目は、どうしても当たり障りのない、最大公約数的なものにならざるを得ないからです。
例えば、あなたの会社が「失敗を恐れない挑戦」を最も重要な価値観としているとします。
しかし、テンプレートの評価項目が「ミスの少なさ」や「計画の遵守率」を重視するものであったならどうでしょう。
リスクを取って果敢に挑戦した優秀な社員よりも、ミスなく無難に業務をこなした社員の方が、評価が高くなるという逆転現象が起こり得ます。
これでは、挑戦する社員が報われません。
「この会社にいても、自分の価値は正当に評価されない」
そう感じたエース社員は、より自分を高く評価してくれる会社を求め、静かにあなたの会社を去っていくのです。
テンプレートは、あなたの会社にとっての「宝物」を見分けるフィルターにはなってくれません。
理由3:社長のメッセージが真逆に伝わる
人事制度は、社長が社員に送る、最も強力なメッセージです。
「我が社は、こういう人材を大切にする」「こういう働き方に報いる」という、社長の価値観の表明に他なりません。
テンプレートを安易に流用することは、この最も重要なメッセージを、全く意図しない形で、あるいは真逆の形で社員に伝えてしまうリスクを伴います。
例えば、社長が日頃から「チームワークが大事だ」と口にしていたとしましょう。
しかし、ダウンロードしてきたテンプレートが、個人の成果目標(MBO)の達成率のみで賞与が決まる仕組みだったら、社員にどのようなメッセージが伝わるでしょうか。
「社長は口ではチームと言っているが、結局はこの会社、個人で数字を上げた者勝ちじゃないか」
そう解釈されても仕方がありません。
社員は、社長の「言葉」ではなく、自分たちの給与や昇進を決める「制度」を信じます。
テンプレートの無批判な導入は、社長が大切にしたいと願う企業文化を、意図せず破壊してしまうのです。
社長の想いと制度が発するメッセージの間に生じたズレは、社員のエンゲージメントを著しく低下させ、組織の活力を奪っていきます。
人事制度の魂は社長が決める「理念」である

テンプレートが機能しない理由を理解していただけたでしょうか。
では、人事制度を「生きた仕組み」に変えるために、最も重要なことは何なのか。
それは、制度の根幹に、社長が決めた「理念」という名の「魂」を吹き込むことです。
ここでは、その魂の本質に迫ります。
人事制度は社長の「えこひいき」を言語化する作業
「えこひいき」と聞くと、ネガティブな印象を持つかもしれません。
しかし、私は、優れた人事制度とは「社長の『えこひいき』を、全社員が納得する形で言語化し、仕組み化したもの」であると断言します。
会社という組織において、全ての社員を完全に平等に扱うことは不可能ですし、そうすべきでもありません。
会社に大きく貢献した人材と、そうでない人材の処遇に差がつくのは当然です。
問題は、その「差」の付け方が、社長の個人的な感情や、その場の気分といった曖昧なもので行われることです。
これでは、社員は納得できません。
人事制度の目的は、この「えこひいき」の基準を、誰の目にも明らかな「会社の公式ルール」として定めることにあります。
「我が社は、顧客を熱狂させた社員をえこひいきする」 「我が社は、チームの成果を最大化させた社員をえこひいきする」 「我が社は、誰もやらないような挑戦に踏み出した社員をえこひいきする」
このように、社長が「どのような社員を特別に扱い、報いたいのか」という意思を明確に言語化し、全社員に宣言する。
それが、納得感のある人事制度の第一歩なのです。
「誰に」「何で」報いるかを決めるのが理念
あなたの会社の「理念」とは何でしょうか。
それは、壁に飾られた美辞麗句のことではありません。
理念とは、有限である会社の資源(カネ、モノ、情報、時間)を、「誰に」「どのような行動に対して」優先的に分配するのか、という社長の「決断」そのものです。
人事制度は、その決断を最も分かりやすく体現する装置です。
例えば、給与や賞与という「カネ」を、どのような働きに対して支払うのか。
勤続年数の長いベテラン社員に手厚く報いるのか。
個人の売上目標を達成したエースに報いるのか。
失敗のリスクを背負って新しい事業を立ち上げたチャレンジャーに報いるのか。
この決断の一つひとつが、あなたの会社の理念を形作ります。
もし、あなたが「挑戦する文化」を創りたいと本気で願うなら、挑戦した結果、たとえ失敗したとしても、そのプロセス自体を評価し、報酬に反映させる仕組みが必要です。
そうでなければ、「挑戦せよ」という言葉は、ただの空念仏に終わるでしょう。
社員は、社長の言葉よりも、自分の給与明細に書かれた数字を信じるのです。
会社の法律作りは社長にしかできない仕事
人事制度は、いわば「会社という王国の法律」です。
法律は、その国が何を善とし、何を悪とするのか、その価値基準の根幹をなすものです。
そして、その国の法律を最終的に制定できるのは、国王や元首といった、その国の最高責任者だけです。
会社の法律である人事制度も全く同じです。
その最終決定権は、人事部長やコンサルタントにあるのではありません。
社長である、あなたにしか、その責任と権限はないのです。
これは、非常に重い責任です。
しかし同時に、これほどクリエイティブで、やりがいに満ちた仕事もありません。
なぜなら、それは会社の未来そのものをデザインする行為だからです。
どんな法律を創るかによって、国の文化や国民性が変わるように、どんな人事制度を創るかによって、会社の文化や社員の働き方は、劇的に変わります。
この最も重要でクリエイティブな仕事を、決して他人に丸投げしてはいけません。
【実践】社長が理念を言語化する3ステップ

「理念が重要であることは分かった。しかし、具体的にどうすればいいのか」
そう思われたかもしれません。
理念の言語化は、決して難しい作業ではありません。
ここでは、社長がたった一人でも取り組める、具体的な3つのステップをご紹介します。
STEP1:価値観を掘り起こす「5つの魔法の質問」
まず、誰にも邪魔されない静かな時間と、一本のペン、そして一枚の紙をご用意ください。
そして、以下の5つの質問に、思いつくままに答えを書き出してみてください。
- これまでの経営者人生で、社員のどんな行動を見て、心の底から「嬉しい」と感じましたか?
- 逆に、社員のどんな行動を見て、心の底から「がっかりした」あるいは「許せない」と感じましたか?
- もし、自分の子供が自社に入社するとしたら、どんな先輩社員のようになってほしいですか?
- 会社の業績が絶好調な時、その利益を、どんな成果を上げた社員に、最も多く分配したいですか?
- あなたが経営者を引退する日、社員から「社長は〇〇な人でした」と言われるとしたら、〇〇にどんな言葉が入ると嬉しいですか?
これらの質問に、綺麗に答えようとする必要はありません。
格好つけず、本音で、できるだけ具体的に書き出すことが重要です。
このプロセスを通じて、社長であるあなた自身が、無意識のうちに何を大切にし、何を評価の基準としているのか、その「価値観の源泉」が見えてくるはずです。
STEP2:「理想のチーム」の姿を紙に書き出す
次に、少し未来に視点を移してみましょう。
5年後、あなたの会社が大きな成功を収め、その祝賀会を開いている場面を想像してみてください。
そのパーティーの壇上で、あなたが「今回の成功の立役者だ」と、マイクを片手に紹介しているのは、どのような社員たちでしょうか。
彼らの顔ぶれ、年齢、役職、そして何より「彼らがどのような活躍をしたから、そこにいるのか」を、具体的に書き出してみてください。
「前例のないプロジェクトを、粘り強く成功に導いたA君」 「後輩の面倒見が良く、部署全体の士気を高めてくれたBさん」 「誰もが無理だと思った顧客を、誠実さで射止めたC部長」
ここに出てきた人々の「活躍の物語」こそが、あなたの会社が本当に評価すべき「行動」の具体例です。
この理想のチームの姿を明確に描くことで、人事制度が目指すべきゴール、つまり「どんな人材を育てるべきか」という方向性が、はっきりと定まります。
STEP3:理念を「会社の法律」に翻訳する
最後のステップは、STEP1と2で掘り起こした、あなたの「価値観」や「理想のチーム像」を、人事制度という「会社の法律」に翻訳していく作業です。
これは、抽象的な想いを、具体的なルールに落とし込むプロセスです。
例えば、STEP1で「挑戦する姿に感動した」という価値観が見つかり、STEP2で「新規プロジェクトを成功させたA君」が理想の社員像として描かれたとしましょう。
これを、人事制度に翻訳すると、以下のようになります。
・評価制度への翻訳: 評価項目に「新規性・挑戦度」という項目を設け、たとえ失敗しても、その挑戦プロセス自体を評価の対象に加える。
・等級制度への翻訳: 上位等級の昇格要件に「自ら課題を発見し、周囲を巻き込みながら新たな価値創造を主導できること」といった一文を加える。
・報酬制度への翻訳: 通常の賞与とは別に、「チャレンジ・オブ・ザ・イヤー」のような表彰制度を設け、最も果敢な挑戦をしたチームや個人に、特別なインセンティブを与える。
このように、あなたの理念を一つひとつ、制度の各パーツに埋め込んでいくのです。
これが、魂を吹き込むという作業の正体です。
まとめ:テンプレートは器。未来を刻むのは社長自身

人事評価制度のテンプレートは、使い方を間違えれば組織を蝕む劇薬となり、正しく使えば理念を実現する強力な道具となります。
その分岐点は、テンプレートをダウンロードする前、いや、ダウンロードした後に、社長であるあなたが、どれだけ自社の「理念」と真剣に向き合い、その「魂」を制度に吹き込む覚悟を持てるかにかかっています。
テンプレートは、あくまで白紙の法律の「器」に過ぎません。
その第一条に、どのような条文を刻むのか。
その法律で、どのような国民(社員)の幸福を実現したいのか。
その未来を描き、言葉を刻む仕事は、他の誰にもできない、社長だけの特権であり、最もクリエイティブな仕事です。
さあ、あなたの手で、あなたの会社の未来を刻んでください。
人事評価制度にお困りの方は、お気軽に村井にご相談ください。
➖ 資料請求 ➖
資料請求は下記バナーより。

➖ 問い合わせ ➖
新規事業、DX、人事制度などの経営課題に関するご相談は以下よりお受けしております。