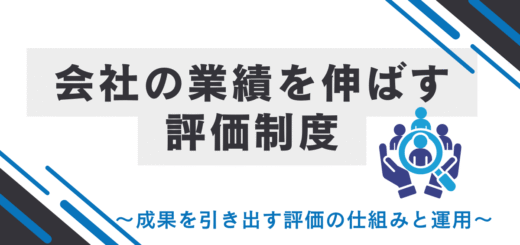人事評価制度の運用ポイント|ルールブックを燃やし理念を語れ!
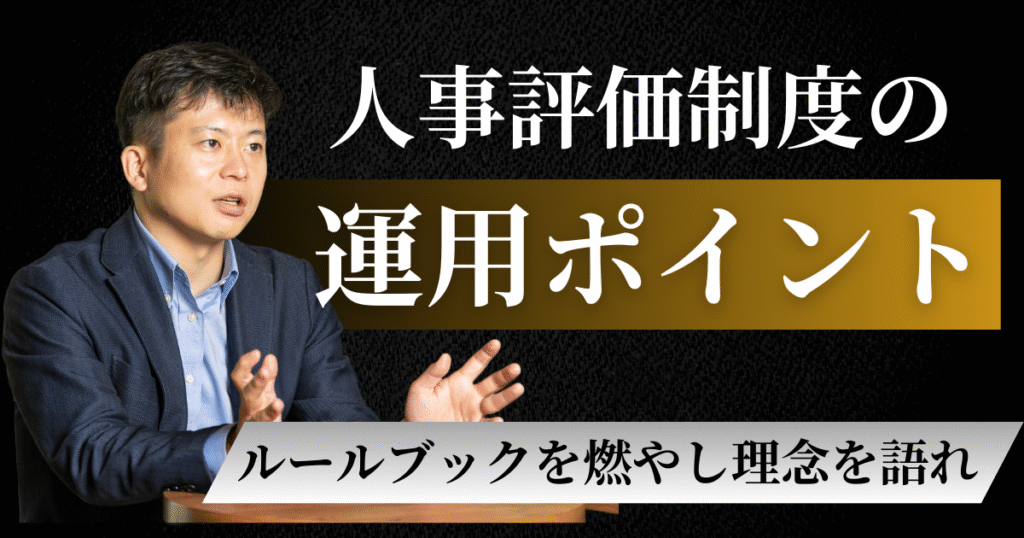
完璧な人事評価制度を設計し、詳細な運用ルールブックも作成した。
評価者研修も実施し、これでようやく、公平で納得感のある運用ができるはずだ。
多くの経営者や人事担当者が、そう期待します。
しかし、その期待とは裏腹に、現場からは「評価への不満」が聞こえ、管理職は「運用業務の負担」に疲弊し、社員はいつしか「評価のための仕事」をするようになる…。
なぜ、こんなことが起こるのでしょうか。
良かれと思って整えたはずの制度運用が、気づかぬうちに、社員のやる気や創造性を奪う枷になってしまっているとしたら?
この記事では、その根本原因を解き明かし、あなたの会社の人事評価制度に「命」を吹き込むための、本質的な運用ポイントを解説します。
ぜひ、最後までお読みください。

【村井 庸介(むらい ようすけ)】
大学卒業後は株式会社野村総合研究所に入社し通信業・製造業の経営コンサルティングに携わる。その後リクルート、グリー、日本IBMに転職。その中でグリー株式会社にて人事制度設計に携わった。
2015年に独立後は、社員30名のベンチャー企業から5,000名を超える大企業まで幅広く人事制度設計や導入伴走に携わる。顧客業種は製造業、サービス、IT企業が中心。経営理念・事業戦略から逆算した人事制度構築を得意とする。
はじめに:その人事評価制度の運用が社員のやる気を奪っている

人事評価制度の運用について、多くの企業が頭を悩ませています。
しかし、その議論のほとんどは、評価エラーをなくす方法や、面談の進め方といった、表面的なテクニックに終始しています。
問題の根源は、もっと深い場所にあるのです。
なぜ人事評価制度の運用は「作業」と化すのか
期初に目標シートを記入させ、期末に評価シートを回収し、評価結果をフィードバック面談で伝える。
この一連の流れが、いつの間にか、魂のこもらない「作業」になっていませんか?
管理職は、評価シートの膨大な項目を埋めることに追われ、部下の成長と向き合う時間を失います。
社員は、評価期間の終わりが近づくと、評価シート映えする「アリバイ作り」のような仕事に精を出すようになります。
制度を運用することが目的化し、本来の目的である「社員の成長」と「会社の発展」が、置き去りにされてしまうのです。
この「作業化」こそが、制度が機能不全に陥る、最も深刻な病です。
答えはルールに「社長の体温」がないから?
なぜ、運用は「作業」になってしまうのでしょうか。
その答えは、運用マニュアルや評価シートといった「ルール」に、社長の想い、つまり「体温」が感じられないからです。
どんなに精緻で公平に見えるルールでも、それがなぜ存在するのか、そのルールを通じて会社として何を成し遂げたいのかという、創り手の「想い」が伝わらなければ、ただの冷たい文字の羅列に過ぎません。
社員は、冷たいルールには従うかもしれませんが、心を動かされることはありません。
そして、心が動かなければ、本当の意味で人が育つことも、組織が活性化することもないのです。
あなたの会社の運用ルールブックから、社長の「体温」は感じられますか?
制度運用に「命」を吹き込む
この記事は、既存の運用マニュアルに、新たなルールを書き加えるためのものではありません。
そうではなく、今ある制度に「命」を吹き込み、血の通った「生きた仕組み」として機能させるための、本質的な考え方と具体的な実践方法を提示します。
この記事を読み終える頃には、あなたは、人事評価制度の運用というものを、全く新しい視点で見つめ直しているはずです。
さあ、あなたの会社に「命」を吹き込む旅を、始めましょう。
人事評価制度 運用の9割が陥ることとは?
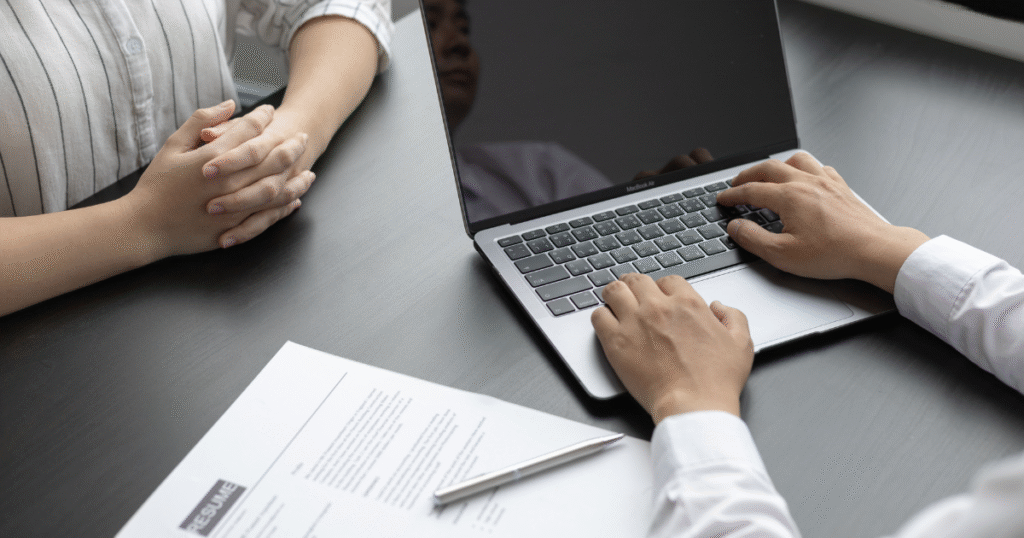
多くの企業が、良かれと思って取り入れている「一般的な運用ポイント」。
しかし、その常識こそが、実は制度を形骸化させる罠であることに、ほとんどの人が気づいていません。
ここでは、9割の企業が陥る、運用の落とし穴について解説します。
一般的な運用ポイントという名の思考停止
「目標はSMARTに設定しましょう」 「評価エラーを防ぐために、評価者研修を実施しましょう」 「フィードバックはSBIモデルを活用しましょう」
これらは、人事評価制度の運用において、よく語られる「一般的な運用ポイント」です。
もちろん、一つひとつは、先人たちの知恵であり、決して間違ってはいません。
しかし、これらの「正解」とされるものに頼りすぎると、経営者や人事担当者は、「自社にとって、本当に大切なことは何か」を考えることをやめてしまいます。
つまり、「思考停止」に陥るのです。
他社の成功事例や、世の中の常識を、自社の文化や事業特性を無視してそのまま当てはめようとする。
その結果、誰の心にも響かない、どこにでもある、無味乾燥な制度運用が生まれてしまうのです。
「ルール暗記大会」と化した評価者研修の悲劇
運用ポイントの中でも、特に「評価者研修」は、多くの企業が熱心に取り組みます。
しかし、その中身が「評価エラーの種類」や「評価シートの正しい書き方」といった、ルールの解説と暗記に終始しているとしたら、それは悲劇の始まりです。
そのような研修を受けた管理職は、「ルールから逸脱しないこと」を最優先に行動するようになります。
彼らは、部下の成長を支援する「育成者」ではなく、ルール違反を取り締まる「監視者」になってしまうのです。
部下の個性や、状況に応じた柔軟な判断よりも、ルールブックに書かれた通りの評価をすることに全神経を集中させます。
これでは、管理職も部下も、評価制度の本来の目的を見失い、ただただ疲弊していくだけです。
評価者研修とは、ルールを暗記させる場ではなく、会社の理念を共有し、管理職を「理念の伝道師」へと育てる場でなければならないのです。
なぜ完璧なルールほどエースは辞めるのか
矛盾しているように聞こえるかもしれませんが、実は、人事評価の運用ルールが「完璧」であればあるほど、優秀なエース社員が会社を去っていくリスクが高まります。
なぜなら、完璧なルールとは、言い換えれば「裁量の余地がない」ということだからです。
ルールが細かく、評価基準が精緻であればあるほど、社員は、そのルールに最適化された行動を取るようになります。
減点されないように、無難な目標を立て、失敗しないように、リスクのある挑戦を避ける。
しかし、本当に会社を成長させるエース社員とは、時にルールからはみ出し、常識を打ち破るような挑戦をする人材ではなかったでしょうか。
彼らは、ルールに縛られることを極端に嫌います。
完璧すぎるルールは、彼らの創造性や情熱を閉じ込める「檻」となり、やがて、より自由な環境を求めて、あなたの会社から飛び立ってしまうのです。
人事評価制度 運用の本質は「理念」を語ること
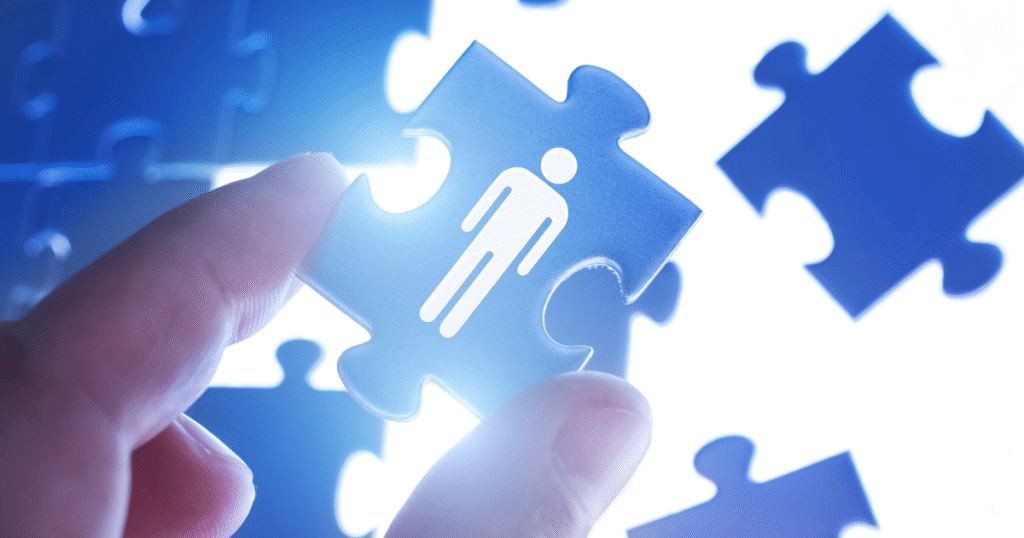
ルールで縛る運用が、なぜうまくいかないのか。
その答えが見えてきたでしょうか。
ここからは、人事評価制度の運用の「本質」について、深く掘り下げていきます。
そのキーワードは、ただ一つ。「理念」です。
優れた運用は「解釈の余地」から生まれる
ルールでがんじがらめにするのではなく、あえて「解釈の余地」を残すこと。
これこそが、優れた運用の秘訣です。
もちろん、最低限のルールは必要です。
しかし、全ての事象をルールで網羅しようとすることは不可能ですし、そうすべきでもありません。
重要なのは、会社の理念やビジョンという、大きな「判断の軸」を、全社員と共有することです。
そして、その軸に沿っていれば、現場の状況に応じた柔軟な判断、つまり「解釈」を、管理職や社員に委ねるのです。
この「解釈の余地」こそが、社員一人ひとりの主体性や、当事者意識を育みます。
「理念に照らし合わせると、この場合はどう判断すべきか」
社員が自ら考えるプロセスを通じて、理念は初めて、血の通った「生きた規範」となるのです。
理念こそが究極の運用判断基準
ルールブックには、想定される、ありとあらゆるケースへの対処法が書かれています。
しかし、ビジネスの世界では、常にルールブックに書かれていない「想定外」の事態が発生します。
その時、何を基準に判断すれば良いのでしょうか。
その答えこそが「理念」です。
理念は、どんなルールブックよりも強力な、究極の運用判断基準となります。
例えば、ある社員が、会社のルールを少し破ったものの、結果として、お客様から絶大な感謝を得るという出来事があったとします。
ルールブックに従えば、その社員は「減点」の対象かもしれません。
しかし、「顧客第一」という理念に照らし合わせれば、その行動は「賞賛」されるべきものかもしれません。
理念というブレない軸があるからこそ、私たちは、ルールの奴隷になることなく、本質的な判断を下すことができるのです。
人は指示でなく「共感する目的」で動く
そもそも、人は、ルールや指示といった「外的要因」だけでは、本当の意味でパフォーマンスを発揮することはできません。
もちろん、罰を恐れて、あるいは報酬に釣られて、行動することはあるでしょう。
しかし、その行動に、情熱や創造性が伴うことはありません。
人が、自らの持つ能力を最大限に発揮するのは、「この目的のためなら、頑張りたい」と、心の底から思える「共感する目的」に出会った時だけです。
人事評価制度の運用とは、この「共感する目的」、つまり会社の「理念」を、社員一人ひとりの心に届け、火をつけるための、コミュニケーション活動そのものなのです。
理念への共感が、社員を自律的な存在へと変え、組織を内側から動かしていく、最も強力なエンジンとなります。
人事評価制度 運用を成功させる「理念の伝え方」

では、具体的にどうすれば、会社の理念を、日々の運用の中で伝えていくことができるのでしょうか。
それは、決して難しいことではありません。
ここでは、明日からすぐに実践できる、具体的な3つの方法をご紹介します。
社長の想いを「自分の原体験」として語る
会社の理念やバリューは、多くの場合、社長の言葉として、少し抽象的に語られます。
管理職が、その言葉をそのまま部下に伝えても、右から左へ受け流されてしまうでしょう。
部下の心に響かせるためには、その「理念」を、あなた自身の「原体験」という物語に変換して語ることが不可欠です。
例えば、会社のバリューに「誠実」という言葉があるならば、あなたが過去に、誠実な対応で顧客の信頼を勝ち取った成功体験や、逆に不誠実な行動で手痛い失敗をした経験を、具体的なエピソードとして語るのです。
「昔、俺は大きなミスをしてしまって、正直に言うか迷ったことがあった。でも、勇気を出して謝罪したら、お客様は逆に『正直に話してくれてありがとう』と言ってくれたんだ。あの経験が、この仕事における『誠実さ』の本当の意味を教えてくれた」
あなた自身の血の通った物語として語られることで、理念は初めて、リアリティと熱量を持ち、部下の心に深く刻まれるのです。
評価面談を「成長契約の場」に変える質問術
評価面談は、過去の評価を伝えるだけの場ではありません。
それは、部下の未来の成長について、会社と本人が「契約」を結ぶ、極めて重要な儀式の場です。
この「成長契約」を成功させるために、いくつかの魔法の質問があります。
一つ目は、「この半期で得た経験を、君自身の成長ストーリーの中で、どう位置づけている?」という質問です。
これにより、部下は、業務を「自分ごと」として意味づけることができます。
二つ目は、「その強みを活かして、次は会社にどんな貢献ができると思う?」という質問です。
これにより、部下の成長と会社の成長が、地続きであることを意識させます。
そして三つ目は、「その挑戦のために、私や会社は、どんなサポートをすればいい?」という質問です。
これにより、会社が本気で部下の成長を支援する姿勢であることを、明確に示すことができます。
これらの質問を通じて、面談は、未来に向けた、希望に満ちた対話の場へと変わるのです。
日常業務を「理念を体感する場」に変える
理念は、評価面談のような特別な場だけで語られるべきものではありません。
むしろ、日々の何気ない業務の中にこそ、理念を体感させるチャンスが溢れています。
例えば、朝礼の5分間を使って、社員が「会社の理念を体感した瞬間」をスピーチする時間を作る。
会議で意見が分かれた時には、「そもそも、私たちの理念に立ち返ると、どちらの選択が正しいだろうか?」と問いかける。
部下からの日報に対して、単に「了解」と返すのではなく、「その行動は、まさに我が社の〇〇という価値観を体現しているね」と、理念と結びつけたフィードバックを一言添える。
このように、日常のあらゆる接点を、理念を語り、理念を体感する場へと、意図的にデザインしていくのです。
この地道な積み重ねが、やがて、理念が組織の隅々にまで染み渡った、強い企業文化を創り上げます。
まとめ

人事評価制度の運用ポイントの本質は、どこまでいっても、非常にシンプルです。
それは、分厚いルールブックを精緻に運用することではありません。
社長の想いが込められた「理念」を、経営者と管理職が、自らの言葉で、飽きることなく、語り続けること。
ただ、それだけです。
燃やすべきは、社員を縛り、思考停止に陥らせる、魂のこもらないルールブックです。
そして、代わりに育てるべきは、社員一人ひとりの心に灯る、理念への共感という名の、生きた炎です。
この記事を読み終えた社長、そして管理職のあなたへ。
最後に、たった一つのメッセージを送ります。
明日から、評価シートを脇に置き、あなたの言葉で、あなたの会社の物語を、部下に語ってあげてください。
その対話こそが、あなたの会社を、本当の意味で強く、たくましく育てていくのです。
人事評価制度にお困りの方は、お気軽に村井にご相談ください。
➖ 資料請求 ➖
資料請求は下記バナーより。

➖ 問い合わせ ➖
新規事業、DX、人事制度などの経営課題に関するご相談は以下よりお受けしております。