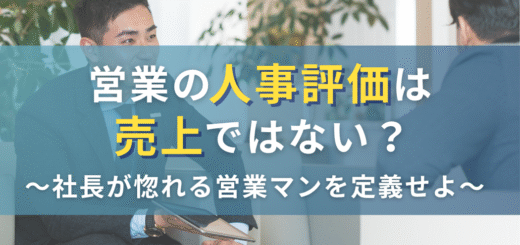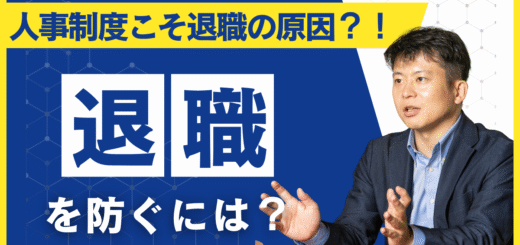中小企業の人事評価制度|その導入、本当に必要ですか?
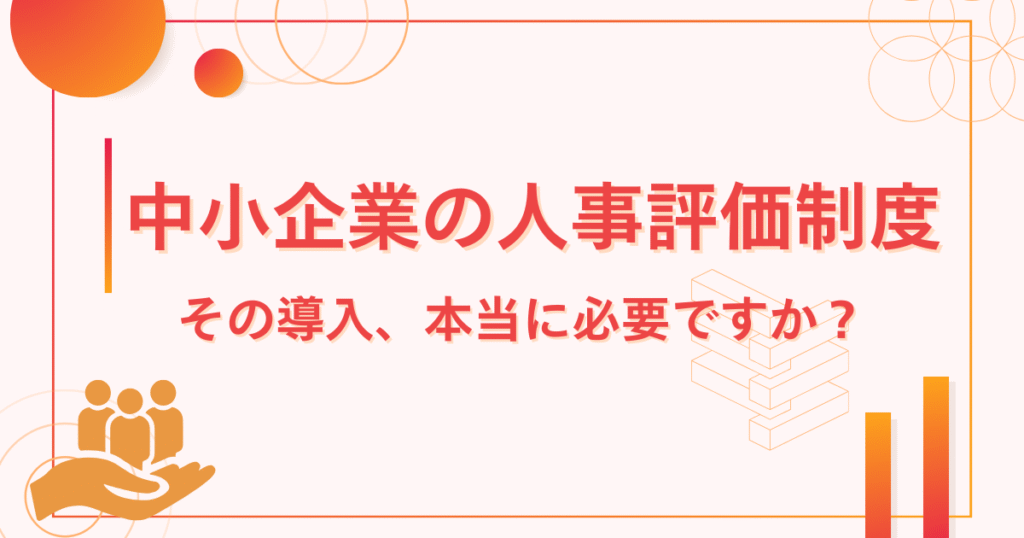
中小企業の人事評価制度、会社の規模が大きくなるにつれて、「そろそろ、うちも導入すべきか」と考える経営者の方は、非常に多いのではないでしょうか。
しかし、その一歩が、あなたの会社の成長を加速させる特効薬になるか、あるいは、組織の活力を奪う劇薬になるか知っていますか?
自社の現状と照らし合わせながら、読み進めてみてください。

【村井 庸介(むらい ようすけ)】
大学卒業後は株式会社野村総合研究所に入社し通信業・製造業の経営コンサルティングに携わる。その後リクルート、グリー、日本IBMに転職。その中でグリー株式会社にて人事制度設計に携わった。
2015年に独立後は、社員30名のベンチャー企業から5,000名を超える大企業まで幅広く人事制度設計や導入伴走に携わる。顧客業種は製造業、サービス、IT企業が中心。経営理念・事業戦略から逆算した人事制度構築を得意とする。
はじめに:中小企業の人事評価制度 その導入は劇薬かもしれない

人事評価制度は、正しく使えば組織を成長させる強力なツールとなります。
しかし、その導入の決断は、極めて慎重に行われなければなりません。
特に、体力に限りある中小企業にとって、安易な導入は、取り返しのつかない事態を招きかねないのです。
なぜ9割の中小企業は制度導入で失敗するのか
驚かれるかもしれませんが、多くの中小企業が、良かれと思って導入した人事評価制度によって、むしろ組織の状態を悪化させています。
社員のモチベーションは下がり、管理職は疲弊し、社内には不信感が渦巻く。
なぜ、こんなことが起こるのでしょうか。
その理由は、非常にシンプルです。
ほとんどの企業が、制度導入の「本当の目的」を理解しないまま、ただ「仕組み」だけを導入してしまっているからです。
魂のない制度は、人を幸せにしません。
大企業ごっこになっていないか?
「上場企業が導入しているから」「立派な制度があれば、採用で有利になるから」
こうした、体裁を整えるためだけの制度導入を、私たちは「大企業ごっこ」と呼んでいます。
中小企業には、中小企業ならではの強みがあります。
それは、社長と社員の距離が近く、意思疎通が密であることです。
この最大の武器を自ら捨て去り、形だけの「大企業ごっこ」に走ることは、会社の個性を失い、組織を弱体化させる、最も愚かな選択の一つなのです。
会社の健康診断書を把握しよう
この記事は、あなたの会社に「人事評価制度を導入すべきか、否か」という問いに対する、一つの「健康診断書」として機能します。
まずは、巷で語られる一般的なメリットと作り方を理解する。
その上で、あなたの会社が、本当に制度という「劇薬」を必要とするステージにあるのかを、客観的に見極める。
そして、もし必要だと判断したならば、失敗しないための、本質的な処方箋を手に入れる。
さあ、あなたの会社の健康状態を、共に診断していきましょう。
まずは知るべき一般的なメリットと導入手順
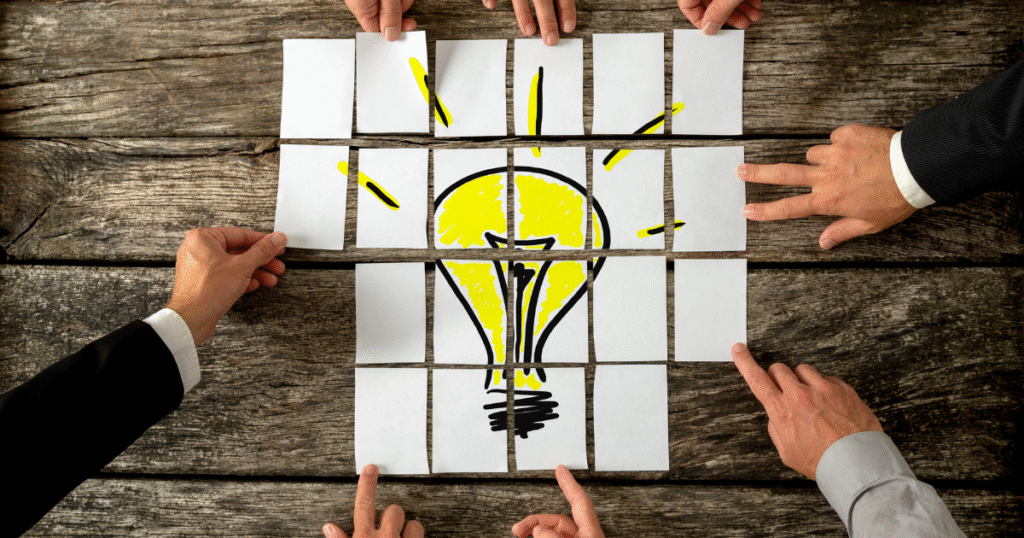
本質的な議論に入る前に、まずは、世の中で「正しい」とされている、人事評価制度の一般的なメリットと、その作り方について、網羅的に確認しておきましょう。
これらは、導入を検討する上での、基本的な知識となります。
中小企業が制度導入で得られるとされるメリット
人事評価制度が理想的に機能すれば、中小企業は多くのメリットを享受できるとされています。
第一に、「公平性・透明性の確保」です。 社長の個人的な感覚ではなく、明確な基準に基づいて評価されることで、社員は納得感を持ちやすくなります。
第二に、「従業員のモチベーション向上」です。 努力や成果が、昇給や賞与といった形で正当に報われることが、仕事への意欲を高めます。
そして第三に、「人材育成と定着」です。 評価を通じて、個々の社員の強みや課題が明確になり、育成計画が立てやすくなることで、人材の成長と定着に繋がります。
これらは確かに、企業経営における重要なテーマです。
一般的な人事評価制度の作り方5ステップ
では、これらのメリットを実現するために、一般的には、どのような手順で制度を作るのでしょうか。
多くの解説書では、以下の「5つのステップ」が紹介されています。
ステップ1は、「課題把握と目的設定」です。 自社の課題を洗い出し、制度で何を解決したいのかを明確にします。
ステップ2は、「評価基準と項目の決定」です。 定めた目的に基づき、何をすれば評価されるのか、具体的な基準を策定します。
ステップ3は、「評価方法とルールの設定」です。 誰が、どのように評価し、それをどう処遇に反映させるのかを決めます。
ステップ4は、「システム整備と社員への周知」です。 評価シートなどを用意し、全社員に制度の内容を説明します。
ステップ5は、「運用開始と定期的な見直し」です。 実際に制度を動かしながら、継続的に改善を加えていきます。
この5ステップが、一般的な制度の作り方です。
中小企業向け人事評価システムの現実
近年、こうした制度の設計や運用を、比較的安価にサポートしてくれる、中小企業向けの人事評価システムも、数多く登場しています。
これらのシステムは、確かに、人事担当者の業務負担を軽減し、評価プロセスの効率化に貢献するでしょう。
しかし、忘れてはならないのは、システムは、あくまで「道具」に過ぎないということです。
どんなに高価な料理道具を揃えても、料理人の「何を作りたいか」という思想がなければ、美味しい料理は作れません。
システムは、あなたの会社の理念を、自動で形にしてくれる魔法の杖ではないのです。
その現実を、私たちは、まず直視する必要があります。
50名未満の中小企業に人事評価制度が不要な理由

さて、ここからが、この記事の核心です。
私たちは、これまでの経験から、「従業員数50名未満の中小企業においては、人事評価制度は、むしろ導入しない方が良いケースが多い」と、考えています。
これは、多くの専門家の意見とは、真逆かもしれません。
その理由を、ご説明します。
社長の生の声が最強の評価制度である
従業員が50名未満の規模であれば、多くの場合、社長は、全社員の顔と名前、そして、その働きぶりを、直接把握することができます。
誰が、今、最も頑張っているか。
誰が、チームに最も貢献しているか。
誰が、悩みを抱えているか。
社長であるあなたの「肌感覚」が、それを教えてくれるはずです。
そして、その肌感覚に基づいて、あなたが直接かける「ありがとう」「よくやったな」「次は、こうしてみないか」という、生の声。
それこそが、どんなに精緻な評価シートよりも、社員の心を動かす、「最強の評価制度」なのです。
無理な制度導入が引き起こす3つの悲劇
この「社長の生の声」という、中小企業ならではの最強の武器を捨ててまで、無理に人事評価制度を導入すると、多くの場合、3つの悲劇が起こります。
一つ目は、「組織のスピード感の喪失」です。 これまで社長の一声で決まっていたことが、評価期間や目標設定といった、制度のプロセスに縛られ、意思決定が遅くなります。
二つ目は、「社員のモチベーション低下」です。 社長との人間的な関係性の中で評価されていた状態から、冷たい評価シートの上で点数を付けられる状態へと変わることは、社員にとって、大きなストレスと不信感を生み出します。
三つ目は、「本業へのリソース圧迫」です。 ただでさえリソースの限られる中小企業が、制度の設計や運用に多大な時間と労力を費やすことは、売上や利益に直結する、本来の事業活動を、圧迫することに繋がります。
制度の前に社長がやるべきこと
もし、あなたの会社が50名未満で、かつ、組織に大きな問題を感じていないのであれば。
あなたが今やるべきことは、人事評価制度の導入ではありません。
もっと、社員と対話することです。
もっと、顧客と向き合うことです。
そして何より、社長であるあなた自身が、「この会社を、どこへ導きたいのか」という、自らの理念を、より深く見つめ直すことです。
制度という「仕組み」に頼る前に、まず、あなたの「想い」を、あなたの「言葉」で、社員に伝え続けること。
それが、50名未満の企業における、最も本質的な人事施策なのです。
本当に必要な中小企業とは社長の目が届かなくなった会社

では、どんな中小企業に、人事評価制度は、本当に必要になるのでしょうか。
その答えは、極めてシンプルです。
それは、社長であるあなたの「目」が、もはや、全社員に届かなくなった時です。
導入のタイミングは50名の壁
多くの企業で、その限界点、つまり「社長の目が届かなくなる」のが、従業員数50名前後であると、私たちは考えています。
私たちは、これを「50名の壁」と呼んでいます。
社員数が50名を超えると、社長は、もはや全社員の働きぶりを、直接、肌感覚で把握することは、物理的に不可能になります。
社長の目が届かない部署では、社長が大切にしてきたはずの理念や文化が、いつの間にか、部署独自のルールに上書きされ、歪んで伝わり始めます。
この「50名の壁」こそが、人事評価制度の導入を、本気で検討すべき、唯一のタイミングなのです。
制度の目的は社長の分身を創り出すこと
そして、このタイミングで導入する人事評価制度の目的は、一般的な「公平性の確保」や「モチベーション向上」ではありません。
その、たった一つの、しかし最も重要な目的。
それは、社長の目が届かない場所で、社長の代わりに、社長の理念や価値観を伝え、判断を下してくれる、「社長の分身(アルター・エゴ)」を、創り出すことです。
人事評価制度とは、社長の理念をインストールされた、もう一人のあなたなのです。
この制度があるからこそ、会社が大きくなっても、組織のベクトルがずれることなく、社長が目指す方向に、全社員が一丸となって、進むことができるのです。
理念から創る中小企業のための人事評価制度
では、どうすれば、「社長の分身」となる、魂のこもった人事評価制度を、創ることができるのでしょうか。
それは、他社の真似をするのではなく、社長である、あなた自身の心の中から、創り出すのです。
STEP1:社長が誰をえこひいきするかを宣言する
制度作りの最初のステップは、社長であるあなたが、「この会社では、どのような価値観を持ち、どのような行動をする人間が、最も賞賛され、報われるべきなのか」という、会社の「えこひいき」の基準を、明確に言語化し、全社員に宣言することです。
「我が社は、失敗を恐れずに挑戦する人間を、えこひいきする」
この、社長の覚悟のこもった「えこひいき宣言」こそが、制度の魂となり、全ての評価の、ブレない軸となります。
STEP2:理念をシンプルなルールに落とし込む
次に、その宣言した理念(えこひいきの基準)を、できるだけシンプルな「ルール」へと、落とし込んでいきます。
中小企業の制度は、大企業のように、複雑である必要は全くありません。
例えば、「挑戦」をえこひいきするなら、評価項目に「チャレンジ度」という項目を一つ加え、その配点を高くする。
賞与の査定において、挑戦的なプロジェクトに関わった社員には、特別な加算を行う。
このように、理念を体現する、数個の、しかし強力なルールを作るだけで、十分なのです。
STEP3:社長自らが最初の法律遵守者となる
そして、最も重要なのが、この新しい「法律」を、社長自らが、誰よりも、厳格に遵守する姿を見せることです。
たとえ、個人的に親しい社員であっても、理念に反する行動を取ったならば、ルールに則って、厳しい評価を下す。
逆に、普段は目立たない社員でも、理念を体現する素晴らしい行動を取ったならば、ルールに則って、最大限の賞賛と報酬を与える。
社長のこの一貫した姿勢が、制度への信頼を生み、社員の行動を変えていくのです。
まとめ:自社の規模と理念に合った制度を考える
中小企業の人事評価制度。
その導入の是非は、会社の「規模」と「理念」という、二つの軸で、判断すべきです。
あなたの会社は今どのステージにいるのか
まず、自問してください。
「私の目は、まだ、全社員に届いているだろうか?」
もし、答えが「YES」であるならば、あなたは、まだ、制度という「仕組み」に頼る必要はありません。
あなたの「生の声」こそが、最高の評価制度です。
もし、答えが「NO」であるならば、あなたは、いよいよ、「社長の分身」を創るべき、ステージに来たのかもしれません。
中小企業専門の人事制度設計 個別相談
もし、あなたが、自社のステージを見極め、あなたの会社の理念、つまり「魂」のこもった、唯一無二の人事評価制度を、本気で創りたいと願うならば、ぜひご相談ください。
社長であるあなたの「想い」を言語化し、それを組織の隅々にまで浸透させる、血の通った制度設計を、ゼロから、共に行います。
あなたの会社だけの「本物の制度」を、共に創り出せる日を、心から楽しみにしています。
人事評価制度にお困りの方は、お気軽に村井にご相談ください。
➖ 資料請求 ➖
資料請求は下記バナーより。

➖ 問い合わせ ➖
新規事業、DX、人事制度などの経営課題に関するご相談は以下よりお受けしております。