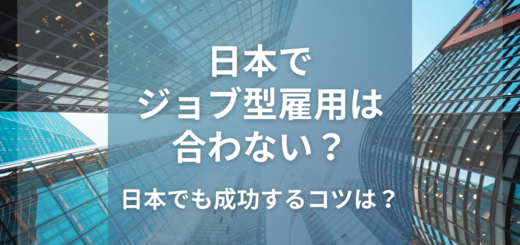人事制度こそ退職の原因?!退職を防ぐには?
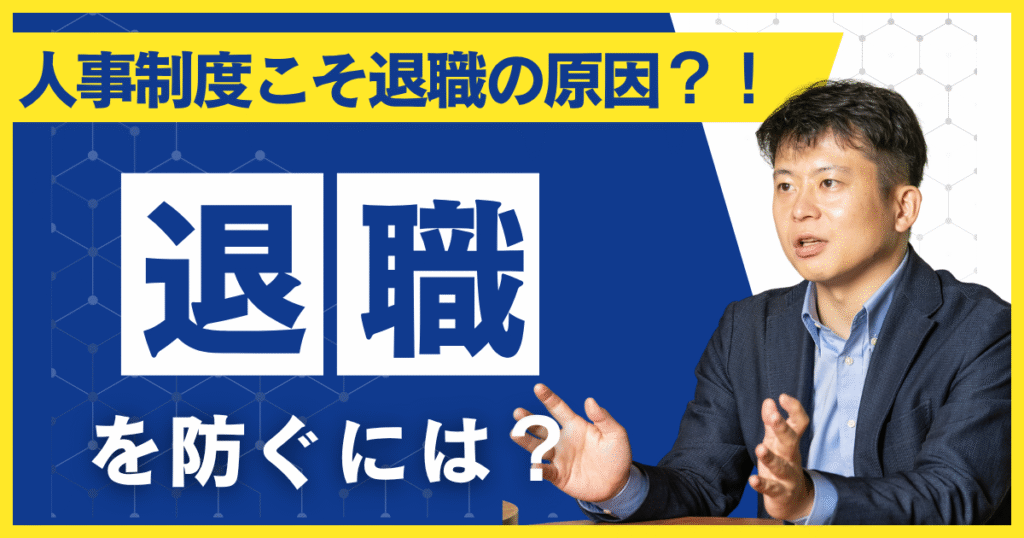
「人事制度を導入すれば、社員の不満が減り、退職率も下がるはずだ」
多くの経営者や人事担当者が、そう信じて、多大な時間とコストをかけて人事制度を導入します。
しかし、現実はどうでしょうか。
良かれと思って導入したはずの制度が、なぜかうまく機能せず、むしろ社員の不満が噴出。
優秀な人材から、静かに会社を去っていく。
そんな、悪夢のような事態に陥っていませんか?
もし、そうだとすれば、あなたは、衝撃的な事実を、受け入れなければならないかもしれません。
それは、「人事制度こそが、退職の本当の原因かもしれない」という事実です。
この記事では、なぜ、その悲劇が起こるのか、その根本原因を徹底的に解き明かします。
そして、あなたの会社が、退職の連鎖を断ち切り、社員が本当に「この会社で働き続けたい」と思える組織へと生まれ変わるための、本質的な「たった一つの答え」を解説しましょう!

【村井 庸介(むらい ようすけ)】
大学卒業後は株式会社野村総合研究所に入社し通信業・製造業の経営コンサルティングに携わる。その後リクルート、グリー、日本IBMに転職。その中でグリー株式会社にて人事制度設計に携わった。
2015年に独立後は、社員30名のベンチャー企業から5,000名を超える大企業まで幅広く人事制度設計や導入伴走に携わる。顧客業種は製造業、サービス、IT企業が中心。経営理念・事業戦略から逆算した人事制度構築を得意とする。
なぜ人事制度が退職の原因になるのか
人事制度は、正しく使えば組織を成長させる強力な武器となります。
しかし、その設計や運用を一つ間違えれば、組織の活力を奪い、優秀な人材を流出させる「劇薬」にもなり得るのです。
良かれと思って導入した制度が退職を生む
「公平な評価を実現したい」
「社員のモチベーションを高めたい」
「人材を育成したい」
こうした、経営者の「良かれ」という想いから人事制度は導入されます。
しかし、その想いが、社員に正しく伝わらなければ、どうなるでしょうか。
複雑すぎる評価項目、曖昧な評価基準、一方的なフィードバック。
これらは、社員にとって、「管理されている」「信頼されていない」という、ネガティブなメッセージとして、受け取られてしまいます。
良かれと思って作ったルールが、社員の手足を縛り、主体性を奪い、やがて「こんな会社、もう辞めたい」という、退職の引き金を引くことになるのです。
優秀な人材ほど辞めていく理由
そして、何よりも深刻なのは、「優秀な人材」ほど、ダメな人事制度に、敏感に反応し、早く見切りをつけて辞めていく、という事実です。
なぜなら、彼ら、彼女らは、成長意欲が高く、会社への貢献意識も、誰よりも強いからです。
だからこそ、自分の頑張りが正当に評価されない、会社の理念が見えない、キャリアの未来が描けない、と感じた時の、失望感も、人一倍大きいのです。
彼らは、不満を口にする代わりに、静かに、そして、あっという間に、次のステージへと去っていきます。
会社に残るのは、制度に不満を持ちながらも、転職する勇気がない社員と、変化を恐れる社員だけ。
これこそが、制度導入が招く、最悪のシナリオです。
50名未満の会社の制度導入が退職トリガー?
特に、私が強く警鐘を鳴らしたいのが、従業員数50名未満の企業における、安易な制度導入です。
この規模の会社は、本来、社長の「目」と「声」が、全社員に直接届くはずです。
誰が頑張っているか、誰が悩んでいるか、社長が肌感覚で分かり、直接、声をかけることができる。
これこそが、小規模組織の、最大の武器です。
この武器を自ら捨て去り、冷たい「仕組み」に頼ろうとすることは、社員との間に、見えない壁を作ることになりかねません。
「社長は、私たちを見てくれなくなった」
その失望感が、退職のトリガーになるケースを、私は、嫌というほど、見てきました。
一般的に言われる人事制度と退職の理由

では、世間一般では、人事制度と退職は、どのように関連付けられているのでしょうか。
まずは、よく語られる「一般的な退職理由」を、整理しておきましょう。
しかし、忘れないでください。
これらは、あくまで「症状」に過ぎない、ということを。
理由1 評価基準への不満と納得感の欠如
退職理由として、最も多く挙げられるのが、評価基準への不満です。
「評価基準が曖昧で、上司の好き嫌いで決まっている」 「何をすれば評価されるのかが、分からない」
このような、評価の「不公平感」や「不透明感」は、社員の納得感を、著しく低下させます。
自分の頑張りが正当に評価されないと感じた時、社員は、会社への信頼を失い、モチベーションを維持することが、困難になります。
理由2 頑張りが報われない給与への不満
評価への不満は、多くの場合、給与への不満と、直結しています。
「あれだけ成果を出したのに、給与がほとんど上がらない」
「頑張っていない同期と、給与が変わらない」
人事評価制度が、社員の貢献度と、給与や賞与といった報酬とを、正しく連動させていない。
この「頑張りが報われない」という感覚は、社員の勤労意欲を、根本から、へし折ってしまいます。
特に、優秀な人材ほど、自らの市場価値を、敏感に察知しています。
正当な報酬を提示できない会社に、彼らが留まり続ける理由はありません。
理由3 将来が見えないキャリアパスの不在
三つ目の理由は、将来への「絶望感」です。
「この会社に、あと何年いても、成長できる気がしない」
「自分のキャリアが、どうなっていくのか、全く見えない」
人事評価制度が、単なる「査定」のツールとしてしか機能しておらず、
社員一人ひとりの、中長期的な「成長」や「キャリアパス」を、示すことができていない。
このような、未来の展望が描けない職場で、優秀な人材が、働き続けたいと思うでしょうか。
彼らは、自らの成長の機会を求めて、新天地へと、旅立っていくのです。
退職の本当の原因は制度ではなく社長の不在
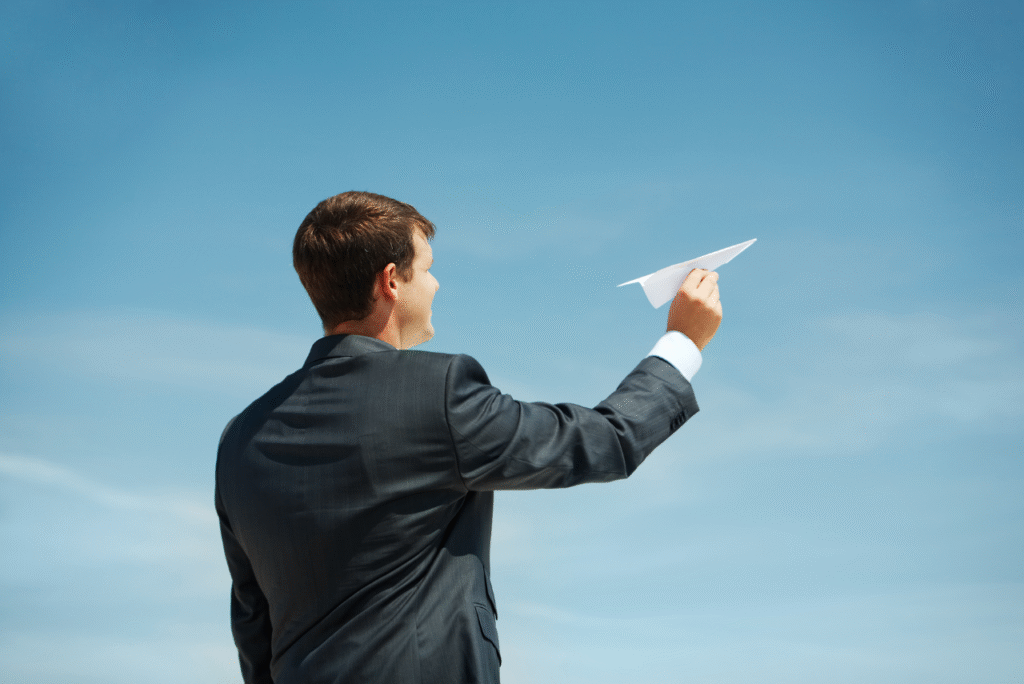
評価基準の曖昧さ、給与への不満、キャリアパスの不在。
これらは確かに、退職の引き金となります。
しかし、私は、これらはすべて「症状」に過ぎないと、断言します。
では、病気の「根本原因」は、どこにあるのでしょうか。
その答えは、ただ一つ。「社長の不在」です。
制度に会社の法律がない
私の思想の根幹には、「人事評価制度は、会社という王国の法律である」という考え方があります。
そして、その法律の制定者は、社長、あなた以外にあり得ません。
しかし、多くの企業で、社長は、制度設計や運用を、人事部やコンサルタントに「丸投げ」してしまいます。
その結果、どうなるか。
社長の理念や、価値観、つまり「魂」のこもっていない、ただのテクニックの寄せ集めのような、無味乾燥な「法律」が、できあがります。
社員は、そんな「魂のない法律」に、従いたいと思うでしょうか。
理念なき公平性で社員の心を冷ます
「魂のない法律」は、どんなに「公平」な体裁を繕っても、社員の心を、惹きつけることはできません。
むしろ、その機械的で、冷たい「公平性」こそが、社員の心を、冷え込ませるのです。
人は、ただ公平に扱われたいわけではありません。
自分が信じる「理念」や「価値観」のために働きたいのです。
そして、その理念を体現した仲間と共に、成長したいのです。
社長の理念という「熱源」がない制度は、組織の体温を奪い、社員の情熱を、凍てつかせてしまいます。
退職防止策が対症療法で終わってしまう
社長が「不在」のまま、現場が、いくら退職防止策を講じても、それは、すべて「対症療法」で終わります。
給与が不満だと言われれば、給与テーブルをいじる。
評価基準が曖昧だと言われれば、評価項目を増やす。
キャリアパスが見えないと言われれば、研修制度を作る。
しかし、そのすべてに、社長の「理念」という、一貫した背骨が通っていなければ、必ず、どこかで歪みが生じます。
そして、社員は、その場しのぎの対策を、敏感に見抜き、さらに失望を深めていくのです。
退職という「出血」は、社長という「心臓」が、理念という「血液」を、組織の隅々にまで、送り届けて初めて、止まるのです。
退職を防ぐ本質的な人事制度の作り方
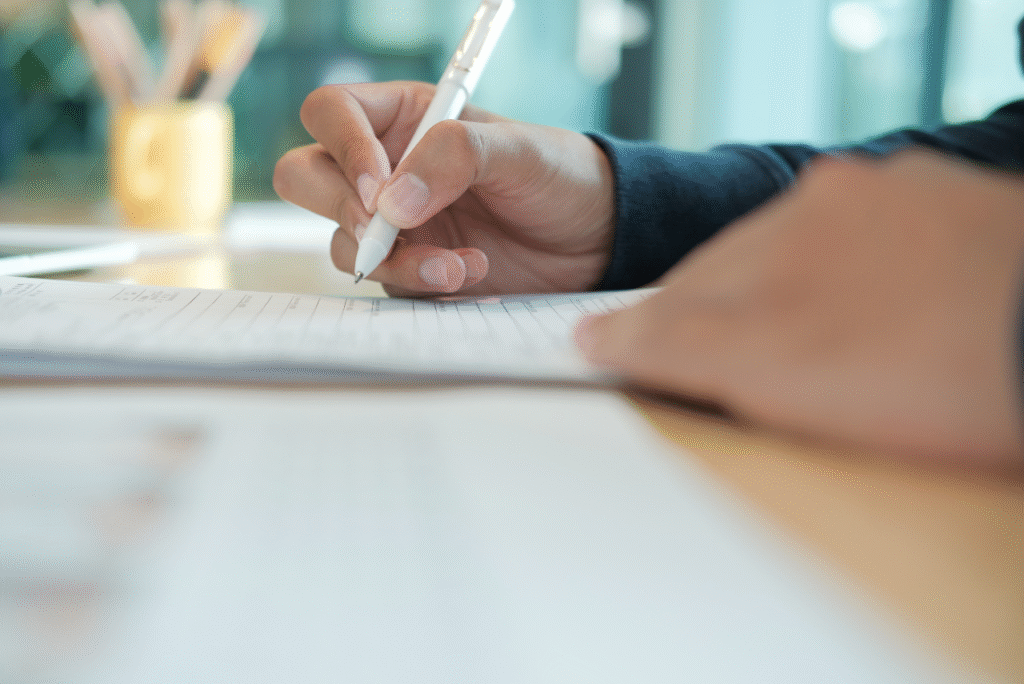
では、どうすれば、退職を防ぎ、社員が「この会社で働き続けたい」と、心の底から思えるような、「生きた人事制度」を、作ることができるのでしょうか。
その答えは、社長である、あなた自身が、「不在」の状態から、「制度の中心」に、帰還することです。
STEP1 社長が「誰に居続けてほしいか」を宣言する
制度作りの第一歩は、評価項目を考えることではありません。
まず、社長であるあなた自身が、「この会社に、誰に、居続けてほしいのか」を、全社員に向けて、明確に「宣言」することです。
それは、あなたの会社の「理想の人材像」であり、社長の「えこひいき」の基準です。
「私は、失敗を恐れずに挑戦する人に、居続けてほしい」 「私は、誰よりも顧客に誠実な人に、居続けてほしい」 「私は、チームのために自己犠牲を払える人に、居続けてほしい」
この、社長の覚悟のこもった「宣言」こそが、新しい「法律」の、基本理念となります。
STEP2 理念を等級・評価・報酬の法律に翻訳する
次に、その宣言した理念(えこひいきの基準)を、具体的な人事制度のルール、つまり「等級・評価・報酬」の法律の条文へと、「翻訳」していきます。
例えば、「挑戦する人」をえこひいきする、という理念があるならば。
・等級制度(身分法):
上位の等級に上がるための要件に、「前例のない挑戦の経験」を明記する。
・評価制度(刑法):
評価項目に「チャレンジ度」を設け、たとえ失敗しても、そのプロセスを評価する(罪に問わない)。
・報酬制度(褒章法):
最も果敢な挑戦をした人に、特別な報酬を与える。
このように、理念が、制度のあらゆる側面に、一貫して反映されるように、設計していくのです。
STEP3 社長自らが最初の法律遵守者となる
そして、最も重要なのが、この新しい「法律」を、社長自らが、誰よりも、厳格に遵守する姿を見せることです。
たとえ、個人的に親しい社員であっても、理念に反する行動を取ったならば、ルールに則って、厳しく律する。
逆に、普段は目立たない社員でも、理念を体現する素晴らしい行動を取ったならば、最大限の賞賛と報酬を与える。
この、立法者である社長の一貫した姿勢が、法律への信頼を生み、社員の心に、「この会社は、本気だ」という、揺るぎない納得感を育んでいくのです。
まとめ 制度を見直す前に理念を見直そう
人事制度が、退職の原因になる。
その本当の理由は、制度が「ある」からではなく、制度に「魂(理念)」が、ないからです。
退職を防ぐために、あなたが、今、見直すべきは、評価シートの項目ではありません。
社長である、あなた自身の、「理念」です。
あなたの会社には法律がありますか
最後に、社長であるあなたに、改めて問いかけます。
あなたの会社には、社員が「これこそが、私たちの誇りだ」と、胸を張って言えるような、明確な「法律」が、ありますか?
もし、その答えが「YES」でないのならば、退職の連鎖は、これからも止まらないかもしれません。
退職を防ぐ人事制度の個別相談
もし、あなたが、単なる「管理者」であることをやめ、「立法者」として、あなたの会社の「法律」を、本気で制定したいと願うならば、ぜひ、私にご相談ください。
私は、単なる制度の作り方を教えるのではありません。
社長であるあなたの「想い」を言語化し、それを「退職を防ぎ、社員を惹きつける」生きた制度へと昇華させる、そのプロセスを、ゼロから、共に行います。
あなたの会社が、社員にとって、最高の「居場所」となる、その第一歩を、共に踏み出せることを、心から楽しみにしています。
人事制度全般にお困りの方は、お気軽に村井にご相談ください!
➖ 資料請求 ➖
資料請求は下記バナーより。

➖ 問い合わせ ➖
新規事業、DX、人事制度などの経営課題に関するご相談は以下よりお受けしております。