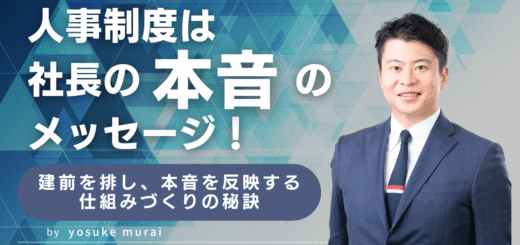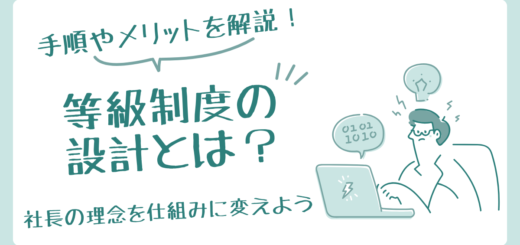人事評価制度の形骸化|原因は制度でなく「社長の不在」
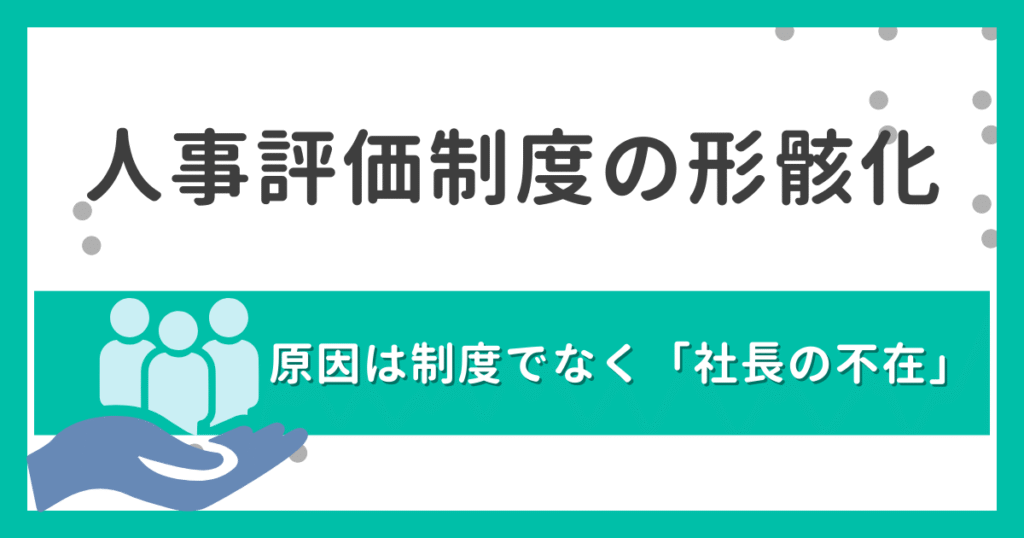
多大な時間とコストをかけて作り上げた、人事評価制度。
導入当初は、社員の成長や組織の活性化への期待に満ちていたはずです。
しかし、数年が経った今、その制度は、あなたの会社でどのように機能しているでしょうか。
評価シートの提出が、ただの「作業」になり、フィードバック面談が、形だけの「儀式」になっていませんか。
もし、そうだとすれば、あなたの会社の人事評価制度は「形骸化」という深刻な病に侵されているのかもしれません。
この記事では、多くの企業が陥る「形骸化」という病の正体を解き明かします。
この記事を読み終える頃には、あなたは、その本質的な原因に気づき、形骸化した制度に再び命を吹き込むための、確かな一歩を踏み出しているはずです。

【村井 庸介(むらい ようすけ)】
大学卒業後は株式会社野村総合研究所に入社し通信業・製造業の経営コンサルティングに携わる。その後リクルート、グリー、日本IBMに転職。その中でグリー株式会社にて人事制度設計に携わった。
2015年に独立後は、社員30名のベンチャー企業から5,000名を超える大企業まで幅広く人事制度設計や導入伴走に携わる。顧客業種は製造業、サービス、IT企業が中心。経営理念・事業戦略から逆算した人事制度構築を得意とする。
人事評価制度の形骸化とその兆候

人事評価制度の形骸化は、組織の活力を静かに、しかし確実に奪っていく静かなる病です。
まずは、その病の正体と、あなたの会社に現れているかもしれない危険な兆候について、正しく理解することから始めましょう。
形骸化とはどのような状態か
人事評価制度の「形骸化」とは、制度が「形」だけは残っているものの、その「実体」が失われ、本来の目的を果たさなくなった状態を指します。
本来、人事評価制度は、社員一人ひとりの成長を促し、その成長を会社の発展へと繋げるための、極めて重要な経営の仕組みです。
しかし、形骸化してしまった制度は、その機能を完全に喪失します。
評価は、ただ給与や賞与を決めるための、事務的な査定作業に成り下がります。
目標設定は、達成できそうな無難な目標を並べるだけの、アリバイ作りの場と化します。
フィードバック面談は、上司と部下の間に気まずい沈黙が流れる、ただの儀式になります。
誰もが「やっても意味がない」と感じながら、惰性で続けている。
それが、形骸化の恐ろしい実態なのです。
あなたの会社は大丈夫?
あなたの会社では、以下のような言葉や光景が見られませんか。
もし、一つでも当てはまるものがあれば、形骸化がすでに進行している危険なサインです。
「評価面談、5分で終わったよ」 「どうせ、評価なんて好き嫌いで決まるんでしょ?」 「評価シート、とりあえず埋めておけばいいや」 「目標設定?前期とほとんど同じ内容をコピーしただけ」 「自分の評価が、どうやって給与に反映されているのか、誰も知らない」
これらのサインは、社員が制度に対して、完全に信頼と期待を失っている証拠です。
制度が、社員の成長やモチベーション向上に、全く貢献していないことを示しています。
この状態を放置すれば、社員のエンゲージゲージメントは低下し、優秀な人材から静かに会社を去っていくという、最悪の事態を招きかねません。
なぜ人事評価制度は形骸化するのか
では、なぜ、多くの企業で人事評価制度は形骸化してしまうのでしょうか。
その原因は、一つではありません。
制度の目的が曖昧で、経営戦略と連動していなかったり。
評価項目が複雑すぎて、正しく評価することが困難だったり。
評価者への教育が不十分で、運用が現場任せになっていたり。
これらの、一般的に指摘される原因については、次の章で詳しく解説します。
しかし、私たちが本当に目を向けるべきは、これらの原因を生み出している、さらに根深い「本当の原因」なのです。
この記事では、その核心にまで、踏み込んでいきます。
形骸化の一般的な原因と対策

ここでは、多くの専門家やコンサルタントが指摘する、人事評価制度が形骸化する「一般的な原因」と、それに対する「一般的な対策」を、網羅的に見ていきましょう。
これらは、いわば病気の「症状」に対する治療法です。
まずは、これらの基本をしっかりと押さえることが重要です。
原因1:目的の不明確さとその対策
最も多く見られる原因は、そもそも「何のために人事評価制度を導入したのか」という目的が、不明確であるか、社員に全く共有されていないケースです。
「流行っているから」「会社としての体裁を整えるため」といった理由で導入された制度は、魂のない抜け殻と同じです。
この場合の対策は、制度の目的を再定義し、明確に言語化することです。
「人材育成」「業績向上」「企業文化の浸透」など、自社が制度を通じて何を達成したいのか、その目的を、経営陣から全社員に向けて、繰り返し発信し続ける必要があります。
原因2:制度の複雑化とその対策
公平性を追求するあまり、評価項目をやみくもに増やし、評価基準を細分化しすぎた結果、制度が複雑怪奇になってしまうケースも少なくありません。
複雑すぎる制度は、評価者である管理職の理解が追いつかず、正しい評価を困難にします。
また、評価業務にかかる時間も増大させ、現場の大きな負担となります。
この場合の対策は、制度の簡素化、つまり「評価項目の絞り込み」です。
本当に重要な評価項目は、実はそれほど多くないはずです。
会社の理念やビジョンに直結する、最も重要な3〜5つの項目に絞り込む勇気が、形骸化を防ぎます。
原因3:運用体制の不備とその対策
どれだけ素晴らしい制度を作っても、それを運用する体制が整っていなければ、絵に描いた餅で終わってしまいます。
特に、「評価者への教育不足」と「フィードバックの不徹底」は、運用不備の二大要因です。
評価者である管理職が、評価基準や面談の方法を正しく理解していなければ、評価は個人の主観や価値観に左右され、不公平感を生み出します。
対策としては、定期的な「評価者研修」の実施が不可欠です。
また、評価結果を本人に伝えるフィードバック面談が、ただの結果通知で終わっていたり、そもそも実施されていなかったりすれば、社員は成長の機会を失います。
評価とフィードバックは、必ずセットで運用することを、会社の公式ルールとして徹底する必要があります。
原因4:評価者の負担感とその対策
形骸化の大きな要因として、評価者である管理職が感じる「負担感」も無視できません。
通常業務に加えて、部下一人ひとりの目標設定から、評価シートの作成、フィードバック面談まで、その業務量は膨大です。
この負担感が、評価を「早く終わらせたい作業」へと変えてしまいます。
対策としては、まず会社として、評価業務を「管理職の重要な責務である」と位置づけ、そのための時間を物理的に確保することが必要です。
また、評価プロセスを支援するITツールやシステムを導入することも、負担軽減に有効な手段と言えるでしょう。
形骸化の本当の原因は社長の不在

ここまで、形骸化の一般的な原因と対策を見てきました。
しかし、断言します。
これらはすべて、病気の「症状」に対する対症療法に過ぎません。
いくら薬を飲んでも、病気の「根本原因」を治療しない限り、形骸化という病は、必ず再発します。
その根本原因とは、ただ一つ。「社長の不在」です。
なぜ社長は制度から不在になるのか
もちろん、社長が物理的に会社にいない、という意味ではありません。
ここで言う「不在」とは、人事評価制度という、会社の最も重要な仕組みの中心に、社長の「魂」や「意思」が存在していない、という状態を指します。
制度を設計する段階では、社長も熱心に関わっていたかもしれません。
しかし、いざ運用が始まると、「あとは人事部に任せた」と、現場から遠ざかってしまう。
日々の経営に追われ、人事評価という、すぐに結果が出ないテーマへの関心が薄れてしまう。
あるいは、人に評価を下すという、精神的な負担の大きい仕事から、無意識のうちに距離を置いてしまう。
こうして、社長は、自らが創ったはずの制度の「当事者」から、いつしか「傍観者」へと変わってしまうのです。
社長の不在が会社の法律を無効にする
著者の考え方の根幹には、「人事評価制度は、会社という王国の法律である」という思想があります。
そして、その法律を制定し、その法律の正当性を保証する最高責任者は、社長以外にあり得ません。
もし、国の最高責任者が、自らが定めた法律に全く関心を示さず、その運用を役人に丸投げしていたとしたら、その法律は、国民から尊重されるでしょうか。
答えは、言うまでもありません。
法律は、あっという間に形骸化し、誰も守らない、ただの紙切れになるでしょう。
人事評価制度も、全く同じです。
社長が「不在」になった瞬間、その制度は、拠り所となるべき「魂」を失い、ただの抜け殻、つまり形骸化へと向かって、一直線に進み始めるのです。
どんな対策も対症療法で終わる理由
社長が不在のまま、人事部がいくら制度の簡素化や、評価者研修といった「対策」を講じても、それは根本的な治療にはなり得ません。
なぜなら、社員が本当に知りたいのは、「評価シートの書き方」といったテクニックではないからです。
彼らが知りたいのは、「この会社は、どこへ向かっているのか」「社長は、私たちに何を期待しているのか」という、会社の「意思」そのものです。
その「意思」を語れるのは、社長、ただ一人です。
社長が不在のまま行われるどんな対策も、社員の心には響かず、一時しのぎの対症療法で終わってしまうのは、必然なのです。
「社長の不在」を解決する本質的な形骸化対策

では、どうすれば、形骸化した制度を根本から再生させることができるのでしょうか。
その方法は、ただ一つ。
「不在」だった社長が、再び、制度の中心に「帰還」することです。
ここでは、そのための具体的な3つのステップをご紹介します。
社長が制度の魂として帰還する
最初のステップは、社長であるあなた自身が、「人事評価制度の最高責任者は、この私である」と、改めて覚悟を決めることです。
そして、その覚悟を、役員や社員に向けて、明確に宣言してください。
「これからの我が社の人事評価は、私の理念を反映した、最も重要な経営の仕組みとして、私自身が責任を持って運用していく」
この力強い宣言こそが、形骸化した制度に、再び命の火を灯す、最初の狼煙となります。
それは、制度に「魂」が戻ってきた瞬間です。
社長が「誰をえこひいきするか」を再定義する
次に、社長がやるべきことは、あなたの会社の「法律」の根幹を、自らの言葉で再定義することです。
それは、「今、この会社で、最も賞賛され、報われるべきは、どのような価値観を持ち、どのような行動をする人材なのか」という、会社の「えこひいき」の基準を、明確に言語化する作業です。
それは、5年前と同じ答えでしょうか。
会社の成長ステージや、市場環境の変化に応じて、求める人材像も変わっているはずです。
この「えこひいき」の基準こそが、全ての評価の拠り所となります。
この基準が明確であれば、制度は、自ずとシンプルになり、評価者の負担も、劇的に軽減されるのです。
社長自らが理念の伝道師となる
最後のステップは、再定義した理念、つまり新しい「法律」を、社長自らが、あらゆる場面で語り続けることです。
朝礼で語り、会議で語り、社内報で語り、そして何より、社員一人ひとりとの対話の中で、熱く語るのです。
社長の言葉は、どんな精緻なマニュアルよりも、力強く、社員の心に浸透していきます。
社長が、誰よりも楽しそうに、自社の理念を語り、その理念を体現する社員を賞賛する。
その姿を見せることで、形骸化した制度は、再び、社員の成長と会社の未来を創るための、生きた仕組みとして、力強く脈動を始めるのです。
社長は、制度の「監視者」ではなく、理念を伝える「伝道師」でなければなりません。
まとめ

人事評価制度の形骸化。
その問題の根源は、制度の設計や運用といった、テクニカルな部分にあるのではありません。
それは、社長が、制度の魂であるべき「理念」から、どれだけ遠ざかってしまっているか、という、極めてシンプルで、しかし本質的な問題なのです。
人事評価制度の形骸化を防ぐ第一歩
形骸化を防ぎ、制度を再生させるための第一歩。
それは、評価シートの項目を見直すことではありません。
新しい評価システムを導入することでもありません。
まず、社長であるあなた自身が、一人で静かに、自社の理念と向き合う時間を取ることです。
そして、「自分は、どんな仲間と、どんな未来を創りたいのか」という、原初の問いに、もう一度、立ち返ることです。
その答えが見つかった時、あなたの会社の人事評価制度は、本当の意味で、再生への道を歩み始めるでしょう。
制度再生のための個別相談のご案内
もし、あなたが、自社の理念と向き合い、それを「生きた制度」へと昇華させるプロセスにおいて、信頼できるパートナーを必要としているならば、ぜひご相談ください。
あなたの会社の「魂」を言語化し、それを組織の隅々にまで浸透させるための、具体的なお手伝いをすることができます。
あなたの会社が、形骸化の長いトンネルを抜け出し、再び力強く成長していく、その第一歩を、共に踏み出せることを、心から楽しみにしています。
人事評価制度にお困りの方は、お気軽に村井にご相談ください。
➖ 資料請求 ➖
資料請求は下記バナーより。

➖ 問い合わせ ➖
新規事業、DX、人事制度などの経営課題に関するご相談は以下よりお受けしております。