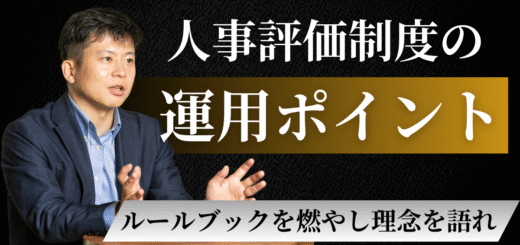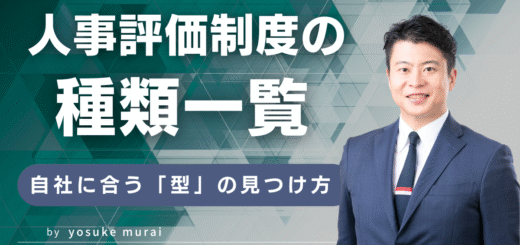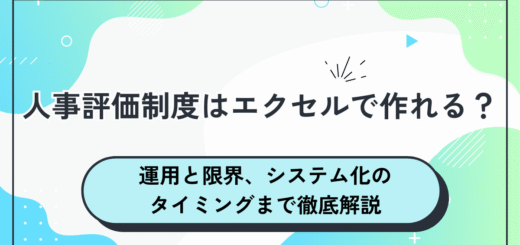人事評価制度の失敗事例|その失敗、原因は社長にあります!?
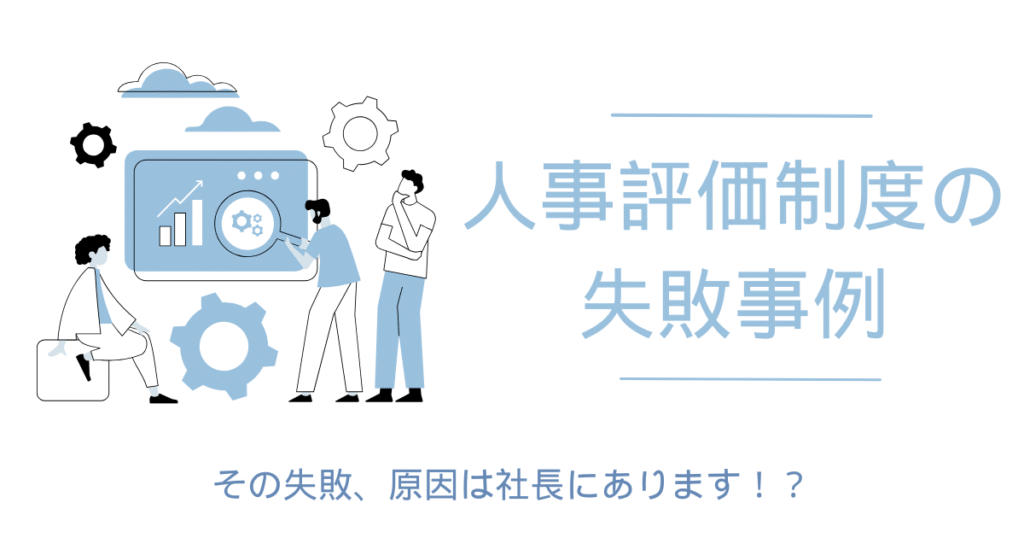
なぜ、良かれと思って導入した人事評価制度が、社員の不満を生み、組織を蝕んでしまうのか。
多くの経営者や人事担当者が、この問いに頭を悩ませています。
世の中には、数々の「人事評価制度の失敗事例」が溢れており、それらを読んで「うちの会社は大丈夫だろうか」と、不安に感じている方も少なくないでしょう。
この記事では、まず、多くの企業が経験する典型的な失敗事例とその一般的な原因を、網羅的に解説します。
もし、あなたが本気で、失敗しない人事評価制度を創りたいと願うなら、是非最後までお付き合いください。

【村井 庸介(むらい ようすけ)】
大学卒業後は株式会社野村総合研究所に入社し通信業・製造業の経営コンサルティングに携わる。その後リクルート、グリー、日本IBMに転職。その中でグリー株式会社にて人事制度設計に携わった。
2015年に独立後は、社員30名のベンチャー企業から5,000名を超える大企業まで幅広く人事制度設計や導入伴走に携わる。顧客業種は製造業、サービス、IT企業が中心。経営理念・事業戦略から逆算した人事制度構築を得意とする。
人事評価制度でよくある失敗事例

まずは、あなたの会社の現状を客観的に把握するために、多くの企業が陥りがちな「よくある失敗事例」を見ていきましょう。
これは、決して他人事ではありません。
あなたの会社でも、静かに進行している悲劇かもしれません。
失敗事例1:社員の納得感が得られずモチベーションが低下
最も多く聞かれる失敗事例が、これです。
制度を導入した結果、社員から「評価基準が曖訪で、上司の好き嫌いで評価が決まっている」「自分の頑張りが、正当に評価されていない」といった声が噴出する。
評価への納得感が得られない社員は、次第に仕事への情熱を失い、組織全体のモチベーションは、見る見るうちに低下していきます。
「頑張っても、どうせ報われない」という空気が蔓延した組織の未来は、決して明るいものではありません。
失敗事例2:制度が形骸化し誰も本気にしない
導入当初は、誰もが真剣に取り組んでいたはずの人事評価制度。
しかし、数年も経つと、いつの間にか、誰も本気にしない「形骸化」した儀式になってしまう。
これも、非常によくある失敗事例です。
目標設定は、とりあえず当たり障りのない項目を埋めるだけの「作業」と化し、評価面談は、5分で終わる「形式的なイベント」になる。
制度が、本来の目的である「人材育成」や「組織の活性化」に、全く貢献しなくなるのです。
時間と労力だけがかかる、無意味な制度。
それが、形骸化の正体です。
失敗事例3:個人主義が蔓延しチームワークが崩壊
特に、個人の成果を重視する「成果主義」を、安易に導入した企業で頻発する失敗事例です。
自分の評価を上げることだけを考える社員が増え、部署やチーム内での協力体制が失われます。
同僚は「仲間」ではなく「ライバル」となり、ノウハウの共有は行われず、足の引っ張り合いが横行する。
結果として、個々の社員は高い成果を上げていたとしても、組織全体としてのパフォーマンスは、著しく低下してしまうのです。
失敗事例4:優秀な人材から会社を去っていく
そして、これら全ての失敗事例が、最終的に行き着く先。
それが、「優秀な人材の流出」です。
成長意欲が高く、会社への貢献意識も強い、本来、会社に最も居続けてほしいはずのエース社員ほど、不公平で、形骸化した、チームワークを阻害するような評価制度に、強い失望を覚えます。
そして、「この会社にいても、自分の未来はない」と見切りをつけ、より良い環境を求めて、静かに、しかし確実に、あなたの会社を去っていくのです。
これは、会社にとって、計り知れない損失と言えるでしょう。
失敗事例の一般的な原因と対策

では、なぜ、このような悲劇的な失敗事例が、後を絶たないのでしょうか。
ここでは、多くの専門家が指摘する、失敗の「一般的な原因」と、それに対する「一般的な対策」を、整理しておきましょう。
目的の不明確さと経営戦略とのズレ
失敗の最も根源的な原因の一つが、そもそも「何のために人事評価制度を導入するのか」という目的が、不明確であることです。
「他社もやっているから」という理由だけで導入された制度は、羅針盤のない船と同じです。
対策としては、まず「人材育成」「業績向上」「理念浸透」など、制度導入の目的を明確に言語化し、それが会社の経営戦略と、どのように連動しているのかを、全社員に明確に示す必要があります。
評価基準の曖昧さと評価者のスキル不足
次に多いのが、評価基準が曖昧で、評価者である管理職の主観や解釈に、評価が大きく左右されてしまうケースです。
これでは、社員が不公平感を抱くのも当然です。
対策としては、評価基準を、誰が見ても同じ解釈ができるように、具体的な行動レベルの言葉で定義すること。
そして、評価者がその基準を正しく運用できるよう、定期的な「評価者研修」を実施し、評価スキルと目線を合わせることが、不可欠です。
フィードバック不足とコミュニケーション不足
評価結果を、ただ一方的に通知するだけで、その理由や、次の成長に向けた具体的なアドバイスが、全く行われない。
このような、フィードバックとコミュニケーションの不足も、失敗の大きな原因です。
社員は、自分がなぜその評価になったのかを理解できず、次に何をすれば良いのかも分かりません。
対策としては、評価面談を「結果を伝える場」から「成長を支援する対話の場」へと、再定義すること。
そして、期末の面談だけでなく、1on1ミーティングなどを通じて、日頃から上司と部下が、密なコミュニケーションを取る文化を醸成することが重要です。
全ての失敗事例の本当の原因は社長の不在?

さて、ここまで見てきた「一般的な原因と対策」は、どれも正論であり、もちろん実践すべきことです。
しかし、断言します。
これらは全て、病気の「症状」に対する、対症療法に過ぎません。
本当の「病巣」は、もっと深く、そして、もっと経営の根幹に関わる部分にあるのです。
その病巣とは、ただ一つ。「社長の不在」です。
なぜ社長は制度から「不在」になってしまうのか
もちろん、社長が物理的に会社にいない、という意味ではありません。
ここで言う「不在」とは、人事評価制度という、会社の最も重要な仕組みの中心に、社長の「魂」や「意思」が存在していない、という状態を指します。
制度を設計する段階では、社長も熱心だったかもしれません。
しかし、運用が始まると、「あとは人事部に任せた」と、現場から遠ざかってしまう。
人に評価を下すという、精神的な負担の大きい仕事から、無意識のうちに距離を置いてしまう。
こうして、社長は、自らが創ったはずの制度の「当事者」から、いつしか「傍観者」へと、変わってしまうのです。
社長の不在が「会社の法律」を無効にする
著者の思想の根幹には、「人事評価制度は、会社という王国の法律である」という考え方があります。
そして、その法律の正当性を保証する最高責任者は、社長以外にあり得ません。
もし、国の最高責任者が、自らが定めた法律に関心を示さず、その運用を役人に丸投げしていたら、どうなるでしょう。
その法律は、国民から尊重されず、あっという間に形骸化し、誰も守らない、ただの紙切れになるはずです。
人事評価制度も、全く同じです。
社長が「不在」になった瞬間、その制度は、拠り所となるべき「魂」を失い、全ての失敗事例へと繋がる、坂道を転がり始めるのです。
どんな対策も対症療法で終わる理由
社長が不在のまま、人事部がいくら評価基準を明確化し、評価者研修を実施しても、それは根本的な治療にはなり得ません。
なぜなら、社員が本当に知りたいのは、「評価シートの書き方」といったテクニックではないからです。
彼らが知りたいのは、「この会社は、どこへ向かっているのか」「社長は、私たちに何を期待しているのか」という、会社の「意思」そのものです。
その「意思」を、最終的な責任と情熱を持って語れるのは、社長、ただ一人です。
社長が不在のまま行われるどんな対策も、社員の心には響かず、一時しのぎの対症療法で終わってしまうのは、必然なのです。
社長が失敗を成功に変えるための本質的な対策

では、どうすれば、この失敗の連鎖を断ち切り、人事評価制度を、本当に機能する仕組みへと、再生させることができるのでしょうか。
その方法は、ただ一つ。
「不在」だった社長が、再び、制度の中心に「帰還」することです。
社長が制度の魂として帰還する
最初のステップは、社長であるあなた自身が、「人事評価制度の最高責任者は、この私である」と、改めて覚悟を決めることです。
そして、その覚悟を、役員や社員に向けて、明確に宣言してください。
「これからの我が社の人事評価は、私の理念を反映した、最も重要な経営の仕組みとして、私自身が責任を持って運用していく」
この力強い宣言こそが、失敗の連鎖を断ち切る、最初の狼煙となります。
それは、制度に「魂」が戻ってきた瞬間です。
社長が誰をえこひいきするかを再定義する
次に、社長がやるべきことは、あなたの会社の「法律」の根幹を、自らの言葉で再定義することです。
それは、「今、この会社で、最も賞賛され、報われるべきは、どのような価値観を持ち、どのような行動をする人材なのか」という、会社の「えこひいき」の基準を、明確に言語化する作業です。
それは、5年前と同じ答えでしょうか。
会社の成長ステージや、市場環境の変化に応じて、求める人材像も変わっているはずです。
この「えこひいき」の基準こそが、全ての評価の拠り所となります。
この基準が明確であれば、制度は、自ずとシンプルになり、社員の納得感も、劇的に高まるのです。
社長自らが理念の伝道師となる
最後のステップは、再定義した理念、つまり新しい「法律」を、社長自らが、あらゆる場面で語り続けることです。
朝礼で語り、会議で語り、社内報で語り、そして何より、社員一人ひとりとの対話の中で、熱く語るのです。
社長の言葉は、どんな精緻なマニュアルよりも、力強く、社員の心に浸透していきます。
社長が、誰よりも楽しそうに、自社の理念を語り、その理念を体現する社員を賞賛する。
その姿を見せることで、失敗続きだった制度は、再び、社員の成長と会社の未来を創るための、生きた仕組みとして、力強く脈動を始めるのです。
社長は、制度の「傍観者」ではなく、理念を伝える「伝道師」でなければなりません。
まとめ:失敗の原因は社長 あなたを救うのも社長自身
人事評価制度の、数々の失敗事例。
その根本原因をたどっていくと、私たちは、常に、同じ一つの結論に行き着きます。
その失敗の原因は、制度でも、運用でも、管理職でもない。
その原因は、社長、あなた自身にあるのかもしれない、ということです。
人事評価制度の失敗を乗り越える第一歩
しかし、どうか、絶望しないでください。
なぜなら、失敗の原因が社長にあるということは、その失敗を成功に変えることができるのも、また、社長であるあなた自身しかいない、という希望をも意味するからです。
失敗を乗り越えるための第一歩。
それは、外部のコンサルタントに相談することではありません。
まず、社長であるあなたが、一人で静かに、自社の理念と向き合う時間を取ることです。
そして、「自分は、どんな仲間と、どんな未来を創りたいのか」という、原初の問いに、もう一度、立ち返ることです。
その答えが見つかった時、あなたの会社の人事評価制度は、本当の意味で、再生への道を歩み始めるでしょう。
失敗しない制度作りを支援する個別相談のご案内
もし、あなたが、自社の理念と向き合い、それを「失敗しない、生きた制度」へと昇華させるプロセスにおいて、信頼できるパートナーを必要としているならば、ぜひ、私たちにご相談ください。
私たちは、あなたの会社の「魂」を言語化し、それを組織の隅々にまで浸透させるための、具体的なお手伝いをすることができます。
あなたの会社が、失敗の長いトンネルを抜け出し、新たな成長への道を力強く歩み出す、その第一歩を、共に踏み出せることを、心から楽しみにしています。
人事評価制度にお困りの方は、お気軽に村井にご相談ください。
➖ 資料請求 ➖
資料請求は下記バナーより。

➖ 問い合わせ ➖
新規事業、DX、人事制度などの経営課題に関するご相談は以下よりお受けしております。