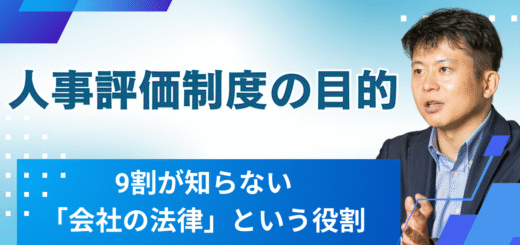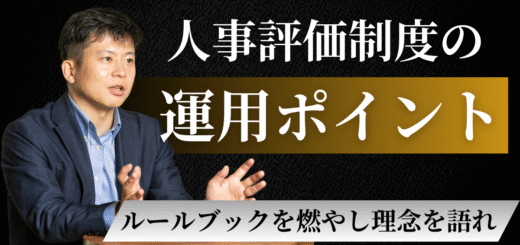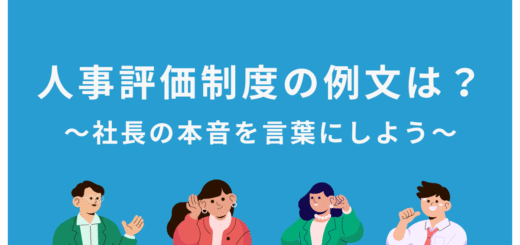失敗しない人事制度設計の進め方

このコラムではクラフトビール会社の新規事業で年商1億円を達成してから1.5倍2倍へと成長させてきた村井が、その実践的なノウハウを紹介しています。
またコンサルティング会社として新規事業の立ち上げをサポートした、または大手の会社とのお仕事から培ってきた経験をお届けしています。
以前の記事で、「人事制度が社長の本音をどれほど反映しているか」が企業の成長や定着率を大きく左右することをご紹介しました。
実際、「3か月で新制度を完成させてほしい」と急ぐあまり、現場が混乱し、優秀な人材が離れてしまうケースも珍しくありません。
そこで、今回は短期導入で生じやすい手戻りや離職リスクをどのように回避し、制度を成功に導くかを解説します。
必要な期間設定、戦略との整合性、そして管理職の事前教育という三つの視点から、人事制度を「形だけ」で終わらせない具体策を掘り下げていきましょう。

【村井 庸介(むらい ようすけ)】
大学卒業後は株式会社野村総合研究所に入社し通信業・製造業の経営コンサルティングに携わる。その後リクルート、グリー、日本IBMに転職。その中でグリー株式会社にて人事制度設計に携わった。
2015年に独立後は、社員30名のベンチャー企業から5,000名を超える大企業まで幅広く人事制度設計や導入伴走に携わる。顧客業種は製造業、サービス、IT企業が中心。経営理念・事業戦略から逆算した人事制度構築を得意とする。
制度設計に十分な期間をかける必要性

「3か月でさっと作り上げてほしい」。
経営陣からはよく挙がる声ですが、人事制度は企業全体の基盤を大きく動かすため、部分的な改定ならまだしも、全体の見直し、再構築には9か月から1年の慎重な準備が必要とされています。
ここでは、その理由を改めて見ていきましょう。
まず、経営陣の「未来像」や「企業のありたい姿」を丁寧に整理する作業が欠かせません。
これは、前回の記事で内容を解説しました。
どのような経営戦略を描き、どんな組織や人材を育てたいのかを経営トップや役員から引き出し、言葉にする工程です。
経営陣インタビューを通じて、5年後・10年後のビジョンと、そこへ至るために必要な企業文化や組織構造をすり合わせておくことで、制度設計が明確な方向性を持って進められます。
もしこの工程を省略してしまうと、たとえば、社長は「若手を重用したい」と言い、専務は「ベテランを手厚く処遇したい」と考えている場合、両者の想いがすり合わないまま制度を作り始めると、導入後に「目指す方向が違う」と気づいてしまうかもしれません。
導入後に「そもそも我々が目指したい方向と違う」ということで、ちゃぶ台返しが発生するリスクが高まります。
社員インタビューは“ギャップ”を見つけるためのものです。
社員インタビューを実施する際、意見をすべて制度に反映するわけではありません。
重要なのは、経営陣のメッセージと現場の認識にどれほどギャップがあるかを把握することです。
たとえば社長は「若手抜擢」を打ち出していても、現場には「ベテラン優先が変わらない」という空気が根強いかもしれません。
こうしたズレを見極めることが、後の混乱を防ぐカギになります。
詳細設計の調整

さらに、等級・評価・報酬などの詳細設計には、シミュレーションと各要素の細かい調整が必要です。
特に等級や報酬の見直しをする際は、
「具体的に誰がどの等級に入るのか」
「その人は本当にその等級でよいのか」
など、バイネームでの検証を行いながら、
「従来よりも給与が下がる社員がどれくらい出るか」
「人件費が底上されても会社の利益は担保できるか」
といった細かい調整をしなければなりません。
この作業を短期間で急いで行うと、想定外に会社の収益を圧迫し、経営そのものを危機に陥れかねません。
特に、評価基準が曖昧だったり、昇給額や賞与支給額が社員の納得を得られなかったりすると、人事制度が形骸化してしまう可能性が大きくなります。
例えば、
「管理職が部下との衝突を避けようとする」
「評価基準が曖昧で、公平性の観点が欠けている」
などの要因から評価が総じて甘くなる制度となると、
想定以上に昇給者が増え、早期から総人件費が大幅に膨らんでしまうリスクがあります。
昇給原資を圧迫すれば、次年度以降の賞与や新たな人材への投資に割けるリソースが減り、経営そのものに影響を及ぼすことにもなりかねません。
こうしたトラブルは、制度全体の信頼を大きく損ない、せっかくの新制度が社員から敬遠される「形だけの制度」に陥るリスクが高いのです。
研修時間の想定

加えて、制度導入後には社内説明や評価者向け研修の時間が必要となります。
管理職やマネージャーが新たな人事制度の意図を理解し、
運用方法を習得するためにじっくり研修を行わなければ、現場と経営陣の温度差が生まれ、社員がスムーズに受け入れられない恐れがあります。
これについては、後段で詳細の解説をします。
これらを考慮すると、わずか3か月程度で走り切ろうとすると、経営陣の意図を取りこぼしたまま制度を形にする恐れがあります。
もちろん、企業規模や導入範囲によっては、3か月で評価項目の見直しだけリリースし、昇給や報酬テーブルの大幅改定は次年度に持ち越すなど、段階的な導入も選択肢に入ります。
しかし、その場合でも「最終的な全体像」を描きながら進めないと、途中で方針がぶれて混乱を招きかねません。
そして、原則として、評価基準は1年間同じものを運用した方が社員の納得度を得やすいです。
前向きな改善は良いですが、ソフトウェアのように多頻度にアップデートを行うと、かえって混乱を招きます。
だからこそ、焦らずに十分な期間を確保し、段階的に検討と合意形成を進めることが求められます。
もし、年度途中にどうしても必要な修正がある場合は、社内周知や説明を丁寧に行い、混乱を最小限にとどめるようにしましょう。
また、この期間を通じて経営陣も改めて「どのような人材に、どのような評価を与えたいのか」「どんな行動を企業として推奨し、成果をどう定義するのか」を深く考える機会を得られます。
制度は単なる評価や報酬の仕組みではなく、企業が将来に向けてどう成長し、どんな文化を育むかを形づくる重要なツールでもあります。
そのため、制度づくりを急いで進めるよりも、9か月から1年の時間を投資して熟慮することで、導入後のブレを最小限に抑え、社員からの信頼を得やすい制度を構築できるのです。
このように、6か月ではなく9か月から1年かけて制度設計を行う利点は多岐にわたります。
経営陣と現場との認識合わせ、詳細設計のシミュレーション、導入前の研修や説明会をゆとり持って行うことで、
短期導入による不満やトラブルを大幅に削減できるのです。結果として、社員の納得感を伴いながら制度が運用されるという好循環が生まれます。
結局のところ、「3か月ですぐ作ってほしい」という要望は、一見するとスピード感があって魅力的なように思えますが、
それに伴うリスクは大きく、後々の手戻りやコスト増につながる可能性が高いと言えます。
一度走り出すと止めづらい制度だからこそ、焦らずに必要な期間を確保して慎重に進めるのが、成功への近道なのです。
戦略と組織のありたい姿を一致させる

「数字のシミュレーションを先にやりたくなる」のは、多くの企業で共通の傾向ですが、その前に必ず押さえておきたいのが「企業としての戦略や組織のありたい姿」と人事制度をどう結びつけるか、という視点です。
では「どんな組織を目指すのか」を十分に考えずに制度を作ると、何が起こるでしょうか。
たとえば、チームワークを競争力の要とする企業が、極端に個人の成果を重視する評価項目に変更した結果、「互いに助け合わなくなる」「情報共有が滞る」という事態に陥ることがあります。
経営トップの本音とは逆行した結果、制度が形骸化するリスクが高まるのです。
「評価基準をどう定めるか」
「昇給額をどのようなテーブルにするか」
「賞与の原資はどのようなロジックで決めるか」
といった、細かい部分の設計の話に一足飛びで話が実際の現場では起こりがちです。です。
たしかにシミュレーションを正確に行うことは重要ですが、“枝葉”の部分にすぎません。
本来もっとも大切なのは「経営戦略」と「組織のありたい姿」をしっかりと一致させることです。
ここが曖昧だと、いくら精密なルールを作っても、組織全体が目指すべき方向と制度が噛み合わず、結果的に社員の不満や混乱を引き起こすリスクが高まります。
たとえば、チームワークを競争優位としている企業が、個人の数値成果を過度に重視する人事制度に切り替えれば、
しばらくは業績が伸びるかもしれませんが、長期的には協力関係が希薄になり、一体感を失う恐れがあります。
その他、以前紹介したIT企業では、過去に貢献したベテラン社員が管理職を独占し、若手が昇格しにくい構造が業績停滞の一因でした。
経営トップが「若手のイノベーションを軸に成長したい」という戦略を掲げ、それに合わせて昇格基準を実力・成果重視へ切り替えたところ、優秀な若手が積極的にリーダーシップを発揮するようになりました。
結果として、若手のアイデアが活かされるようになり、売上だけでなく採用力の強化や離職率の低下にもつながりました。まさに「戦略と人事制度が噛み合ったからこそ生まれた成功例」といえます。
ここで重要なのは、表面的に「若手の抜擢を重視する」と言うだけでなく、実際に給与や評価の仕組みにその考えを反映させた点です。
具体的なルールが戦略と合致すること

つまり、「どんな行動をどう評価するか」という具体的なルールが、戦略と合致したからこそ効果を発揮しました。
また、組織のありたい姿を先に明確にすることには、「変化に耐えうる」メリットもあります。
仮に数年後、外部環境が変わって戦略の一部を修正しなければならなくなっても、
組織として大切にしている文化や基準がはっきりしていれば、大幅な改変を行わなくても部分的な見直しだけで十分に対応できる場合が多いのです。
評価制度や報酬体系を都度根こそぎ変えてしまうと、社員の混乱が大きくなりますが、
戦略と組織文化の軸が通っていれば、比較的スムーズに修正が進みやすくなります。
結局のところ、
「私たちはこの企業をどんな方向に伸ばしたいのか」
「そのために社員にどんな行動や能力を発揮してほしいのか」
という点を、経営陣が徹底的に議論し、管理職も含めて周知することが不可欠です。
これを端折って細かいルールだけ先に決めてしまうと、導入後に「なぜこの基準なのか」「どうして協力よりも個人目標が優先されるのか」といった戸惑いや不満が噴出する恐れがあります。
戦略と組織文化を前提に制度を組み立てることで、制度が長期的に機能し、企業の成長と目標達成をしっかりと後押しする基盤となるのです。
管理職の事前教育が制度の成否を握る

制度の設計が万全でも、それを運用し社員と向き合うのは管理職です。
ここで管理職が制度の意図や評価基準を理解せず、表面的に評価シートを埋めるだけになってしまえば、
社員の納得感が得られず、制度そのものが形骸化するリスクが高まります。
管理職は、いわば「経営陣のメッセージを現場に伝える代理人」です。
例えば、社長が「若手抜擢」を口にしていても、
評価する側である管理職がその考えを理解していなければ、実際には従来の年功序列的評価が続いてしまいます。
また、部下が数値目標を達成できなかったとしても、
チーム貢献やイノベーションを見逃さずに評価できるのか――
こうした判断は、管理職が制度の背景や狙いをどれほど“腹落ち”しているかにかかっています。
具体的には、ロールプレイで「数値目標を未達だが、新人指導に力を尽くした中堅社員との評価面談」を想定し、どのように声かけをし、
どんなアクションプランを示すのかを管理職同士で練習します。
たとえば、未達ではあるが、新人指導を通じてチーム全体のミス削減や業務効率化に寄与している場合は、
「短期的な目標数字が未達でも、社内貢献を正当に評価する」ルールを明確化しておき、
管理職が評価面談で「あなたの指導によってこれだけの改善が生まれた」と定量・定性の両面からフィードバックする、という形です。
こうした訓練を事前に行っておけば、「業績未達だが組織に重要な役割を果たしている社員」をどう評価し、
どのように次の目標を設定するかを落ち着いて説明できるようになります。
そうした事前トレーニングを経てこそ、管理職は制度を自分の言葉で語り、社員とのコミュニケーションをスムーズに行えるようになるのです。
加えて、管理職は現場の声を経営陣へフィードバックする役割も担います。
制度の導入後、予期せぬ部分で不満や混乱が発生するかもしれませんが、
その際に「現場では実はこういう障害が出ています」と素早く報告し、経営陣と協力して微調整を図ることができれば、制度は運用と共に進化していきます。
管理職が単に“評価するだけ”ではなく、“制度を育てる担い手”として認識しているかどうかが、導入後の組織全体の満足度や運営の安定度を大きく左右するのです。
まとめ
「3か月ですぐ作ってほしい」
経営陣からは魅力的に思われる言葉ですが、人事制度は一度導入すると止めづらく、頻繁に修正すれば社員の不信感を招くリスクも非常に高いものです。
こうして焦らずに9か月から1年をかけて制度設計すれば、
導入後も混乱や不満が少なく、社員の納得感を得やすい形で運用が進むでしょう。
結果的には企業の成長を加速する原動力となり、採用力や定着率の向上にも貢献するはずです。
そして、導入前の管理職教育を徹底し、評価者自身が制度の狙いや背景を深く理解し、部下と正面から向き合える体制を築くことが不可欠です。
管理職を“運用の主体”として位置付け、ロールプレイや面談のトレーニングを行うことで、組織全体が新制度のメリットを実感しやすくなるでしょう。
人事評価制度にお困りの方は、お気軽に村井にご相談ください。
➖ 資料請求 ➖
資料請求は下記バナーより。

➖ 問い合わせ ➖
新規事業、DX、人事制度などの経営課題に関するご相談は以下よりお受けしております。