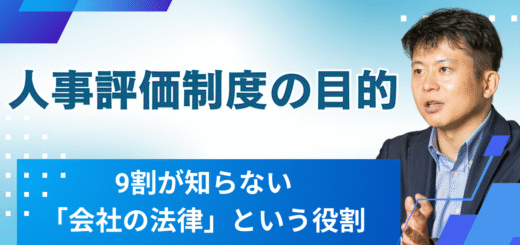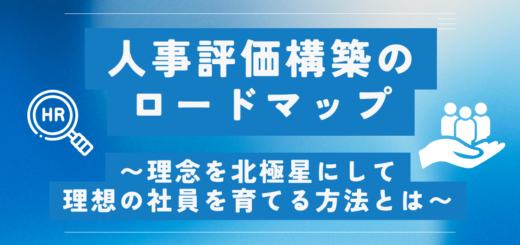人事評価制度コンサルは不要?社長が本当に考えるべきこと
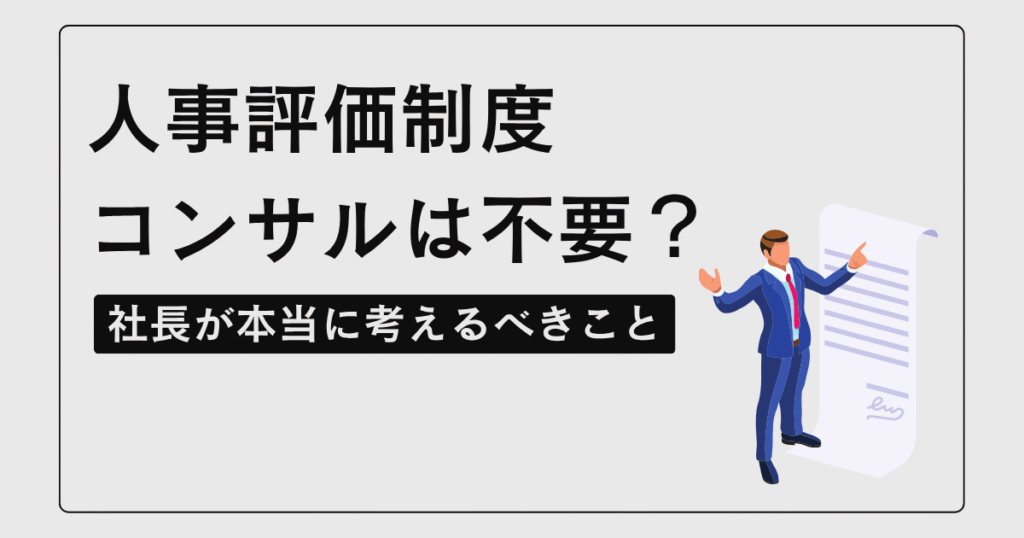
社長、時間と費用をかけて作ったはずの人事制度が、いつの間にか誰も見向きもしない「絵に描いた餅」になっていませんか?
社員のモチベーションを上げるはずが、聞こえてくるのは給与への不満ばかり。
採用を強化するはずが、面接で魅力的に語れる制度になっていない。
公平性を目指したはずが、かえって優秀な社員から「正当に評価されていない」という声が上がる…。
もし、一つでも思い当たる節があれば、それは決してあなたや社員の能力が低いからではありません。
実は、世の中の人事制度の9割は、その導入目的が「会社の利益」に直結しておらず、構造的に失敗すべくして失敗しているのです。
本記事では、なぜ多くの人事制度が機能不全に陥るのか、その根本原因を徹底的に解き明かします。
「公平な評価という幻想」や「コンサルタントの光と闇」といった、多くの人が口をつぐんできた不都合な真実にまで踏み込み、あなたの会社が本当に目指すべきゴールを再定義します。
巷のノウハウに惑わされるのは、もう終わりにしましょう。
この記事を読み終える頃には、社長自身の言葉で、自社の未来を創るための「会社の法律」を描くための一歩を踏み出せるはずです。

【村井 庸介(むらい ようすけ)】
大学卒業後は株式会社野村総合研究所に入社し通信業・製造業の経営コンサルティングに携わる。その後リクルート、グリー、日本IBMに転職。その中でグリー株式会社にて人事制度設計に携わった。
2015年に独立後は、社員30名のベンチャー企業から5,000名を超える大企業まで幅広く人事制度設計や導入伴走に携わる。顧客業種は製造業、サービス、IT企業が中心。経営理念・事業戦略から逆算した人事制度構築を得意とする。
なぜ、人事制度は「絵に描いた餅」で終わるのか?

多くの経営者が、会社の成長段階において人事制度の必要性を感じ、その導入や改定に踏み切ります。
しかし、その善意の投資が、なぜか期待した成果に結びつかないどころか、かえって組織の停滞や混乱を招いてしまうケースが後を絶ちません。
その理由は、制度設計のテクニック以前の、もっと根深い部分に横たわっています。
ここでは、多くの企業が陥りがちな「失敗の構造」を解き明かしていきます。
「採用強化」「公平性」…その目的、本当に会社の利益に繋がっていますか?
人事制度を導入する際、多くの社長が「採用力を強化したい」「社員を公平に評価したい」といった目的を掲げます。
これらは一見すると、非常に正しく、聞こえの良い目標です。
しかし、これらの目的が、あなたの会社の「利益」という最終ゴールと、どのように結びついているのかを言語化できているでしょうか。
例えば、「採用強化」のために立派な人事制度を作ったとします。
等級制度や評価基準が明文化され、求人票にも「明確なキャリアパスあり」と記載できるようになったかもしれません。
ですが、その制度が求める人材像と、会社の事業戦略が求める人材像が一致していなければ、全く意味がありません。
むしろ、制度という「体裁」に惹かれて入社したものの、実際の企業文化や事業の方向性と合わずに、すぐに辞めてしまうというミスマッチを誘発する危険性すらあります。
採用は、あくまで事業を成長させるための手段であって、目的ではありません。
会社の利益を生み出すのは、商品であり、営業であり、マーケティング活動です。
人事制度は、これらの活動を最大化する「人」の力を引き出すための装置であるべきなのです。
「公平性」についても同様のことが言えます。
社員一人ひとりを公平に扱いたいという社長の想いは、非常に尊いものです。
しかし、その「公平」とは、一体何を基準とした「公平」なのでしょうか。
全ての社員に同じ基準を当てはめることが、果たして本当に公平と言えるのでしょうか。
利益に大きく貢献したハイパフォーマーと、最低限の役割しか果たしていない社員を、「公平」という名のものとに同じような評価軸で測り、処遇に大差をつけないのであれば、それは優秀な社員に対する「不公平」に他なりません。
結果として、頑張る人が報われない文化が醸成され、優秀な人材から静かに会社を去っていくという最悪の結末を迎えかねないのです。
人事制度の導入目的が、「会社の利益にどう貢献するのか」という視点と固く結びついていない限り、それは単なる自己満足か、社員迎合のためのコストで終わってしまいます。
会社を蝕む「公平な評価」という幻想と、「納得感のある不公平」の作り方
私たちは、「公平」という言葉に、一種の魔法のような響きを感じてしまいます。
しかし、組織運営において、絶対的な「公平」などというものは存在しません。
それは、組織が「ヒト」という感情を持つ存在で構成されている以上、避けられない事実です。
社長がどれだけ公平な評価をしようと努力しても、評価される側は「もっと評価されてしかるべきだ」と感じるものです。
評価者と被評価者の間には、情報の非対称性や、立場の違いによる認識のズレが必ず存在します。
このズレを完全に埋めることは不可能です。
この現実から目を背け、「完全な公平」を目指して評価項目を細分化し、評価プロセスを複雑化させていくと、組織は深刻な病に蝕まれ始めます。
評価のための評価に多大な時間が費やされ、管理職は部下の評価シートを埋める作業に疲弊し、本来のマネジメント業務が疎かになります。
社員は、評価項目の点数を稼ぐための「評価ゲーム」に興じるようになり、本来の顧客価値の創造や、本質的な業務から意識が離れていってしまいます。
これが、「公平な評価」という幻想がもたらす悲劇です。
では、どうすれば良いのでしょうか。
目指すべきは、「完全な公平」ではなく、「納得感のある不公平」です。
「納得感のある不公平」とは、評価の結果に差がつくこと、つまり「不公平」が生じることを前提としながらも、その評価基準やプロセスが明確であり、社員が「その基準で評価されるなら仕方ない」「あの人が高く評価されるのは当然だ」と受け入れられる状態を指します。
例えば、「今期、最も会社の利益に貢献した事業部のメンバーを手厚く処遇する」という方針が明確に示されていれば、他の事業部の社員は悔しいと感じるかもしれませんが、その決定に「納得」はできるでしょう。
あるいは、「会社の理念を最も体現し、周囲に良い影響を与えた社員をMVPとして表彰し、特別な報酬を与える」という基準があれば、たとえ自分が選ばれなくても、その選考プロセスに「納得」はできるはずです。
重要なのは、評価項目を細かくすることではなく、会社として「何を大切にし、何を評価するのか」という、たった一つの、しかし極めて強力なメッセージを、社長自身の言葉で明確に示すことなのです。
そのメッセージこそが、「納得感」の源泉となります。
そのコンサル契約、成果を約束できますか?人事評価制度コンサルの光と闇

自社だけで人事制度を構築するのが難しいと感じたとき、多くの経営者が「人事評価制度 コンサル」の活用を検討します。
専門家の知見を借りることは、決して間違った選択ではありません。
しかし、コンサルタントという存在を正しく理解し、その価値と限界を見極めなければ、高額な費用を支払ったにもかかわらず、全く成果が出ないという事態に陥りかねません。
ここでは、コンサルティング業界の「光」と「闇」に切り込みます。
コンサルができることと、できないこと
優秀な人事評価制度コンサルタントは、あなたの会社に多くの価値をもたらしてくれます。
彼らは、世の中にある様々な人事制度の「型」に関する知識が豊富です。
MBO(目標管理制度)、コンピテンシー評価、360度評価、あるいは最近注目されているノーレイティングなど、各制度のメリット・デメリットを熟知しています。
あなたの会社の業種や規模、目指す方向性に応じて、最適な制度の「型」を提案してくれるでしょう。
また、他社の導入事例に関する情報も豊富です。
同業他社や、似たような成長ステージにある企業が、どのような制度を導入し、どのような課題に直面したのか、具体的なケースを基にアドバイスをくれます。
これは、自社だけで試行錯誤する時間を大幅に短縮してくれる、大きなメリットです。
さらに、制度設計のプロセス管理も得意とします。
いつまでに何を決定し、どのようなステップで社員に説明し、いつから導入するのか、といったプロジェクト全体のスケジュールを設計し、ファシリテーターとして議論を円滑に進めてくれます。
ここまでが、コンサルタントが提供できる「光」の部分、つまり彼らができることです。
では、彼らに「できないこと」とは何でしょうか。
それは、あなたの会社の人事制度に「魂」を吹き込むことです。
コンサルタントは、最適な「器」を用意することはできますが、その器に何を注ぎ込むのか、つまり「会社として何を大切にし、どんな人材に報いるのか」という思想そのものを、あなたの代わりに決めることはできません。
この「魂」の部分こそが、先ほど述べた「納得感」の源泉であり、制度が機能するか否かを分ける決定的な要素なのです。
もし、コンサルタントが「我が社のメソッドを使えば、どんな会社でもうまくいきます」と語ったり、社長であるあなた自身の理念や価値観を深く問うことなく、いきなり制度の設計図を描き始めたりするならば、要注意です。
そのコンサルタントは、あなたの会社に最適化された唯一無二の制度を作ろうとしているのではなく、自社の商品である「既製品の制度」を売ろうとしているだけの「作業屋」である可能性が高いでしょう。
コンサル費用を「投資」に変える条件
人事評価制度コンサルの費用は、決して安いものではありません。
企業の規模や依頼する業務範囲によって大きく変動しますが、プロジェクト型のコンサルティングであれば、数百万円から、大企業になれば数千万円規模になることも珍しくありません。
また、継続的な支援を依頼する顧問契約型であれば、月額数十万円が一般的な相場観です。
これだけの金額を支払う以上、その費用は単なる「コスト」ではなく、将来の利益を生み出す「投資」でなければなりません。
では、コンサル費用を「投資」に変えるための条件とは何でしょうか。
第一の条件は、社長自身がプロジェクトの「最高責任者」として、主体的に関与し続けることです。
コンサルタントに「丸投げ」した瞬間に、そのプロジェクトの失敗は約束されたようなものです。
先述の通り、制度の「魂」を決められるのは社長だけです。
コンサルタントは、社長の頭の中にある曖昧な想いやビジョンを言語化し、整理し、仕組みに落とし込むための「壁打ち相手」であり「翻訳家」です。
壁打ちをする相手がいなければ、コンサルタントは一般的な正論を並べるしかありません。
社長が自身の時間とエネルギーを投下し、本気でこのプロジェクトに取り組む覚悟を示すこと。
これが、コンサル費用を投資に変えるための最も重要な条件です。
第二の条件は、制度の導入効果を測定するための「指標」を、事前に設定しておくことです。
例えば、「離職率の低下」「従業員満足度の向上」「特定部門の生産性向上」など、何を達成するために制度を導入するのか、具体的なKPIを設定します。
そして、そのKPIをコンサルタントと共有し、成果に対するコミットメントを求めるのです。
もちろん、人事制度の効果は、すぐに数字に表れるものばかりではありません。
しかし、目指すべきゴールを定量的に設定し、その進捗を追いかけることで、プロジェクトの方向性がブレることを防ぎ、コンサルタントにも良い意味でのプレッシャーを与えることができます。
目的が曖昧なまま支払うお金は「コスト」ですが、明確なリターンを期待して支払うお金は「投資」になるのです。
人事コンサル導入の成功とよくある失敗トップ3
ここでは、人事コンサルティングの導入における成功パターンと、多くの企業が陥りがちな失敗パターンを具体的に見ていきましょう。
成功する企業に共通しているのは、コンサルタントを「魔法使い」ではなく「パートナー」として活用している点です。
彼らは、コンサルタントの専門知識を尊重しつつも、最終的な意思決定は必ず自社で行います。
社長が明確なビジョンを示し、プロジェクトチームが現場の声を吸い上げ、コンサルタントが外部の視点と専門知識でそれを補強する。
この三位一体の協力体制が、成功の鍵となります。
対して、失敗する企業には、いくつかの共通したパターンが見られます。
最も多い失敗の第一位は、「社長の丸投げ」です。
多忙を理由に、社長がプロジェクトのキックオフにだけ顔を出し、あとは担当役員や人事部長に任せきりにしてしまうケースです。
これでは、制度の根幹となるべき社長の「想い」が反映されず、各部門の利害調整に終始した、当たり障りのない制度しか生まれません。
結果として、誰からも支持されない「魂の抜けた制度」が完成してしまいます。
失敗の第二位は、「他社の成功事例の猿真似」です。
コンサルタントが提示する「あの先進企業も導入している」といった成功事例に安易に飛びつき、自社の企業文化や事業特性を無視して、そのまま導入しようとするケースです。
例えば、成果主義が根付いていないウェットな文化の企業に、ドライな実力主義の制度を導入すれば、社員の猛反発を招き、組織の連帯感が崩壊するのは目に見えています。
他社の事例はあくまで参考であり、自社の風土に合わせて翻訳・編集するプロセスが不可欠です。
そして、失敗の第三位は、「評価者トレーニングの軽視」です。
立派な制度の「器」を作っただけで満足し、その制度を運用する管理職(評価者)への教育を疎かにしてしまうケースです。
評価基準がどれだけ明確でも、評価者によって解釈にバラつきがあったり、部下へのフィードバック面談のスキルが不足していたりすれば、制度は全く機能しません。
むしろ、不適切な運用によって、社員の不信感を増大させる結果となります。
制度設計にかけるエネルギーと同等か、それ以上のエネルギーを、評価者の育成に注ぐ覚悟が必要です。
人事制度とは”会社の法律”である
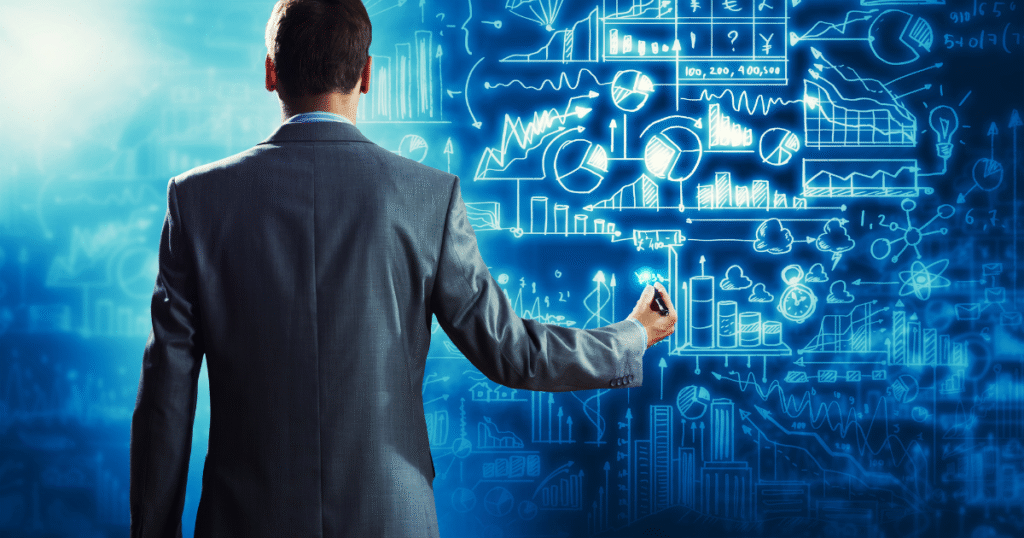
ここまで、人事制度が失敗する理由や、コンサルタントとの付き合い方について述べてきました。
では、そもそも人事制度とは、会社にとってどのような意味を持つのでしょうか。
私は、人事制度とは「社長が創る、会社という王国の法律である」と定義しています。
法律とは、その国の国民が守るべきルールであり、その国が何を大切にし、どのような行動を奨励し、どのような行動を罰するのかという、国家の価値観そのものです。
人事制度も全く同じなのです。
等級制度:誰に「会社の未来」を任せるか
等級制度とは、社員の役割や責任の大きさを段階的に定義したものです。
一般的には、「一般社員」「リーダー」「マネージャー」「部長」といった階層で表現されます。
これは単なる序列を示すものではありません。
等級制度は、「この会社において、どの役割を担う人材に、会社の未来を託していくのか」という、社長からの極めて重要なメッセージなのです。
例えば、年功序列的な等級制度を採用すれば、「長く会社に貢献してくれた人を大切にする」というメッセージになります。
一方、年齢や社歴に関わらず、高い専門性を持つ人材を上位等級に格付けする制度であれば、「この会社は、専門性を何よりも重視する」というメッセージになります。
あるいは、管理職としてのマネジメントラインとは別に、専門性を極める「専門職ライン」を設ければ、「マネージャーになることだけがキャリアではない。スペシャリストとして会社に貢献する道もある」という多様なキャリア観を示すメッセージとなります。
あなたの会社は、どのような役割を担う人材に、より大きな責任と権限を与え、会社の未来を牽引していってほしいのでしょうか。
その答えを形にしたものが、等級制度なのです。
報酬制度:誰の、どんな「挑戦」と「成果」に報いるのか
報酬制度、つまり給与や賞与のルールは、人事制度の中でも最も直接的で、強力なメッセージを発します。
なぜなら、それは会社が「誰の、どのような働きに対して、有限である原資を分配するのか」という、シビアな意思決定そのものだからです。
人が何に時間と情熱を注ぐかは、何によって報われるかによって大きく左右されます。
もし、個人の成果よりも、チーム全体の成果を重視するのであれば、個人単位のインセンティブよりも、チーム単位の賞与の比率を高くすべきでしょう。
そうすれば、「個人の成功よりも、チームの成功を優先する」というメッセージが伝わります。
もし、短期的な売上目標の達成よりも、長期的な顧客満足度の向上を重視するのであれば、賞与の算定基準に、売上だけでなく顧客アンケートの結果を反映させるべきです。
そうすれば、「目先の数字を追うだけでなく、顧客と長期的な関係を築くことが評価される」というメッセージが明確になります。
あるいは、失敗を恐れずに新しいことに挑戦する文化を創りたいのであれば、たとえ失敗に終わったとしても、その挑戦のプロセス自体を評価し、報酬に反映させる仕組みが必要です。
そうしなければ、「挑戦せよ」という掛け声は空虚に響くだけで、誰もリスクを取ろうとはしなくなります。
あなたの会社は、社員のどのような「挑戦」と「成果」に、最も厚く報いたいのでしょうか。
その優先順位を明確にすることが、報酬制度の設計の第一歩です。
評価制度:スター社員を生み出す仕組み
評価制度は、設定された等級や報酬のルールに基づき、個々の社員のパフォーマンスを判定するプロセスです。
これは、単に優劣をつけるための仕組みではありません。
評価制度とは、「この会社が、どのような人材を『スター社員』として認め、全社員が目指すべきロールモデルとして提示するのか」を決めるための、極めて戦略的な仕組みなのです。
会社が掲げる理念やビジョンは、それだけでは抽象的で、日々の業務に落とし込みにくいものです。
しかし、「あの人のような働き方が、この会社では高く評価される」という具体的なロールモデルが可視化されることで、社員は初めて、理念やビジョンを自分ごととして捉え、具体的な行動に移すことができます。
評価制度を通じて高く評価され、昇進し、賞賛される社員の姿は、他の全社員にとっての「北極星」となります。
例えば、個人としてのスキルは高いものの、チームワークを乱す利己的な社員よりも、自らの知識や経験を惜しみなく周囲に共有し、チーム全体の成果を高める社員を高く評価すれば、「この会社では、協調性と他者貢献が成功の鍵である」という文化が育ちます。
逆に、結果さえ出せばプロセスは問わないという評価を続ければ、ハラスメントや不正の温床となり、組織は内側から崩壊していくでしょう。
評価制度とは、社長が望む「スター社員」を意図的に生み出し、その存在を通じて、会社全体の文化をデザインしていくための、最もクリエイティブなツールなのです。
「50名の壁」の恐怖と克服法
創業期、社員が数名から十数名の頃は、人事制度などなくても、会社はうまく回ります。
なぜなら、社長が全社員の顔と名前、働きぶり、さらにはその家族構成まで把握できているからです。
社長の目が物理的に届く範囲では、社長自身が「生きた人事制度」として機能します。
誰が頑張っているか、誰がチームに貢献しているかは、社長の肌感覚で分かります。
しかし、組織が成長し、社員数が30名を超え、50名に近づくにつれて、状況は一変します。
いわゆる「50名の壁」です。
社長は、もはや全社員の働きぶりを直接見ることができなくなります。
社長の目が届かない部署では、社長が大切にしてきたはずの理念や文化が、部署独自のルールに上書きされ、歪んで伝わり始めます。
社長が直接採用に関われない新入社員たちは、創業以来の「暗黙の了解」を知る由もありません。
結果として、本来会社に居続けてほしかったはずの、理念に共感する優秀な人材が「この会社は、自分の見ている方向と違う」と感じて辞めていく。
部署ごとに文化がサイロ化し、会社全体の一体感が失われる。
社風に合わない人材が採用され、早期離職が相次ぎ、採用コストが無駄になる。
このような事態が、静かに、しかし確実に進行していくのです。
これが「50名の壁」の恐怖です。
人事制度は、この「50名の壁」を乗り越え、社長の目が届かない場所にまで、社長の想い、つまり「会社の法律」を浸透させるためにこそ、必要になるのです。
それは、社員を管理するための息苦しいルールではありません。
会社の規模が大きくなっても、創業時の情熱や価値観を失うことなく、全社員が同じ方向を向いて進むための「共通言語」であり「羅針盤」なのです。
社長が「北極星」を定める4ステップ

人事制度が「会社の法律」である以上、その立法者、つまり最高責任者は社長以外にあり得ません。
コンサルタントや人事部長ではありません。
では、社長は具体的に何をすれば良いのでしょうか。
それは、制度の細かな設計図を描く前に、会社の進むべき方向を示す「北極星」を、自らの手で定めることです。
ここでは、そのための具体的な4つのステップを紹介します。
STEP1:【理念の言語化】
最初のステップにして、最も重要なステップが、社長自身の経営理念や価値観を、明確な「言葉」にすることです。
「何のためにこの会社を経営しているのか」「どんな仲間と、どんな未来を創りたいのか」「仕事を通じて、お客様や社会に何を提供したいのか」。
多くの社長は、これらの問いに対する答えを、何となくイメージとしては持っています。
しかし、それを誰にでも伝わる具体的な言葉にできている社長は、驚くほど少ないのが現実です。
あるいは、創業時に掲げた理念が、会社の成長と共に、社長自身の中で少しずつ形骸化してしまっている場合もあります。
このステップでは、誰にも邪魔されない時間を確保し、徹底的に自己と向き合ってください。
創業時の日記や事業計画書を読み返してみるのも良いでしょう。
あなたが最も尊敬する経営者や、歴史上の人物について考えてみるのもヒントになります。
「どんな時に、仕事で心の底から喜びを感じるか」「どんな社員の姿を見ると、嬉しくなるか」「逆に、どんな行動を見ると、許せないと感じるか」。
こうした問いを通じて、あなた自身の「本音」の価値観を掘り起こし、それを飾らない言葉で書き出していくのです。
このプロセスは、孤独で、時には苦しい作業かもしれません。
しかし、この「理念の言語化」なくして、魂のこもった人事制度は絶対に作れません。
STEP2:【ゴールの共有】
社長自身の「北極星」が明確になったら、次のステップは、その光を最も近くで共有すべき相手、つまり役員や経営幹部と「共通のゴール」を設定することです。
どんなに社長が素晴らしい理念を掲げても、経営チームがバラバラの方向を見ていては、会社という船は前に進みません。
「この会社で大事にしていることは?」という問いに対して、役員から異なる答えが返ってくるようでは、その先にある制度作りは、各論反対の不毛な議論に終始するだけです。
このステップでは、合宿など、日常業務から切り離された環境で、経営チームが徹底的に対話する場を設けることを強く推奨します。
まず、STEP1で言語化した社長の想いを、ありのままの言葉で伝えます。
そして、その想いを実現するために、会社として3年後、5年後にどのような状態(売上、利益、市場シェア、組織文化など)になっていたいのか、具体的なゴールのイメージを共有し、議論を尽くすのです。
ここでの目的は、全員が完全に同じ意見になることではありません。
それぞれの視点や考え方の違いをテーブルの上に出し、それでもなお「このゴールに向かって進む」という一点において、固い握手を交わすことです。
この「共通のゴール」に対する合意形成こそが、今後の制度設計における全ての意思決定の拠り所となります。
STEP3:【人材像の定義】
会社の「北極星」と「共通のゴール」が定まったら、次はそのゴールに到達するために、どのような人材が必要なのか、その具体的な「人材像」を定義します。
組織は、機械ではなく、「ヒト」が動かしています。
どんなに優れた戦略を描いても、それを実行する「人」がいなければ、画に描いた餅で終わってしまいます。
このステップでは、経営チームで以下のような問いについて議論します。
「我々が設定したゴールを達成するために、社員には、どのようなスキルや知識を身につけていってほしいか?」
「どのような価値観を持ち、どのように行動する人材に、チームの中核を担ってほしいか?」
「逆に、我々の目指す組織文化とは相容れない、どのような行動や価値観を持つ人材は、この船には乗っていてほしくないか?」
最後の問いは、少し勇気が必要かもしれません。
しかし、求める人材像を明確にすることは、同時に、求めない人材像を明確にすることでもあります。
この「求める人材像」を、具体的な行動レベルの言葉で定義したものが、いわゆる「コンピテンシー」や「バリュー(行動指針)」と呼ばれるものになります。
例えば、「挑戦を称える」という価値観を掲げるなら、「失敗を恐れず、前例のないテーマに自ら手を挙げる」といった具体的な行動にまで落とし込むのです。
この人材像の定義が、後の評価制度において、社員の行動を測る「物差し」となります。
STEP4:【魂の注入】
ここまでの3ステップで、人事制度の「魂」となる部分は、ほぼ完成しました。
最後のステップは、その魂を、具体的な制度の「器」、つまり等級、報酬、評価といった「型」に落とし込んでいく作業です。
ここで重要なのは、「他社にない、魔法のような独自の仕組み」を探し求める必要は全くない、ということです。
世の中の人事制度の「型」は、ある程度出尽くしています。
MBO、コンピテンシー評価、役割等級制度など、基本的なフレームワークは、書籍やインターネットでいくらでも学ぶことができます。
大切なのは、どの「型」が優れているか、ということではありません。
STEP1〜3で明確にした自社の「理念」「ゴール」「人材像」という魂を、選んだ「型」の中に、どのように注入するか、です。
例えば、等級制度という「型」に、「我が社は、マネジメントだけでなく専門性も評価する」という魂を注入すれば、複線型のキャリアパスを持つ等級制度が生まれます。
報酬制度という「型」に、「チームでの成果を何よりも重視する」という魂を注入すれば、チームインセンティブの比重が高い報酬制度が生まれます。
評価制度という「型」に、「挑戦する姿勢そのものを称賛する」という魂を注入すれば、成果だけでなくプロセスも評価項目に含まれる評価制度が生まれるのです。
制度の独自性は、「仕組み」の奇抜さから生まれるのではありません。
自社の「思想」を反映させた「運用」の方針こそが、結果として、他社には真似のできない、唯一無二の人事制度を生み出すのです。
理念を共に創るパートナーの見つけ方|失敗しないコンサル選定術

ここまで読んで、社長自身がやるべきことの重要性は理解したけれど、やはり独力で進めるのは不安だ、と感じる方もいるでしょう。
その不安を解消し、プロセスを円滑に進めるために、外部のコンサルタントを「パートナー」として活用することは、非常に有効な選択肢です。
しかし、そのパートナー選びを間違えれば、全てが台無しになります。
ここでは、あなたの会社の理念創造を共に歩んでくれる、真のパートナーを見極めるための具体的な方法をお伝えします。
見極めポイント
良いコンサルタントと、そうでないコンサルタントを見極めるポイントは、非常にシンプルです。
それは、彼らが「作業屋」か「思想家」か。
そして、「評論家」か「伴走者」か、という二つの軸で見ることです。
「作業屋」タイプのコンサルタントは、あなたの会社の理念や価値観にはあまり興味を示しません。
彼らは、自社が持つテンプレートやフレームワークを提示し、それにあなたの会社を当てはめようとします。
彼らの口癖は「一般的にはこうです」「他社ではこうしています」です。
彼らは、あなたの会社の制度設計を、一つの「作業」として捉えています。
一方、「思想家」タイプのコンサルタントは、何よりもまず、社長であるあなた自身の「想い」を知ろうとします。
「社長は何のためにこの事業を始めたのですか」「どんな会社にしたいのですか」と、繰り返し問いかけてきます。
彼らは、制度設計を、社長の思想を形にする「創造的なプロセス」だと捉えています。
また、「評論家」タイプのコンサルタントは、外部の専門家という立場から、あなたの会社の現状を分析し、あるべき論を語るのは得意です。
しかし、いざ具体的な実行段階になると、「それは会社側の仕事です」と一線を引きます。
彼らは、あくまで第三者としての助言に終始します。
対して、「伴走者」タイプのコンサルタントは、あなたの会社のプロジェクトチームの一員であるかのように、深く関与してくれます。
役員会で厳しい意見を言うことも厭わず、社員向けの説明会で矢面に立ってくれることもあります。
彼らは、制度が完成し、組織に根付くまで、共に汗をかくことを約束してくれます。
あなたが探すべきは、あなたの想いを引き出してくれる「思想家」であり、その実現まで共に走ってくれる「伴走者」なのです。
契約前に必ず聞くべき「7つの必殺質問リスト」
良いパートナーを見極めるために、コンサルタントとの面談で、ぜひ以下の7つの質問を投げかけてみてください。
相手の「本質」が透けて見えるはずです。
- 「人事制度において、最も重要だと思うことは何ですか?」 (→「仕組みの精緻さ」と答えるか、「理念の反映」と答えるか)
- 「このプロジェクトで、私(社長)に最も期待する役割は何ですか?」 (→「迅速なご決断」とだけ答えるか、「社長の想いを語っていただくこと」と答えるか)
- 「過去に支援した企業で、最も上手くいかなかった事例とその理由を教えてください」 (→失敗を語れる誠実さと、そこからの学びがあるか)
- 「もし、私たちの経営陣の意見が割れた場合、どのように進めますか?」 (→安易に多数決に流れるか、対話を促し、本質的な合意形成を目指すか)
- 「制度導入後、社員から反発が出た場合、どのようなサポートを期待できますか?」 (→「それは運用マニュアルで」と答えるか、「説明会や個別面談にも同席します」と答えるか)
- 「御社のコンサルティングの『売り』を一言で言うと何ですか?」 (→独自のメソッドやツールを語るか、「クライアントへの深い理解」を語るか)
- 「あなた自身は、なぜこの仕事をしているのですか?」 (→最後の質問で、コンサルタント個人の「理念」や「情熱」が見える)
これらの質問に対する答えに、正解はありません。
しかし、その答え方や表情から、相手がどのような哲学を持って仕事に取り組んでいるのか、そして、あなたが「この人と一緒に未来を創りたい」と心から思える相手なのかどうか、きっと感じ取れるはずです。
人事制度は社長にしかできない最もクリエイティブな仕事

ここまで、人事制度の本質から、具体的な作り方、パートナーの選び方まで、長い道のりを共に歩んできました。
もしかしたら、その責任の重さに、少し圧倒されているかもしれません。
しかし、どうか忘れないでください。
人事制度作りとは、無味乾燥な管理業務などでは断じてなく、社長にしかできない、最もエキサイティングで、クリエイティブな仕事なのです。
それは、会社の未来そのものをデザインする行為に他なりません。
5年後誰とどんな景色を見たいですか?
最後に、もう一度、あなた自身に問いかけてみてください。
5年後、あなたの会社は、どのような会社になっていたいですか。
そして、その時、社長であるあなたの隣で、一緒に笑っているのは、どんな仲間たちでしょうか。
彼らは、どんな働き方をし、どんなことに喜びを感じているでしょうか。
彼らが「この会社で働けて、本当に良かった」と心から思える。
そんな未来の景色を想像してみてください。
人事制度とは、その理想の景色から逆算して、今打つべき一手を定めるための、未来への設計図です。
誰に船の舵取りを任せ、誰に帆を張ってもらい、誰に新たな航路を探してもらうのか。
そして、その素晴らしい働きをした仲間たちに、どのように報い、感謝を伝えるのか。
その一つひとつの意思決定が、あなたの会社という船の進む方向を決め、共に航海する仲間たちの人生を豊かにしていくのです。
このクリエイティブな旅に、既成概念や他人の物差しは必要ありません。
必要なのは、社長であるあなた自身の「想い」と、未来を信じる「覚悟」だけです。
この記事が、あなたの新たな船出の、確かな羅針盤となることを、心から願っています。
人事評価制度にお困りの方は、お気軽に村井にご相談ください。
➖ 資料請求 ➖
資料請求は下記バナーより。

➖ 問い合わせ ➖
新規事業、DX、人事制度などの経営課題に関するご相談は以下よりお受けしております。