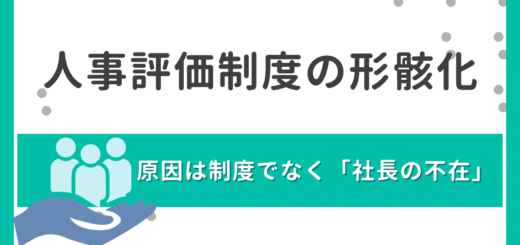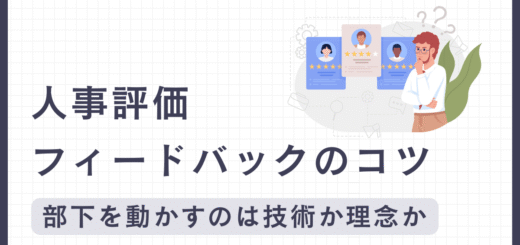人事評価制度の導入方法を徹底解説!手順書を捨てて理念を語れ?
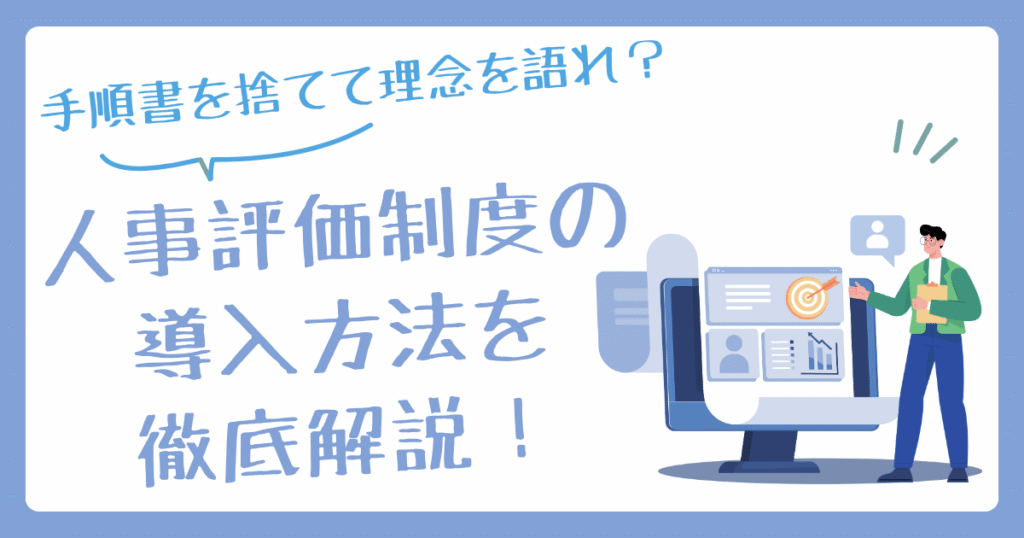
人事評価制度の導入方法の「正しい手順書」を求めて、あなたはこのページにたどり着いたのかもしれません。
世の中には、「5つのステップ」や「7つの手順」といった、分かりやすい導入マニュアルが溢れています。
しかし、手順書通りに、忠実に制度を導入した企業の、実に9割が、失敗という苦い現実に直面しているのです。
なぜ、完璧なはずの手順書が、あなたの会社を成功に導いてくれないのでしょうか。
この記事では、巷で語られる一般的な導入ステップを網羅的に解説した上で、なぜそれだけでは不十分なのか、その根本原因を解き明かします。
そして、あなたの会社が失敗の9割から抜け出し、成功する1割の仲間入りを果たすための、ただ一つの、しかし最も重要な「本質的な導入方法」を解説していきます。

【村井 庸介(むらい ようすけ)】
大学卒業後は株式会社野村総合研究所に入社し通信業・製造業の経営コンサルティングに携わる。その後リクルート、グリー、日本IBMに転職。その中でグリー株式会社にて人事制度設計に携わった。
2015年に独立後は、社員30名のベンチャー企業から5,000名を超える大企業まで幅広く人事制度設計や導入伴走に携わる。顧客業種は製造業、サービス、IT企業が中心。経営理念・事業戦略から逆算した人事制度構築を得意とする。
人事評価制度の導入方法 なぜ手順書通りでは失敗するのか

多くの企業が、多大な時間とコストをかけて人事評価制度を導入します。
しかし、その努力が報われることは、稀です。
その背景には、ほとんどの企業が陥ってしまう、深刻な「罠」が存在します。
多くの企業が陥る「導入が目的化」する罠
人事評価制度の導入プロジェクトは、それ自体が大きな仕事です。
現状分析、評価項目の策定、評価者研修、社員への説明会…。
やるべきことは、山のようにあります。
そして、多くの企業が、これらのタスクをこなすことに夢中になるあまり、いつの間にか、「制度を無事に導入すること」そのものが、最終目的になってしまうのです。
これが、「導入が目的化」する、最も恐ろしい罠です。
本来の目的であるはずの、「社員の成長」や「会社の発展」は、どこかへ置き去りにされてしまいます。
手順書に書かれていない最も重要なこと
なぜ、このような「目的化の罠」に陥ってしまうのでしょうか。
それは、あなたが参考にしている、どんなに優れた「手順書」にも、絶対に書かれていない、たった一つの、しかし最も重要な要素が、抜け落ちているからです。
手順書は、「WHAT(何をすべきか)」と「HOW(どうやるか)」は、教えてくれます。
しかし、その制度を、なぜ、あなたの会社が導入するのかという「WHY」については、何も語ってくれません。
この「WHY」、つまり、あなたの会社の「理念」や「存在意義」こそが、手順書に書かれていない、最も重要なことなのです。
理念なき導入は必ず失敗する
理念なきまま、ただ手順書通りに導入された人事評価制度は、魂のない、ただの抜け殻に過ぎません。
社員は、その制度の目的を理解できず、「また、会社が面倒なことを始めた」と、冷めた目で見るだけでしょう。
管理職は、その制度に込められた想いを知らないため、ただの事務作業として、評価をこなすだけになります。
理念という「魂」がなければ、どんなに精緻な制度も、人の心を動かすことはできません。
そして、人の心が動かなければ、組織が活性化することも、会社が成長することもないのです。
理念なき導入は、その始まった瞬間から、すでに失敗という運命を、背負っているのです。
一般的な人事評価制度の導入方法6ステップ
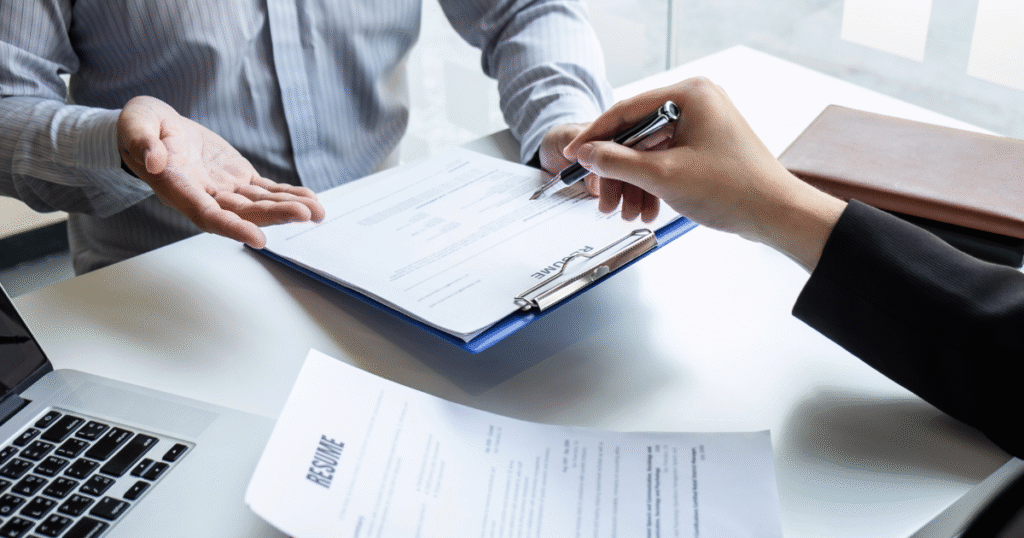
本質的な話に入る前に、まずは、世の中で「正しい」とされている、一般的な人事評価制度の導入方法について、その6つのステップを、網羅的に確認しておきましょう。
これらは、導入を進める上での、基本的な地図となります。
しかし、忘れないでください。
この地図だけでは、目的地にはたどり着けないということを。
現状分析と目的の明確化
最初のステップは、自社の「現状分析」と、制度導入の「目的の明確化」です。
社員アンケートやヒアリングを通じて、「現在の評価制度に、どんな不満があるか」「どんな制度であれば、もっと活躍できるか」といった、現場の課題を洗い出します。
そして、その課題解決を通じて、「人材育成の促進」や「業績向上への貢献」といった、今回の制度導入が目指す、具体的なゴールを定めます。
評価項目・基準・方法の策定
次に、定めた目的に基づき、「何をすれば評価されるのか」という、具体的な評価項目、基準、そして方法を策定します。
会社の理念や行動指針(バリュー)と連動させながら、成果、能力、情意(行動)の何を、どのくらいの重み付けで評価するのかを決定します。
また、MBO(目標管理制度)や360度評価といった、様々な評価手法の中から、自社の目的に合ったものを選択します。
評価制度と処遇との連携
評価制度は、単体では機能しません。
評価の結果を、社員の昇給や賞与、昇格といった「処遇」に、どのように反映させるのか、そのルールを明確に規定します。
また、社員の序列や立場を決める「等級制度」や、給与の全体構造を決める「報酬制度」といった、他の人事制度との、一貫性と整合性を確保することも、極めて重要です。
評価者の教育とシミュレーション
制度の骨格が固まったら、それを運用する「評価者」、つまり管理職への「教育」を行います。
制度の目的や、評価基準の解釈、面談の進め方について、評価者全員の目線を合わせるための研修は、不可欠です。
また、実際に制度を導入する前に、「シミュレーション」を実施することも、失敗を避けるためには有効です。
新しい制度で評価した場合、人件費はどのように変動するのか、といった影響を事前に検証し、問題点を洗い出します。
従業員への周知と運用開始
最終的な制度案が固まったら、全社員に対して、丁寧な「周知」を行います。
なぜ、この制度を導入するのかという目的から、具体的なルールまで、説明会などを通じて、全社員の理解と納得を得ることが、円滑な導入の鍵となります。
この周知のプロセスを経て、いよいよ、制度の「運用開始」となります。
運用後の評価と改善
制度は、導入して終わり、ではありません。
導入後も、その制度が意図した通りに機能しているか、新たな課題は生まれていないかを、定期的に「評価」し、「改善」を加えていく必要があります。
この、PDCAサイクルを回し続けることこそが、制度を形骸化させず、「生きた仕組み」として機能させるための、王道のアプローチだと、考えられています。
「手順書を捨てる」の真意と理念を語る重要性

さて、ここまで見てきた「一般的な導入方法6ステップ」は、一見すると、非常に論理的で、正しい手順のように思えます。
しかし、なぜ、この手順書通りに進めても、9割の導入は失敗に終わるのでしょうか。
それは、これらの手順が、制度という「体」の作り方しか、教えてくれないからです。
人事制度は社長のメッセージそのものである
そもそも、人事評価制度とは、単なる評価のためのツールではありません。
それは、社長であるあなたが、社員に対して送る、最も強力で、最も直接的な「メッセージ」そのものです。
「我が社は、こういう価値観を大切にする」 「こういう働きをする人間を、高く評価する」 「こういうチームを、皆で創っていきたい」
その、社長の「想い」や「価値観」が、等級、評価、報酬という、制度のあらゆる側面に、色濃く反映されます。
社員は、社長の朝礼での言葉よりも、自分たちの処遇を決定する、この制度という名の「メッセージ」を、はるかに真剣に受け止めるのです。
理念こそが制度の「魂」となる
もし、先ほどの6つのステップが、制度という「体」の作り方だとすれば。
社長の「理念」は、その体に命を吹き込む、「魂」です。
どんなに美しい体を作っても、そこに魂が宿っていなければ、それは、ただの動かない人形に過ぎません。
同様に、どんなに精緻な制度を作っても、そこに社長の理念という魂が込められていなければ、それは、人の心を動かすことのない、ただの冷たいルールの束になってしまいます。
理念こそが、制度を生きた仕組みとして、脈動させる、唯一のエネルギー源なのです。
理念がなければどんな制度も形骸化する
そして、この「魂」が不在のまま、体だけが作られてしまった制度は、遅かれ早かれ、必ず「形骸化」します。
社員は、その制度の目的を理解できないため、「やらされ仕事」として、形式的に評価シートを埋めるだけになります。
管理職は、その制度に込められた想いを知らないため、ただの事務作業として、評価をこなすだけになります。
やがて、誰もその制度を本気にしなくなり、時間と労力だけがかかる、無意味な儀式へと、成り下がっていくのです。
理念なき導入が、失敗という終着点にたどり着くのは、必然なのです。
理念から始める本質的な人事評価制度の導入方法

では、どうすれば、魂のこもった、失敗しない人事評価制度を、導入することができるのでしょうか。
その方法は、手順書をなぞることではありません。
まず、社長である、あなた自身の心の中から、始めるのです。
社長が「誰をえこひいきするか」を言語化する
本質的な導入方法の、最初のステップ。
それは、社長であるあなた自身が、「この会社では、どのような価値観を持ち、どのような行動をする人間が、最も賞賛され、報われるべきなのか」という、会社の「えこひいき」の基準を、明確に言語化することです。
「失敗を恐れずに挑戦する人間を、えこひいきする」
この、社長の覚悟のこもった「えこひいき宣言」こそが、制度の魂となり、全ての評価の、ブレない軸となります。
これが、あなたの会社の「法律」の、最も重要な基本理念となるのです。
理念を評価基準という「法律の条文」に翻訳する
次に、その言語化された理念(えこひいきの基準)を、具体的な評価基準、つまり「法律の条文」へと、翻訳していきます。
例えば、「挑戦する人間をえこひいきする」という理念があるならば、評価シートの項目に「チャレンジ度」という項目を設け、その評価ウェイトを高く設定する。
等級制度の昇格要件に、「新規事業や業務改革を主導した経験」を盛り込む。
このように、社長の理念が、制度のあらゆる側面に、一貫して、そして具体的に反映されるように、既存のルールを書き換えていくのです。
このプロセスを通じて、社長の「想い」は、具体的な「仕組み」へと、姿を変えていきます。
社長自らが「理念の伝道師」となる
そして、最も重要なのが、この新しい法律の「精神」を、社長自らが、あらゆる場面で語り続けることです。
朝礼で語り、会議で語り、社内報で語り、そして評価面談の場で、熱く語るのです。
社長の言葉は、どんな精緻なマニュアルよりも、力強く、社員の心に浸透していきます。
社長が、誰よりも楽しそうに、自社の理念を語り、その理念を体現する社員を賞賛する。
その姿を見せることで、制度は、初めて、社員の行動を変え、会社を動かす、生きた力を持つのです。
社長は、制度の「設計者」であると同時に、理念を伝える「伝道師」でなければなりません。
まとめ:手順書に理念という魂を吹き込む
人事評価制度の導入方法。
その成否を分けるのは、手順書通りの、美しい「体」を作れるかどうか、ではありません。
その体に、社長であるあなたの「理念」という、熱い「魂」を、吹き込むことができるかどうか。
ただ、その一点にかかっています。
明日から始めるべき最初のステップ
本質的な導入を成功させるための、明日から始めるべき、最初のステップ。
それは、人事担当者と、打ち合わせをすることではありません。
まず、社長であるあなたが、たった一人で、静かに考える時間を確保することです。
そして、自問してください。
「私は、心の底から、どんな社員を『えこひいき』したいと願っているだろうか?」
その、あなたの正直な答えこそが、失敗しない制度導入の、全ての始まりです。
理念から創る制度導入の個別相談
もし、あなたが、自社の「理念」を言語化し、それを「生きた制度」へと昇GLISH、あなたの会社の「魂」を形にし、組織の隅々にまで浸透させる、本質的な制度導入を、ゼロから、共に行います。
あなたの会社だけの「魂のこもった制度」を、共に創り出せる日を、心から楽しみにしています。
人事評価制度にお困りの方は、お気軽に村井にご相談ください。
➖ 資料請求 ➖
資料請求は下記バナーより。

➖ 問い合わせ ➖
新規事業、DX、人事制度などの経営課題に関するご相談は以下よりお受けしております。