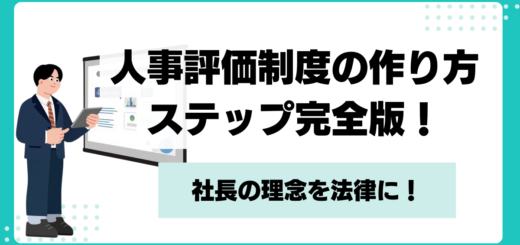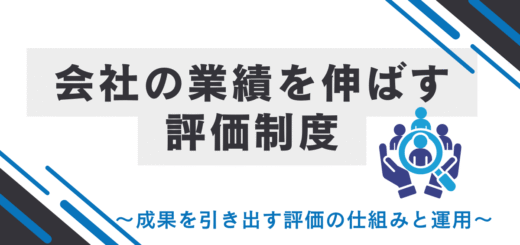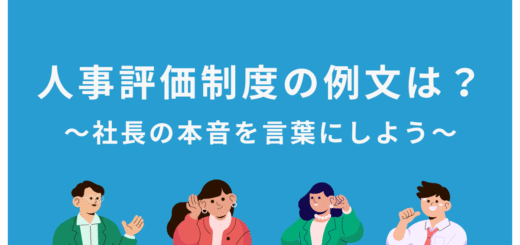人事評価制度の改善方法|なぜ9割の改善は失敗に終わるのか

人事評価制度の改善に、何度頭を悩ませ、時間を費やしてきたでしょうか。
評価項目をいじり、面談方法を変え、評価者研修を繰り返す。
しかし、社員の不満は消えず、制度は形骸化し、組織の空気は一向に良くならない。
「一体、何が間違っているのだろうか…」
もし、あなたがそう感じているのなら、この記事はまさに、あなたのために書かれました。
結論から申し上げます。
あなたの会社の改善がうまくいかないのは、改善方法が間違っているからではありません。
改善すべき「場所」が、根本的に間違っているのです。
この記事では、なぜ9割の改善が失敗という宿命をたどるのか、その本質的な理由を解き明かし、あなたの会社が成功する1割の仲間入りを果たすための、ただ一つの、しかし最も強力な「最終兵器」をお伝えします。
ぜひ、最後までお読みください。

【村井 庸介(むらい ようすけ)】
大学卒業後は株式会社野村総合研究所に入社し通信業・製造業の経営コンサルティングに携わる。その後リクルート、グリー、日本IBMに転職。その中でグリー株式会社にて人事制度設計に携わった。
2015年に独立後は、社員30名のベンチャー企業から5,000名を超える大企業まで幅広く人事制度設計や導入伴走に携わる。顧客業種は製造業、サービス、IT企業が中心。経営理念・事業戦略から逆算した人事制度構築を得意とする。
なぜ人事評価制度の改善は9割失敗するのか

人事評価制度の改善は、多くの企業にとって、終わりなき旅のように思われています。
しかし、その旅路は、希望に満ちたものではなく、むしろ組織の活力を静かに奪っていく、負のスパイラルに他なりません。
改善を繰り返すほど悪化する「改善疲労」の正体
「また、評価制度が変わるのか…」
社員がそう言ってため息をつき、「どうせ、またすぐ変わるんでしょ」と冷めた目で見ているとしたら、あなたの会社は、すでに「改善疲労」という深刻な病に罹っています。
良かれと思って繰り返される改善活動が、現場の社員にとっては、度重なるルールの変更に振り回される、ただのストレスでしかありません。
管理職は、新しい評価シートの書き方を覚えることに疲弊し、人事担当者は、社員への説明と不満の対応に追われ、本来の業務に集中できなくなります。
改善を繰り返せば繰り返すほど、社員は制度への信頼を失い、「どうせ何も変わらない」という無力感が組織全体に蔓延していく。
これが、「改善疲労」の恐ろしい正体です。
失敗の根本原因は制度ではなく「社長の理念」の不在
なぜ、これほどまでに多くの改善が失敗に終わるのでしょうか。
それは、ほとんどの企業が、制度の「表面」ばかりをいじり、その「土台」に手をつけていないからです。
評価項目、評価基準、面談の手順。
これらはすべて、制度の表面的なパーツに過ぎません。
本当に問題なのは、その制度が、そもそも「何のために存在するのか」「誰を、どのような行動を評価するためのものなのか」という、土台となるべき「社長の理念」が、不在であるか、あるいは完全に形骸化してしまっていることなのです。
土台がグラグラな土地に、いくら立派な家を建て増ししても、いずれ崩れ落ちるのは当然のことです。
あなたの会社が繰り返している改善は、この根本原因から目を背けた、ただの対症療法になっていませんか?
失敗のループを断ち切るための最終兵器
では、この絶望的な失敗のループを断ち切るためには、どうすれば良いのでしょうか。
もっと精緻な評価項目を作ることでしょうか。
あるいは、最新の評価システムを導入することでしょうか。
いいえ、違います。
必要なのは、ただ一つ。
社長であるあなた自身が、自社の「理念」に、もう一度、真剣に向き合うことです。
この記事が提示する「理念から始める改善アプローチ」こそが、失敗のループを断ち切るための、唯一無二の「最終兵器」なのです。
9割が陥る「やってる感」だけの無意味な改善方法

本質的な話に入る前に、まずは多くの企業が時間とコストを浪費している、「やってる感」だけの無意味な改善方法について、その実態を直視しましょう。
もしかしたら、あなたの会社でも、心当たりがあるかもしれません。
社員の声を聞くフリだけのアンケート調査
制度改善の第一歩として、多くの企業が「社員満足度アンケート」や「従業員サーベイ」を実施します。
「社員の声を聞き、改善に活かします」という姿勢は、一見すると、非常に民主的で素晴らしいものです。
しかし、その実態はどうでしょう。
集まった数々の不満や要望に対して、「予算がないから」「経営方針と合わないから」といった理由で、結局は何も実行されない。
あるいは、最も声の大きい部署の意見だけを取り入れた結果、他の部署から新たな不満が噴出する。
結局、アンケートは社員の不満を一時的に吐き出させるだけの「ガス抜き」の役割しか果たさず、「どうせ、何を言っても無駄だ」という、さらなる諦めを生み出すだけなのです。
評価項目の修正という終わりなきパッチワーク
「営業部からは、プロセスも評価してほしいという声が上がっている」 「開発部からは、もっと専門性を評価する項目が必要だと言われた」
現場のそうした声に応える形で、評価シートの項目を足したり、引いたり、重み付けを変えたりする。
この、場当たり的な修正作業は、まさに「終わりなきパッチワーク」です。
根本的な設計思想、つまり「我が社は何を最も大切にするのか」という理念がないまま修正を繰り返すため、評価制度は、どんどん複雑で、矛盾に満ちた、ツギハギだらけのものになっていきます。
そして、誰もその全体像を理解できない、運用コストだけが異常に高い「モンスター制度」が誕生するのです。
評価者研修というアリバイ作りの現実
「制度がうまくいかないのは、管理職の評価スキルが低いからだ」
そう結論づけ、評価者研修を実施するのも、よくある改善方法の一つです。
しかし、その研修の中身が、評価エラーの種類や、面談の進め方といった、一般的なテクニックの紹介に終始しているとしたら、それは単なる「アリバイ作り」でしかありません。
管理職が本当に知りたいのは、小手先のテクニックではありません。
「社長は、何を基準に、部下を評価してほしいと本気で願っているのか」という、会社の「本音」です。
その「本音」が共有されないまま、テクニックだけを教えても、管理職は、ただ研修で習った通りの「正しいこと」を言うだけのロボットになるだけです。
それは、部下の心を動かす、血の通ったコミュニケーションには、決してなり得ません。
成功する1割だけが知るたった一つの改善方法

では、失敗する9割の企業を横目に、残りの1割の企業は、どのようにして人事評価制度の改善を成功させているのでしょうか。
その方法は、驚くほどシンプルですが、しかし、極めて本質的です。
改善とは制度ではなく「社長の法律」を改正すること
成功する1割の企業は、人事評価制度の「改善」を、制度という「下位のルール」を修正する作業とは捉えていません。
彼らは、それを、会社のあり方そのものを規定する「最上位の法律」、つまり「社長の理念」を、時代の変化や会社の成長に合わせて「改正」する、極めて重要な経営行為だと捉えているのです。
法律が変われば、人々の行動が変わるように、理念が変われば、社員の働き方は、おのずと変わっていきます。
彼らは、枝葉であるルールをいじるのではなく、常に、根幹である理念に立ち返るのです。
見直すべきは評価項目でなく会社の「北極星」
評価がうまくいかない時、多くの人は、評価シートに書かれた「評価項目」という、足元の石ころばかりを見てしまいます。
しかし、本当に見直すべきは、そこではありません。
会社全体が、どの方向に進むべきかを示す、夜空に輝く「北極星」です。
「我々は何のために存在するのか」 「どんな価値を社会に提供するのか」 「どんなチームでありたいのか」
この「北極星」が、社長を含め、全社員の心の中で、明確に、そして力強く輝いているか。
もし、その輝きが曇っていたり、人によって見えている星が違っていたりするならば、どんなに精緻な評価項目を作っても、組織はバラバラの方向に進むだけです。
真の改善とは、まず、この「北極星」の輝きを、取り戻す作業なのです。
改善の第一歩は社長の「えこひいき」の再定義
では、具体的に、何から始めれば良いのでしょうか。
その第一歩は、社長であるあなた自身が、自社の「えこひいき」の基準を、改めて定義し直すことです。
今のあなたの会社で、最も賞賛され、報われるべきは、どのような価値観を持ち、どのような行動をする人材でしょうか。
半年前、一年前と同じ答えでしょうか。
もしかしたら、会社のステージが変わり、市場環境が変わり、求める人材像も、少しずつ変化しているのではないでしょうか。
この「誰をえこひいきするか」という、会社の最も重要な意思決定を、社長が自らの言葉で再定義し、宣言すること。
それこそが、本質的な制度改善の、全ての始まりとなるのです。
【実践ワーク】理念から始める改善ロードマップ
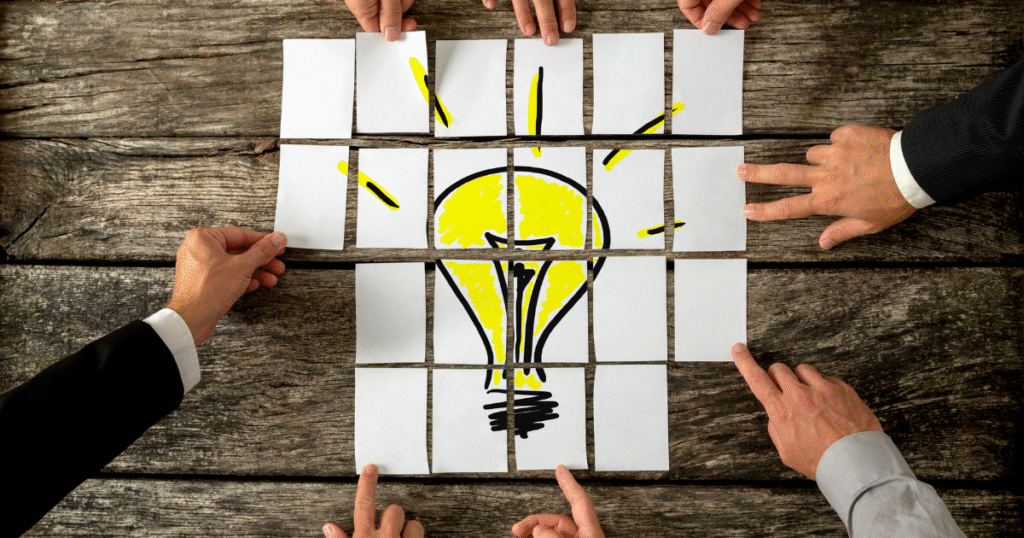
ここからは、あなたの手で、あなたの会社の「法律」を改正するための、具体的な実践ワークをご紹介します。
これは、机上の空論ではありません。
今すぐ始められる、実践的なロードマップです。
STEP1:社長が「理想のチーム像」を一枚の絵に描く
まず、ペンと、真っ白な紙を用意してください。
そして、5年後、あなたの会社が大きな成功を収め、その祝賀会を開いている場面を、ありありと想像してみてください。
その壇上で、あなたが満面の笑みで、全社員に紹介している「成功の立役者たち」は、どのような顔ぶれでしょうか。
そして、彼らは「どのような素晴らしい活躍」をしたのでしょうか。
その情景を、一枚の「絵」として、あるいは「物語」として、具体的に書き出してみてください。
「前例のない挑戦で、新たな市場を切り拓いた開発チーム」 「どんな困難な状況でも、お客様に寄り添い続けたカスタマーサポートのAさん」 「部署の垣根を越え、全社的なプロジェクトをまとめ上げたB部長」
この「理想のチーム像」こそが、あなたの会社が目指すべき、新しい「北極星」の姿です。
STEP2:新理念を等級・評価・報酬の条文に落とし込む
次に、STEP1で描いた「理想のチーム像」という新しい理念を、具体的な人事制度のルール、つまり「法律の条文」に落とし込んでいきます。
例えば、「前例のない挑戦」を最も重要な価値観とするならば、
・等級制度の改正案: 上位等級への昇格要件に、「失敗を恐れず、新規事業や業務改革を主導した経験」を明記する。
・評価制度の改正案: 評価項目から「減点項目」を減らし、「加点項目」として「チャレンジ目標」の達成度を高く評価する。
・報酬制度の改正案: 通常の賞与とは別に、最も果敢な挑戦をしたチームや個人に、特別なインセンティブを与える「イノベーション賞」を新設する。
このように、新しい理念が、等級・評価・報酬という、制度の隅々にまで、一貫して反映されるように、具体的な条文を設計していくのです。
STEP3:改正した「法律」の施行日を全社員に宣言する
最後に、そして最も重要なのが、この「改正された法律」を、全社員に、情熱を持って布告することです。
これは、単なる「制度変更の説明会」ではありません。
社長であるあなた自身が、なぜ、今、この法律を改正する必要があるのか、その背景にある想いや、新しい法律に込めた未来への期待を、自らの言葉で、熱く語る「施行式」なのです。
「我々は、これから、このような価値観を最も大切にする。この新しい法律は、そのための、我々の約束の証だ」
この社長の力強い宣言によって、新しい理念は、初めて全社員の心に届き、生きた「法律」として、組織の隅々にまで浸透していくのです。
まとめ:失敗する9割から成功する1割へ

人事評価制度の改善。
その成否を分けるのは、評価項目の数でも、評価者研修の時間でもありません。
それは、社長が、自社の「理念」という名の「法律」と、どれだけ真剣に向き合い、それを改正し、自らの言葉で語りきる「覚悟」を持てるか。
ただ、その一点にかかっています。
失敗する9割の企業は、これからも、枝葉であるルールをいじり続け、「改善疲労」のループから抜け出せないでしょう。
しかし、この記事をここまで読んでくださったあなたなら、もう、その仲間入りをする必要はありません。
成功する1割の企業になるための、本質的な方法をお伝えしました。
社長、あなたの会社は、どちらの道を選びますか?
その答えは、あなたの中にしか、ありません。
人事評価制度にお困りの方は、お気軽に村井にご相談ください。
➖ 資料請求 ➖
資料請求は下記バナーより。

➖ 問い合わせ ➖
新規事業、DX、人事制度などの経営課題に関するご相談は以下よりお受けしております。