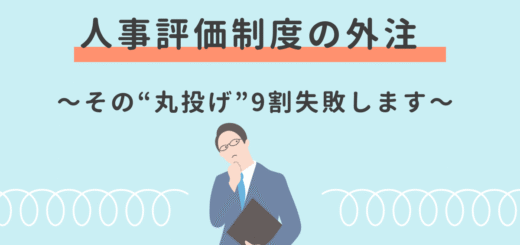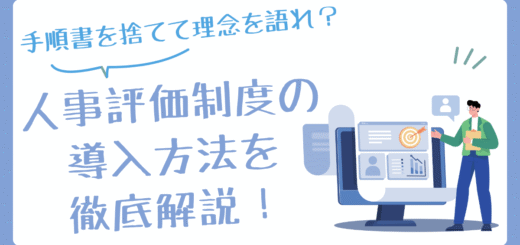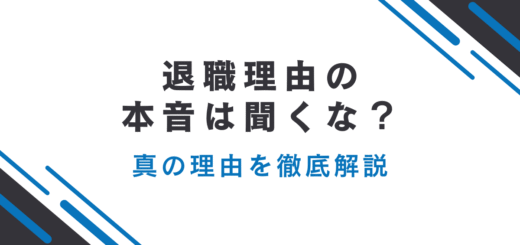介護業界の人事評価のコツ!評価基準は社長の哲学?

介護業界の人事評価。
それは多くの経営者や管理者が頭を悩ませる難解なテーマです。
利用者の満足度。 介護技術の習熟度。 チーム内での協調性。
様々な指標でスタッフの働きぶりを評価しようと試みるもののなぜかしっくりこない。
むしろ形式的な評価が現場の負担を増やしスタッフの心を冷めさせている。
そんな状況に陥っていませんか。
もしそうだとすればあなたは人事評価の本質を見誤っているのかもしれません。
この記事では介護業界特有の人事評価の難しさを解き明かします。
巷で語られる一般的な評価項目の限界を指摘し評価基準の根幹にあるべきものが何かを解説していきます。

【村井 庸介(むらい ようすけ)】
大学卒業後は株式会社野村総合研究所に入社し通信業・製造業の経営コンサルティングに携わる。その後リクルート、グリー、日本IBMに転職。その中でグリー株式会社にて人事制度設計に携わった。
2015年に独立後は、社員30名のベンチャー企業から5,000名を超える大企業まで幅広く人事制度設計や導入伴走に携わる。顧客業種は製造業、サービス、IT企業が中心。経営理念・事業戦略から逆算した人事制度構築を得意とする。
なぜ介護業界の人事評価は難しいのか

介護の仕事は他の多くの職種と異なりその価値を客観的な指標だけで測ることが極めて困難です。
だからこそ多くの事業所が評価制度の設計と運用に苦労しています。
スキルだけでは測れない本当の価値
介護の仕事は単なる作業ではありません。
それは利用者の心に寄り添いその人らしい生活を支える人間的な営みです。
もちろん介護技術や知識は重要です。
しかしそれだけでは測れない価値があります。
利用者の小さな変化に気づく観察眼。 不安な気持ちを受け止める共感力。 尊厳を守ろうとする倫理観。
これら数値化できない「心」の部分こそ介護の仕事の核であり本当の価値なのです。
スキル偏重の評価はこの最も大切な価値を見落としてしまいます。
他職種とは違う評価のポイント
介護職の評価が難しいもう一つの理由は他職種との「貢献の形」と「時間軸」の違いです。
例えば営業職であれば売上という短期的な成果が見えやすいかもしれません。
しかし介護職の貢献はすぐには結果として現れないことが多い。
日々の丁寧な関わりが数ヶ月後数年後の利用者のQOL(生活の質)向上に繋がるのです。
また介護は一人で行うものではなく多職種が連携する「チームケア」が基本です。
個人の成果だけを切り取って評価することが必ずしもチーム全体の質の向上には繋がらないのです。
多くの介護事業所が陥る評価の罠
こうした特殊性を理解しないまま一般的な評価制度を導入すると多くの事業所が罠に陥ります。
評価しやすいスキルや資格ばかりを重視し人間的なケアの価値を軽視してしまう。
短期的な成果を求め長期的な視点での利用者支援や人材育成がおろそかになる。
個人の評価に偏るあまりチーム内の協力体制が崩れてしまう。
結果として評価制度が現場の士気を下げ介護の質そのものを低下させるという本末転倒な事態を招くのです。
一般的な介護職の人事評価項目

では世間一般では介護職の人事評価においてどのような項目が重視されているのでしょうか。
まずはその全体像を把握しておきましょう。
「成果評価」利用者満足度や業務効率
まず挙げられるのが「成果」に関する評価です。
利用者やその家族からの満足度アンケートの結果。 担当する利用者のADL(日常生活動作)の変化。 業務改善提案の数や採用率。 残業時間の削減率など業務効率に関する指標。
これらは比較的客観的に測定しやすい指標として用いられることがあります。
「能力評価」介護スキルや専門知識
次に「能力」に関する評価です。
介護技術(食事入浴排泄介助など)の習熟度。 認知症ケアや医療的ケアに関する専門知識。 資格の取得状況。 研修への参加状況などが評価項目となります。
スタッフの専門性向上を促す目的で設定されます。
「情意評価」協調性や倫理観
そして「情意」つまり仕事への姿勢に関する評価も重要視されます。
チーム内での協調性や情報共有の姿勢。 利用者に対する丁寧な言葉遣いや態度。 介護倫理や法令遵守の意識。 向上心や学習意欲などが評価されます。
介護職としてのプロフェッショナリズムを測る指標です。
これらの指標だけでは不十分な理由
これらの一般的な評価項目はそれぞれ一定の意味を持ちます。
しかしこれらを組み合わせるだけでは介護職の「本当の価値」を捉えるには全く不十分だと私は考えます。
なぜならこれらの指標の多くは依然として「測りやすいもの」を測っているに過ぎないからです。
利用者の心の機微に寄り添う力。 チームの雰囲気を良くするムードメーカーとしての役割。 困難な状況でも諦めない粘り強さ。
こうした数字やチェックリストには現れない人間的な貢献こそ介護現場を支える土台なのです。
これらの指標だけを追い求める評価は本質を見失わせる危険性を孕んでいます。
評価基準は社長の哲学?

では本当の価値を評価するためには何が必要なのでしょうか。
私はその答えは社長であるあなた自身の「哲学」にあると確信しています。
人事評価は社長の理念を映す鏡
人事評価制度は単なる評価ツールではありません。
それは社長であるあなたの「理念」や「価値観」がそのまま映し出される「鏡」なのです。
あなたが「何を大切にしどんな介護を提供したいのか」という想いが評価基準や評価項目という形で具体化されます。
スタッフは評価制度という鏡を見て「この会社は何を目指しているのか」「社長は何を求めているのか」を理解します。
もし鏡が曇っていたり歪んでいたりすればあなたの本当の想いはスタッフには伝わりません。
介護の質は社長のケア哲学で決まる
介護の質は最新の設備やマニュアルだけで決まるものではありません。
それは社長であるあなたがどのような「ケア哲学」を持っているかによって大きく左右されます。
利用者の尊厳を何よりも大切にするのか。 効率性を最優先するのか。 スタッフの働きがいを重視するのか。
あなたの哲学が評価基準となりスタッフの行動を方向づけ結果として提供される介護の質そのものを形作るのです。
評価基準とはまさに社長のケア哲学の表明に他なりません。
哲学なき評価は魂のない作業
もしあなたの会社の人事評価制度に明確なケア哲学という背骨が通っていなければどうなるでしょうか。
評価はただ点数をつけ処遇を決めるための「魂のない作業」と化します。
スタッフは評価項目をクリアすることだけを考え哲学なき介護ロボットのようになってしまうかもしれません。
評価のための評価に現場は疲弊し本来の目的である利用者の幸せは置き去りにされてしまうのです。
哲学なき評価は介護現場から人間らしさを奪います。
設計のコツ① 介護職評価と他職種の違い

社長の哲学を評価制度に落とし込む前に介護職評価の特殊性を改めて深く理解しておく必要があります。
他職種との違いを明確に意識することが失敗しない設計の第一歩です。
感情労働という特殊性
介護の仕事は利用者の様々な感情を受け止め寄り添う「感情労働」としての側面が非常に強い。
これは他の多くの職種にはない大きな特徴です。
スタッフは常に自身の感情をコントロールし時に理不尽な要求やクレームにも対応しなければなりません。
この精神的な負担やストレスを評価制度の中でどのように考慮しケアしていくかという視点が不可欠です。
単なる成果やスキルだけではこの側面を評価できません。
成果の見えにくさと時間軸
介護の「成果」は売上のように明確な数字で測れるものばかりではありません。
利用者の笑顔が増えた。 家族が安心できるようになった。 最期までその人らしく生きられた。
これらの価値は目に見えにくくまたその実現には長い時間がかかります。
短期的な成果だけを追い求める評価制度はこうした本質的な価値を見落とす危険があります。
長期的な視点での貢献を評価する仕組みが必要です。
チームケアの重要性
介護は決して一人では完結しません。
医師看護師ケアマネージャーリハビリ専門職そして介護スタッフ。
様々な職種が連携し情報を共有しそれぞれの専門性を活かして初めて質の高い「チームケア」が実現します。
個人の能力や成果だけを評価するのではなくチーム全体への貢献度や連携力をいかに評価するか。
これも介護職評価の重要な設計ポイントとなります。
設計のコツ② 社長の哲学を評価制度に実装する
介護職評価の特殊性を理解した上でいよいよ社長の哲学を具体的な制度へと「実装」していきます。
ここでのキーワードは「言語化」「翻訳」「浸透」です。
社長の理想のケアを言語化する
まず社長であるあなた自身が「どんな介護を提供したいのか」「どんなスタッフと働きたいのか」という「理想のケア」を明確な言葉で描き出す必要があります。
それは抽象的な美辞麗句ではありません。
あなたの心の中にある具体的な「こだわり」や「譲れない価値観」です。
「利用者一人ひとりの物語を大切にするケア」 「家族のように温かい雰囲気の施設」 「常に学び続け変化を恐れないチーム」
この言語化された理想像こそが評価制度の魂となります。
哲学をシンプルな評価項目に翻訳する
次にその言語化された哲学(理想像)をできるだけシンプルな「評価項目」へと翻訳していきます。
介護現場のスタッフにも理解できるよう具体的で分かりやすい言葉を選ぶことが重要です。
例えば「利用者の物語を大切にする」なら評価項目は「個別ケア計画への主体的な関与」や「利用者・家族との深い対話」かもしれません。
「温かい雰囲気」なら「チームへの気配りと思いやり」かもしれません。
哲学と現場の行動を結びつける翻訳作業が設計の肝です。
評価頻度と対話で哲学を浸透させる
そして最も重要なのがこの新しい「法律」の精神を評価というプロセスを通じて現場に浸透させていくことです。
年に一度の評価では意味がありません。
できれば毎月あるいは毎週のように上司と部下が1対1で向き合い理念に照らして日々のケアを振り返り未来について語り合う「対話の機会」を設けるべきです。
この頻繁な対話こそが哲学を血肉に変え制度を「生きた仕組み」にするのです。
まとめ 哲学なき評価をやめ理念で人を育てる

介護業界の人事評価。
その本質はスキルや成果といった目に見えるものを測ることではありません。
それは社長の「ケア哲学」という名の理念を組織の隅々にまで浸透させその理念に基づいて行動する人材を育て賞賛することなのです。
明日から経営者ができること
もしあなたが今の介護評価に疑問を感じているなら明日からたった一つ始めてみてほしいことがあります。
それはスタッフとの面談の場で評価シートの点数について話す前にこう問いかけることです。
「今週あなたが最も『私たちの理念』を体現できたと感じる瞬間はどんな時だった?」
その問いこそがあなたの事業所の評価軸を「作業」から「哲学」へと変える小さなしかし極めて重要な第一歩となるはずです。
あなたのケア哲学を形にする個別相談
もしあなたが自社の「ケア哲学」を言語化しそれをスタッフの心に響く「生きた評価制度」へと昇華させたいと願うならば。
ぜひ私にご相談ください。
私は単なる制度の作り方を教えるのではありません。
社長であるあなたの「想い」を形にし利用者からもスタッフからも愛される最高の介護現場を創るための「物語」を共に創り上げるお手伝いをします。
あなたの事業所の新たな物語が始まるその瞬間に立ち会えることを心から楽しみにしています。
人事評価制度にお困りの方は、お気軽に村井にご相談くださいね。
➖ 資料請求 ➖
資料請求は下記バナーより。

➖ 問い合わせ ➖
新規事業、DX、人事制度などの経営課題に関するご相談は以下よりお受けしております。