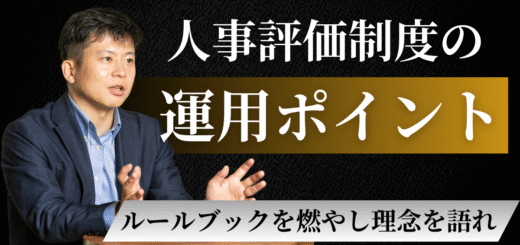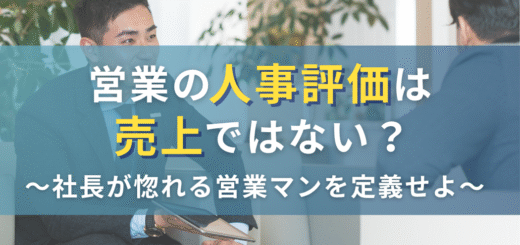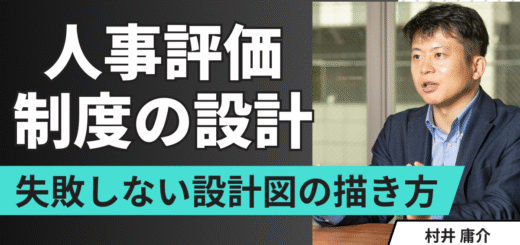人事評価制度の外注【その“丸投げ”9割失敗します】
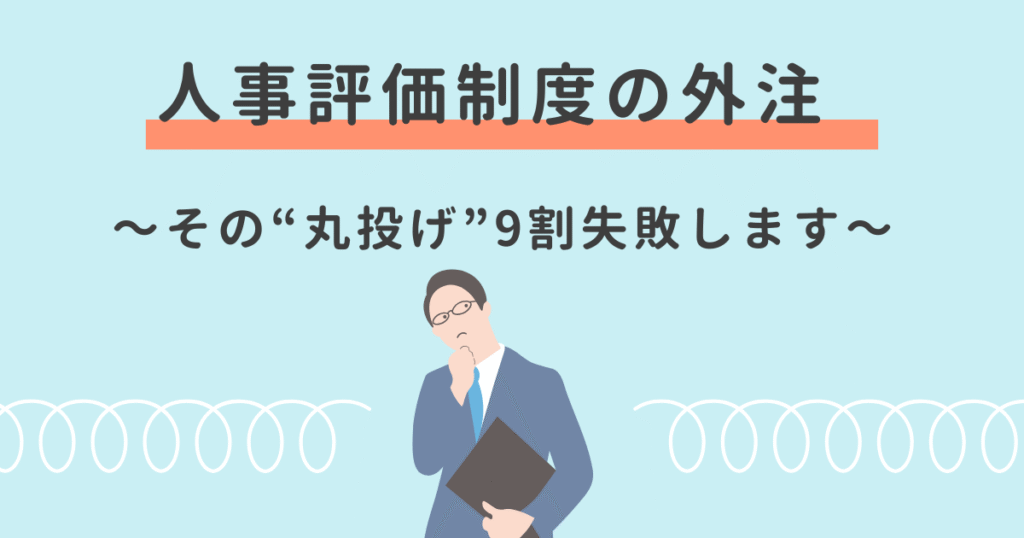
「人事評価制度を新しくしたいが、社内にノウハウがない」
「専門家に任せた方が、早くて良いものができるのではないか」
人事担当者や経営者の皆様は今、そう考えて人事評価制度の外注を検討しているかもしれません。
しかし、その一歩が、あなたの会社を未来永劫にわたって苦しめる「失敗の始まり」になる可能性が非常に高いことをご存知でしょうか。
衝撃的な事実ですが、目的が曖昧なまま行われる人事評価制度の外注は、その実に9割が失敗に終わります。
この記事では、巷にあふれる「外注のメリット・デメリット」といった表面的な解説ではなく、なぜあなたの会社の未来を想うその決断が、意図とは真逆に、社員の士気を下げ、優秀な人材を流出させるだけの結果を招いてしまうのか。
その根本的な原因と、失敗する9割から抜け出し、成功する1割の企業になるための「本質的な外注との向き合い方」を、具体的にお伝えします。
もし、あなたが外注という選択肢で本当に会社を良くしたいと願うなら、ぜひ、最後までお読みください。

【村井 庸介(むらい ようすけ)】
大学卒業後は株式会社野村総合研究所に入社し通信業・製造業の経営コンサルティングに携わる。その後リクルート、グリー、日本IBMに転職。その中でグリー株式会社にて人事制度設計に携わった。
2015年に独立後は、社員30名のベンチャー企業から5,000名を超える大企業まで幅広く人事制度設計や導入伴走に携わる。顧客業種は製造業、サービス、IT企業が中心。経営理念・事業戦略から逆算した人事制度構築を得意とする。
なぜ人事評価制度の外注は9割失敗するのか
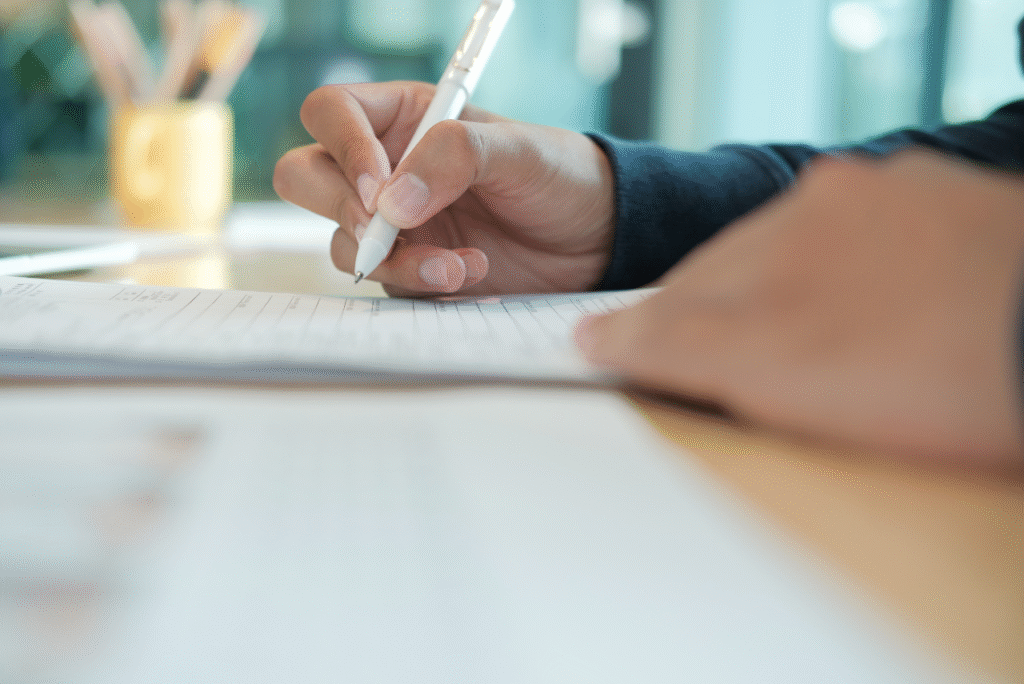
多くの企業が時間とコストを投じて人事評価制度を外注します。
しかし、そのほとんどが「作って終わり」となり、現場に混乱と不満だけを残して形骸化していくのはなぜでしょうか。
その理由は、外注という行為そのものではなく、その「やり方」にあります。
「丸投げ」が引き起こす3つの悲劇
失敗する9割の企業に共通するのは、制度設計の「丸投げ」です。
「とにかく、うちにも何か良い感じの評価制度を作ってください」 この一言が、取り返しのつかない3つの悲劇を引き起こします。
一つ目の悲劇は、現場の混乱と反発です。
外部のコンサルタントが持ってきた「一般的で美しい」テンプレートは、あなたの会社の文化や実態とはかけ離れており、社員は「なぜこんな評価をされるのか」と納得できず、制度への不信感を募らせます。
二つ目の悲劇は、優秀な人材の流出です。
テンプレートで作られた魂のない制度は、本当に会社に貢献している「縁の下の力持ち」や「未来への挑戦者」を正しく評価できません。
正当に評価されないと感じた優秀な社員ほど、静かに会社を去っていきます。 そして三つ目の悲劇が、経営理念の形骸化です。
社長が朝礼で立派な理念を語っても、社員を評価する「法律」である人事制度がその理念と真逆の評価をくだすなら、社員はどちらを信じるでしょうか。
言うまでもなく、後者です。 こうして、会社の理念はただのお題目に成り下がるのです。
失敗の根源は社長の理念の不在
これら3つの悲劇は、すべて同じ根源から生まれています。
それは、制度の根幹をなすべき「社長の理念」が、そこに存在しないことです。
そもそも、この会社は何を最も大切にし、どのような行動を尊び、どんな人間の集団でありたいのか。
この問いに対する社長自身の明確な答えがないまま、ただ外部の専門知識に依存して形だけを整えようとする。
魂を込めるべき設計図を社長が描かずに、ただ腕の良い大工に「立派な家を建ててくれ」と丸投げしている状態です。
どんなに立派な家が建っても、そこに住みたいと思う家族(社員)は一人もいないでしょう。
人事制度の本質は社長のメッセージ
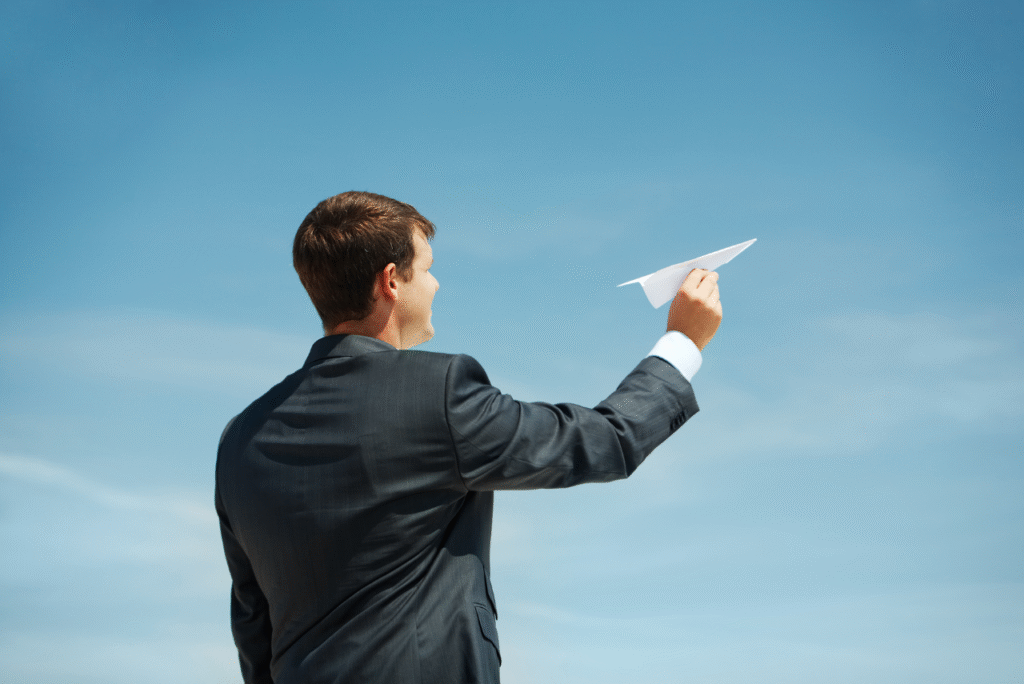
では、そもそも人事評価制度とは何のために存在するのでしょうか。
それを理解せずして、外注の成功はあり得ません。 その本質は、驚くほどシンプルです。
評価制度とは会社の法律そのもの
成功している経営者は、人事評価制度を単なる査定ツールだとは微塵も思っていません。
彼らにとって評価制度とは、「会社という王国の法律」そのものです。 誰を昇進させ、誰により多くの報酬を分配し、どのような行動をした者を評価するのか。
そのルールを定めることは、この国で何を正義とし、何を目指すのかを内外に示す、最も重要な統治行為なのです。
法律なき国家が成り立たないように、社長の哲学なき評価制度は、ただの紙切れでしかありません。
評価とは社長のえこひいきの言語化
「えこひいき」とは、一般的に悪い意味で使われる言葉です。
しかし、会社経営においては、社長による明確な「えこひいき」こそが、組織を強くする原動力となります。
なぜなら、人事評価制度の本質とは、社長が「我が社では、こういう行動をする社員を“えこひいき”します」と、全社員に対して公式に宣言するための仕組みだからです。
挑戦し続ける人材をえこひいきするのか、和を乱さない人材をえこひいきするのか。
その「えこひいき」の基準こそが、会社の文化を創り上げていくのです。
外注を考える前に、まず社長自身が、誰をえこひいきしたいのかを言語化する必要があります。
失敗する外注と成功する外注の決定的な違い

「外注は悪」と言いたいわけでは決してありません。
外部の専門知識は、正しく使えば強力な武器になります。
問題は、その使い方です。 失敗する外注と、成功する外注の間には、天と地ほどの決定的な違いが存在します。
失敗する外注は制度のテンプレートを買う
失敗する企業の典型的なパターンは、「制度のテンプレート」を買おうとすることです。
コンサルタントや業者に「他社で成功した事例を参考に、うちにも合う制度を作ってください」と依頼します。
業者は喜んで、見た目がきれいで論理的に整理された「正解らしき」テンプレートを納品するでしょう。
しかし、それはあなたの会社のために作られたものではありません。 誰の肌にも合わない、既製服と同じです。
これを導入することは、あなたの会社の独自の文化や価値観を、無個性なテンプレートで上書きしてしまう行為に他なりません。
成功する外注は理念の言語化を支援させる
一方、成功する企業は、外注先に「制度を作ってください」とは決して言いません。
彼らが依頼するのは、「我々の理念を、制度という形に翻訳するのを手伝ってください」ということです。
まず社長自身が、会社の「北極星」となる理念や価値観を必死に言語化する。
そして、その魂の叫びを、外部の専門家が持つ客観的な視点と専門知識を借りて、等級、評価、報酬という具体的な「法律」の条文に落とし込んでいくのです。
この場合、外注先は制度の設計者ではなく、社長の理念の「翻訳家」であり、思考を整理するための「壁打ち相手」となります。
主役はあくまで社長自身なのです。
会社の魂を守る外注パートナーを見抜く

では、あなたの会社の魂を守り、理念の翻訳家となってくれる「本物のパートナー」は、どうすれば見つけられるのでしょうか。
高額な見積書や、きらびやかな実績に騙されてはいけません。 見抜くためのポイントは、契約前の段階にこそあります。
見積もりの前に実績より哲学を確認する
パートナー候補のコンサルタントや業者を見つけたら、まずその会社のウェブサイトやブログを隅々まで読み込んでください。
そこで見るべきは、「導入実績〇〇社!」といった過去の栄光ではありません。
その会社が、人事制度についてどのような「哲学」を持っているかです。 もし、その会社の情報発信が「最新の評価手法」「効率的な制度設計」といったテクニック論ばかりであれば、要注意です。
彼らは、制度のテンプレートを売る業者である可能性が高いでしょう。
逆に、「制度の前に、まず理念」「社長の役割が最も重要」といった、プロセスの根幹に関わる哲学を語っているならば、その会社は信頼できるパートナー候補です。
テンプレートを売る業者を見抜く質問
次に、実際のカウンセリングや商談の場で、相手がテンプレートを売る業者かどうかを見抜くための質問を投げかけてみましょう。
例えば、こう聞いてみてください。 「人事評価制度において、最も重要だとお考えのことは何ですか?」 この質問に対して、「公平性です」「納得感です」「目標管理です」といった一般的な答えが返ってきたら、彼らはテンプレート思考の業者です。
しかし、「それは、社長がその制度を通して、社員に何を伝えたいかです」と、理念の重要性を指摘してきたならば、そのコンサルタントは本質を理解しています。
この一つの質問で、相手の実力と哲学の深さを測ることができます。
社長の壁打ち相手になるコンサルタントを選べ
最終的にあなたが選ぶべきは、立派な提案書を持ってくるコンサルタントではありません。
社長であるあなたに対して、耳の痛いことも含めて本質的な問いを投げかけ、思考の整理を手伝ってくれる「壁打ち相手」となってくれるコンサルタントです。
「社長が本当に実現したいチームは、どんなチームですか?」 「そのために、今いる社員に、本当はどうなってほしいのですか?」 こうした厳しい問いに向き合うプロセスこそが、血の通った人事制度を生み出すのです。
あなたの会社の魂を守るパートナーは、安易な答えをくれる人ではなく、あなたから答えを引き出してくれる人なのです。
よくある質問

ここでは、人事評価制度の外注に関して、経営者の方々からよく寄せられる質問にお答えします。
費用はいくらかかるのか
人事評価制度の外注費用は、依頼する業務範囲や企業の規模によって大きく異なり、数十万円から数百万円以上まで幅があります。
テンプレートを導入するだけの安価なサービスもありますが、この記事で解説してきた通り、そうした外注は失敗のリスクが極めて高いです。
本質的な成功を目指すのであれば、社長の理念の言語化から伴走してくれる、質の高いコンサルティングへの投資が必要になります。
それは、目先のコストではなく、会社の未来を創るための「投資」と考えるべきでしょう。
社長はどこまで関わるべきか
結論から言えば、社長は「制度の根幹となる理念と方針を決定するまで」は、100%関わるべきです。
これは、誰にも代行できない、創業者であり経営者であるあなたの最も重要な仕事です。
会社の「北極星」と「法律の基本方針」さえ社長自身が定めれば、その後の具体的な条文作りや運用の詳細設計といった実務的な部分は、信頼できる人事担当者や外部パートナーに任せることも可能です。
しかし、その魂を込める最初のプロセスを省略しては、絶対に成功はありません。
まとめ
この記事では、なぜ9割もの人事評価制度の外注が失敗に終わるのか、その真実を解説してきました。
失敗の原因は、外注という手段そのものではなく、会社の魂であるべき「社長の理念」を他人に丸投げしてしまう、その姿勢にあります。
人事評価制度の外注とは、制度のテンプレートを買うことではありません。 社長が自らの手で会社の「法律」を定めるために、その思考の整理と翻訳作業を支援してくれる「パートナー」を見つけることなのです。
どうか、耳障りの良い言葉を並べる業者や、安価なテンプレートに惑わされないでください。
あなたの会社の魂を守り、未来を創ることができるのは、社長であるあなたしかいません。
この記事が、そのための第一歩を踏み出すきっかけとなったなら幸いです。
人事評価制度にお困りの方は、お気軽に村井にご相談ください。
➖ 資料請求 ➖
資料請求は下記バナーより。

➖ 問い合わせ ➖
新規事業、DX、人事制度などの経営課題に関するご相談は以下よりお受けしております。