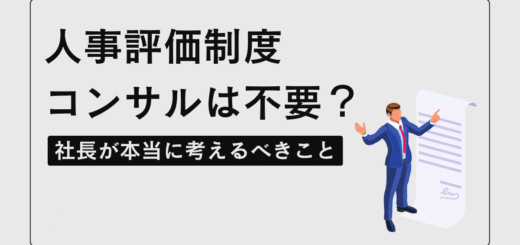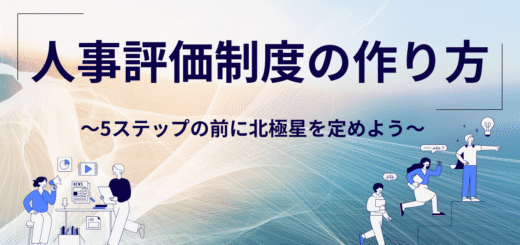人事評価制度とは?導入のコツから運用方法まで
このコラムではクラフトビール会社の新規事業で年商1億円を達成してから1.5倍2倍へと成長させてきた村井が、その実践的なノウハウを紹介しています。
またコンサルティング会社として新規事業の立ち上げをサポートした、または大手の会社とのお仕事から培ってきた経験をお届けしています。
今回は「人事評価制度とは?導入のコツから運用方法まで」というテーマで解説します。

【村井 庸介(むらい ようすけ)】
大学卒業後は株式会社野村総合研究所に入社し通信業・製造業の経営コンサルティングに携わる。その後リクルート、グリー、日本IBMに転職。その中でグリー株式会社にて人事制度設計に携わった。
2015年に独立後は、社員30名のベンチャー企業から5,000名を超える大企業まで幅広く人事制度設計や導入伴走に携わる。顧客業種は製造業、サービス、IT企業が中心。経営理念・事業戦略から逆算した人事制度構築を得意とする。
第1章:人事評価制度とは?

人事評価制度の基本的な定義と役割
人事評価制度とは、企業が従業員の能力・実績・行動などを客観的な基準に基づいて評価する仕組みのことです。
従業員の頑張りを正当に評価し、それを「昇給・賞与・昇進・教育・配置転換」といった人事施策につなげるための基盤制度となります。
評価制度の役割は、単に「人を点数で評価する」ことではありません。
むしろ以下のような企業課題の解決に貢献します。
- 従業員のモチベーション向上
- 成果主義や公平性の担保
- 経営戦略と個人の目標をリンクさせる
- 育成・能力開発における課題の可視化
このように、人事評価制度は経営と人材の橋渡しとなる重要な機能を持っています。
なぜ今、人事評価制度が注目されているのか
近年、人事評価制度が改めて注目されている背景には、次のような環境変化があります。
- 成果主義やジョブ型雇用へのシフト
年功序列から脱却し、成果や能力に基づく人事制度が主流になりつつあります。 - 離職率の上昇と従業員エンゲージメントの低下
社員が「評価されていない」と感じると、離職やモチベーション低下に直結します。
透明性の高い評価制度は、信頼と納得感を生み、従業員の定着を促します。 - 中小企業でも人材確保が難しくなっている
給与や待遇だけでなく、成長実感やキャリア支援の有無が求職者に重視される時代。
「評価制度がある=育成の文化がある会社」という信頼にもつながります。
こうした背景から、「制度を整えたいが、どう始めたらいいかわからない」と悩む中小企業が増えており、ニーズが高まっています。
制度導入が企業にもたらすメリットと目的
人事評価制度の導入は、経営側・従業員側の双方にとって以下のようなメリットがあります。
▷ 経営側のメリット
- 公平な評価により、不満や離職の抑制
- 業績と評価が連動し、生産性が向上
- 適材適所の人事配置が可能に
- 社内教育や研修計画の設計がしやすくなる
▷ 従業員側のメリット
- 自分の強み・弱みが可視化され、成長実感を得やすくなる
- キャリアパスや目標が明確になる
- 正当な評価により、納得感ある昇給・昇進につながる
また、経営戦略と評価制度が連動することで、「目標達成型の組織文化」が育まれます。
これは大手企業の人事戦略でも明確に示されており、今後ますます中小企業にも広がると考えられます。
第2章:人事評価制度の種類と特徴

人事評価制度は、目的や業種、企業規模によってさまざまなタイプがあります。
ここでは、代表的な評価方法とその特徴、組み合わせ方のコツについて紹介します。
業績評価・能力評価・情意評価の違い
人事評価制度の基礎的な評価軸は、一般に以下の3つに分類されます。
| 種類 | 評価内容 | 特徴 |
|---|---|---|
| 業績評価 | 売上・利益・成果などの数値 | 客観的だが職種により評価が難しい場合あり |
| 能力評価 | 業務遂行力・専門スキル | キャリア開発や教育に連動しやすい |
| 情意評価 | 勤怠・積極性・協調性など | 主観が入りやすく、曖昧さに注意が必要 |
多くの企業では、これらを**組み合わせて「多面的に評価」**するスタイルを取っています。
たとえば営業職であれば「業績評価」を重視し、バックオフィスでは「能力・情意評価」に比重を置くなど、職種によるバランス調整も重要です。
コンピテンシー評価とは?
コンピテンシー(Competency)評価とは、「成果を出す人が共通して持つ行動特性」に基づいて評価する手法です。
たとえば「リーダーシップ」「課題解決力」「チームワーク」などがコンピテンシーの一例です。
コンピテンシー評価のメリット:
- 具体的な行動を評価するため、納得感が高い
- 抽象的な“感覚評価”を排除できる
- 行動目標として社員に示しやすく、育成にも直結する
特に中小企業では、「何をもって優秀とするか」の基準が曖昧になりやすいため、明確な行動指針を持つコンピテンシー型評価は有効です。
成果主義・プロセス評価・360度評価などの応用型評価制度
より高度な評価制度として、以下のような発展型手法も存在します。
▷ 成果主義評価
個人の実績(数字や成果)を中心に評価。成果主義はモチベーションを高めやすい反面、短期的な結果偏重や社内競争の激化を招くリスクもあるため、評価制度の設計には注意が必要です。
▷ プロセス評価
結果だけでなく、「そこに至るまでの過程や努力」を重視します。
行動プロセスを見える化することで、成果が出ない時期の社員も正しく評価できます。
▷ 360度評価
上司・同僚・部下・他部門など複数方向からフィードバックを集める評価制度。
上司の主観だけに偏らず、公平性を高めることができますが、組織風土の成熟度が問われるため、導入は段階的に行うのが一般的です。
補足:ハイブリッド型評価制度とは?
現在は「どれか一つ」ではなく、目的に応じて複数の評価軸を組み合わせたハイブリッド型評価制度が主流です。
例えば
- 「能力+業績+情意」の三本柱評価
- 「コンピテンシー評価+KPI設定」で行動と成果を両立
- 「プロセス重視型+成果主義+評価面談」の三層構成 など
中小企業では、まずはシンプルな2軸(能力+成果)からスタートし、徐々に制度を拡張していくのがおすすめです。
第3章:人事評価制度の導入ステップ

人事評価制度は、ただ仕組みを用意すれば機能するわけではありません。
目的の明確化→制度設計→社内浸透→運用改善というステップを段階的に進めることで、初めて機能する制度になります。
この章では、制度導入の流れと、つまずきやすいポイントを整理します。
制度導入の全体フロー
人事評価制度導入の流れは、大きく以下のように分かれます:
- 目的の明確化
なぜ評価制度を導入するのか?(例:人材育成/公平な昇給判断/社員定着など)
▶︎ 制度は“目的”から逆算して設計すべきです。 - 現状分析と課題抽出
既存の評価制度がある場合は、評価のバラつきや社員の不満点を把握
制度がない場合も、課題感(例:評価が属人的、モチベーション低下)を明文化 - 制度設計
評価項目・評価基準・評価者体制・評価サイクルを構築
※詳細は次章で解説 - ルールブック・運用マニュアル作成
運用ルールを文書化し、評価者・被評価者に説明できるようにする - トライアル実施(評価者訓練含む)
いきなり本格導入せず、1回目はテスト的に運用する企業が多い
▶︎ フィードバックと振り返りを重視 - 本格導入・定着支援
制度を社内文化として根づかせるため、説明会や面談支援を継続
導入前に整理すべき自社課題
制度設計前に、次のような「現場の実態」を把握しておくことが重要です。
- 評価が給与や昇格とどう結びついているか(or いないか)
- 管理職が部下を評価する際に悩んでいる点
- 社員が「評価」に対してどのような不満や期待を持っているか
- 今の会社で「育っている人」と「伸び悩んでいる人」の違いは何か?
これらは、制度を「現場に合った形」にするための土台になります。
可能であれば、匿名アンケートや1on1面談を通じて情報を収集しましょう。
関係者の巻き込み方と社内浸透のコツ
制度導入を成功させるには、「トップダウン」「現場巻き込み」「継続改善」の3点が重要です。
1. トップのコミットメント
経営層が「評価制度で会社をよくする」という姿勢を見せ、一貫したメッセージを出すことが第一歩です。
2. 評価者(管理職)への事前研修
評価基準の解釈やフィードバックの方法を、評価者全員に共有することで運用のブレを防ぎます。
3. 被評価者(一般社員)への丁寧な説明
制度の背景・評価項目・評価の使い方(昇給、昇進)を伝え、「納得感のある制度」に変えていく必要があります。
制度の内容だけでなく、「なぜ今、制度が必要なのか」をしっかり伝えることで、反発や形骸化を防げます。
第4章:評価項目・評価基準の設計方法
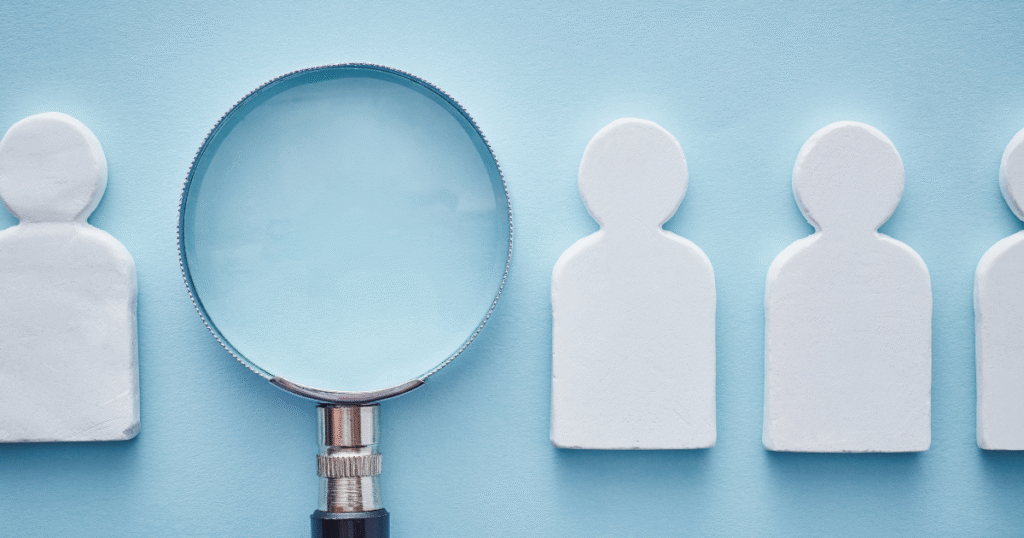
人事評価制度を形骸化させないためには、「評価項目」と「評価基準」の設計が肝心です。
誰が見ても納得でき、かつ行動につながるような指標をつくることが、制度の成功を左右します。
評価指標(KPI・KGI)の設定方法
評価項目の中核となるのが、KPI(重要業績評価指標)やKGI(最終的な成果目標)です。
▷ KGI(Key Goal Indicator)
企業や部署の最終的な目標値
例:年間売上●千万円達成、新規顧客数100件獲得 など
▷ KPI(Key Performance Indicator)
KGIを達成するためのプロセス目標
例:月間訪問件数20件、提案数30件、商談成約率40%など
評価項目をKGIだけにすると「数字に偏った評価」になりがちですが、KPIも取り入れることで“努力の過程”も評価可能になります。
職種・役職別にカスタマイズするポイント
全社員に同じ評価項目をあてはめるのは非現実的です。
職種や役割に応じて、**評価項目を“7~8割共通+2~3割カスタマイズ”**するのが一般的です。
【例:営業職】
- 共通:協調性、勤怠、報連相
- 個別:受注金額、新規開拓数、クロージング率
【例:総務職】
- 共通:協調性、業務遂行能力、マナー
- 個別:社内ルール整備、社員満足度、備品コスト削減率
中小企業では、汎用評価項目をベースにしつつ、個別職種の成果や貢献度が見えるよう微調整するのが現実的です。
「定性評価」と「定量評価」のバランス設計
評価基準には、大きく2つのタイプがあります。
| 評価タイプ | 内容 | 例 | メリット |
|---|---|---|---|
| 定量評価 | 数字で評価 | 売上額、件数、達成率 | 客観性が高い |
| 定性評価 | 行動や姿勢 | 責任感、リーダーシップ、主体性 | チーム力や個人性を加味できる |
両方のバランスが重要です。
▶︎ 成果(定量)だけでなく、プロセスや人柄(定性)も評価することで納得感が生まれます。
特に「定性評価」は評価者の主観が入りやすいため、行動例を明記した評価シートなどを作成して、評価のブレを防ぐ工夫が求められます。
第5章:評価の運用・実施プロセス

制度を設計しても、「運用」がうまくいかなければ評価制度はすぐに形骸化します。
ここでは、評価の実施フロー、面談のコツ、評価結果の活用方法、そして制度を定着させるための改善サイクルについて解説します。
評価面談の進め方とフィードバックの質を高める工夫
評価面談は、単なる「評価の通知」ではなく、部下の成長を促す重要なコミュニケーションの場です。
【面談の基本ステップ】
- 事前準備(評価者は評価シートを確認し、実例を把握)
- 自己評価の確認(被評価者に話をさせる)
- 評価結果のフィードバック(ポジティブ+改善点)
- 次期目標の共有とコミットメント
- 不満・要望のヒアリングと合意形成
ポイントは、「一方的に伝える」のではなく、双方向で信頼を築く対話の場にすること。
フィードバックでは、「事実ベース」で、行動に対する評価を明確に伝えるのが効果的です。
評価結果をどう活用するか(昇給・賞与・配置転換)
評価はゴールではなく、「処遇・育成」に活用してこそ意味があります。
【主な活用方法】
- 昇給・賞与の決定:評価ランクに応じて昇給幅や賞与率を決定
- 昇進・登用:高評価者を次世代リーダー候補として選抜
- 人材配置:適性を見て配属先や職務変更に活用
- 研修計画の立案:評価結果からスキル不足・成長機会を可視化
処遇との連動がない制度は、「評価されても意味がない」と感じさせてしまい、社員の信頼を失う要因になります。
評価制度を定着させるための継続的改善サイクル
評価制度は一度導入して終わりではなく、運用を通じて“育てる”ことが必要です。
【PDCAサイクル例】
- Plan(設計):制度・評価項目の設計
- Do(実行):評価実施、面談の実施
- Check(評価):制度運用結果のモニタリング(不満・評価のブレ)
- Act(改善):評価項目の見直し、基準の微調整
特に導入1年目は、「完璧を目指すより、トライして改善する」姿勢が重要です。
評価者同士のすり合わせ会(評価者会議)や、社員アンケートによるフィードバックの収集も効果的です。
補足:中小企業でのよくあるつまずきポイント
| 課題 | よくある原因 | 解決策 |
|---|---|---|
| 評価者ごとのブレ | 評価基準の解釈が不統一 | 事前の評価者研修・定義の明文化 |
| 被評価者の不満 | 結果に処遇反映がない、面談が一方的 | 面談力強化・評価と給与の仕組みの接続 |
| 忙しくて制度が回らない | 実施スケジュールが形骸化 | 簡易シート・年2回制への絞り込みなど運用簡略化 |
第6章:まとめ

人事評価制度とは、単なる“成績表”ではありません。
人と組織を成長させるための仕組みであり、経営戦略と社員の努力をつなぐ橋渡しとなるものです。
本記事では以下の内容を中心に、人事評価制度の全体像と導入・運用のポイントを解説してきました:
- 評価制度の定義と役割、導入のメリット
- 評価の種類(業績・能力・情意、コンピテンシーなど)と特徴
- 中小企業でも導入できる制度構築のステップ
- 実務で使える評価指標や設計手法
- 制度を定着させるための運用・面談・改善サイクル
導入時に完璧を目指しすぎると、動き出せないまま頓挫してしまう企業が多くあります。
しかし、制度は導入してからの運用の中で改善していけるものです。
社員の声や現場の実情に耳を傾けながら、制度を「生きた仕組み」に育てていくことが成功の鍵です。
「制度導入=大企業の話」と思われがちですが、
むしろ人材の定着・育成が経営の根幹となる中小企業こそ、シンプルで実効性のある評価制度が武器になります。
無理のないスタートから、段階的に制度を育てていくことをおすすめします。
人事評価制度を導入するということは、社員を正しく見つめ、共に成長しようとする経営姿勢そのものです。
制度づくりをきっかけに、社員との対話が生まれ、組織が前向きに変わっていく――
そんな企業がこれからもっと増えていくことを願っています。
人事評価制度にお困りの方は、お気軽に村井にご相談ください。
➖ 資料請求 ➖
資料請求は下記バナーより。

➖ 問い合わせ ➖
新規事業、DX、人事制度などの経営課題に関するご相談は以下よりお受けしております。