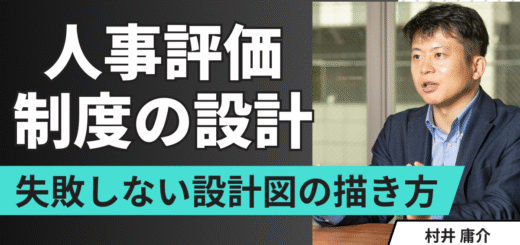人事評価フィードバックのコツ|部下を動かすのは技術か理念か

人事評価のフィードバック面談。
多くの管理職や経営者にとって、一年で最も気が重くなる仕事の一つかもしれません。
「部下のモチベーションを下げずに、どうやって厳しい評価を伝えればいいのか」
「面談が、ただ評価結果を伝えるだけの『作業』になってしまっている」
そんな悩みを抱えるあなたに、一つ、本質的な問いを投げかけたいと思います。
部下を本当に動かすのは、面談の「技術」でしょうか。
それとも、その根底にある会社の「理念」でしょうか。
多くの解説記事では、SBIモデルといった面談の「技術」が紹介されています。
もちろん、それらの技術は重要です。
しかし、技術だけに頼ったフィードバックは、かえって部下の心を冷めさせ、あなたの会社から「魂」を奪っていく危険性を孕んでいます。
この記事では、すぐに使える面談技術を網羅的に解説した上で、その技術を本当の意味で機能させる「理念」の重要性をお話しします。
この記事を読み終える頃には、あなたのフィードバックは単なる「作業」から、部下と会社の未来を共創する「未来への投資」へと変わっているはずです。

【村井 庸介(むらい ようすけ)】
大学卒業後は株式会社野村総合研究所に入社し通信業・製造業の経営コンサルティングに携わる。その後リクルート、グリー、日本IBMに転職。その中でグリー株式会社にて人事制度設計に携わった。
2015年に独立後は、社員30名のベンチャー企業から5,000名を超える大企業まで幅広く人事制度設計や導入伴走に携わる。顧客業種は製造業、サービス、IT企業が中心。経営理念・事業戦略から逆算した人事制度構築を得意とする。
そのフィードバック「答え合わせ」になっていませんか?

半期に一度、あるいは年に一度行われるフィードバック面談。
その光景を少しだけ、客観的に眺めてみましょう。
評価シートを前に、上司が部下へ評価結果を読み上げ、その根拠を説明する。
部下は、神妙な顔でそれに耳を傾ける。
まるで、テストの結果発表のような、過去の行動に対する「答え合わせ」の時間が、そこには流れていないでしょうか。
9割の管理職が陥る「通知表を渡すだけ」の面談
多くの企業で、人事評価のフィードバックは、残念ながら「通知表を渡すだけ」の儀式と化してしまっています。
上司は「評価者」として評価結果を伝え、部下は「被評価者」としてそれを受け取る。
そこには、一方的な情報の伝達があるだけで、未来に向けた創造的な対話は存在しません。
上司は「B評価という結果を、どう伝えれば角が立たないか」ということばかりに気を揉み、部下は「なぜA評価ではないのか」ということばかりに意識が向きます。
これでは、面談が終わった後に残るのは、上司の疲労感と、部下の不満や諦めだけです。
評価期間中の部下の頑張りを認め、次の成長に繋げるという、本来の目的はどこにも見当たりません。
もし、あなたの会社のフィードバックがこのような状態になっているとしたら、それは決して管理職個人の能力の問題ではないのです。
フィードバックに対する、根本的な考え方そのものに、メスを入れる必要があります。
部下の心を折る「正しいフィードバック」の罠
中には、研修などで学んだ「正しいフィードバック」を実践しようと努力している、熱心な管理職の方もいるでしょう。
具体的な事実(ファクト)に基づき、ロジカルに改善点を指摘する。
感情的にならず、あくまで客観的に、冷静に。
一見すると、これは非常に「正しい」アプローチのように思えます。
しかし、この「正しさ」こそが、時として部下の心を折る最も鋭いナイフになり得るのです。
人間は、論理だけで動く生き物ではありません。
どれだけ正論を突きつけられても、感情的に「受け入れたい」と思えなければ、心は固く閉ざされてしまいます。
「君のこの行動は、データ上、非効率だった」という完璧な正論は、部下に反論の余地を与えません。
しかし、それは同時に、部下から「自分なりに工夫したのに」「あの時は、そうせざるを得ない事情があったのに」といった、思考や言い分を奪うことにも繋がります。
正論で追い詰められた部下は、やがて思考を停止し、「どうせ何を言っても無駄だ。上司の言う通りにしておこう」という、指示待ちの状態に陥ってしまうのです。
「正しいフィードバック」は、時として部下から主体性を奪い、成長の機会を潰してしまう罠なのです。
目指すのは「未来の地図」を共に描く対話
では、私たちが目指すべきフィードバックとは、どのようなものでしょうか。
それは、過去の行動を評価する「答え合わせ」や「通知表渡し」ではありません。
部下と共に、未来のキャリアや成長への道筋を描く「未来の地図」を創り上げる、創造的な対話の時間です。
評価結果は、あくまで現在地を確認するためのスタートラインに過ぎません。
重要なのは、その現在地から、部下自身がどこへ向かいたいのか、そして会社としてどこへ向かってほしいのか、その二つのベクトルをすり合わせ、共に目的地へのルートを探していくプロセスです。
この対話を通じて、部下は「自分は会社から期待されている」「この会社でなら成長できる」と感じることができます。
上司は「評価者」ではなく、部下の成長を支援する「パートナー」としての役割を担うのです。
この「未来の地図」を共に描くという発想の転換こそが、フィードバックを意味あるものに変える、全ての始まりです。
【技術編】明日から使える!部下の納得感を高める対話のフレームワーク
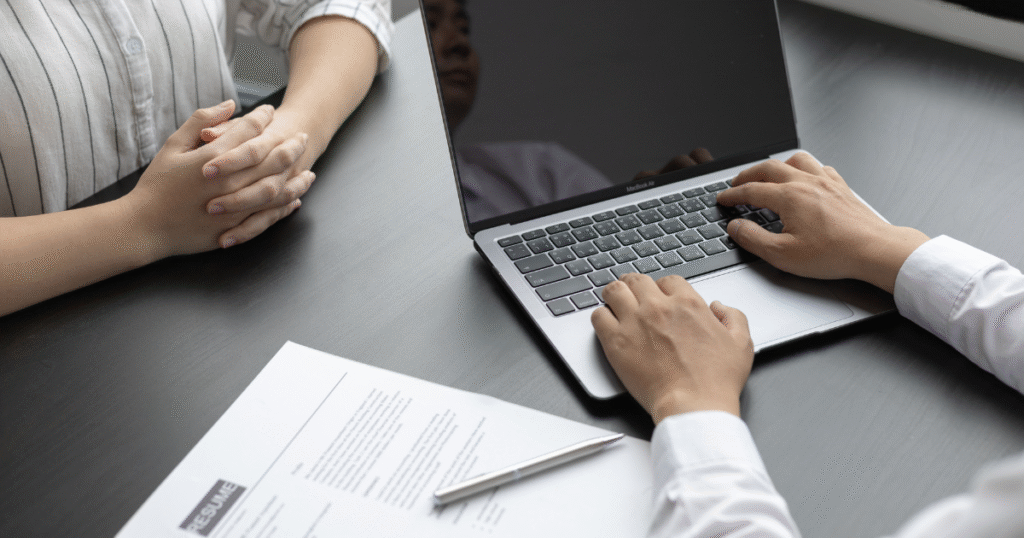
「未来の地図」を描くという目的を理解した上で、次はその対話を円滑に進めるための具体的な「技術」を学びましょう。
理念という魂も、それを伝えるための器がなければ機能しません。
ここでは、明日からすぐに使える、実践的なフレームワークと注意点を解説します。
準備が8割。評価の根拠となる「事実」を集める
質の高いフィードバックは、面談が始まる前、その準備段階で8割が決まると言っても過言ではありません。
ここで最も重要なのは、評価の根拠となる客観的な「事実(ファクト)」を、できるだけ具体的に集めておくことです。
「君は、もっと頑張れたはずだ」といった、抽象的で主観的な言葉は、部下の反発を招くだけです。
そうではなく、「〇月のAプロジェクトにおいて、君が作成した資料のおかげで、クライアントから高い評価を得ることができた」というような、具体的な成功体験。
あるいは、「B案件の報告が、締め切りより2日遅れたことが3回あった。その結果、チームの次の工程に遅れが生じた」といった、具体的な改善点。
これらの「事実」を、過去の1on1の議事録や、日々の業務記録、プロジェクトの成果物などから、丁寧に拾い集めておくのです。
この地道な準備が、あなたのフィードバックに圧倒的な説得力と納得感をもたらします。
そして何より、それは「私は、普段からあなたの仕事ぶりをしっかりと見ている」という、部下に対する最も強力なメッセージとなるのです。
面談の進め方5ステップと時間配分
面談当日は、場当たり的に進めるのではなく、明確なシナリオを持って臨むことが成功の鍵です。
一般的に、60分の面談であれば、以下の5ステップで進めるのが効果的です。
ステップ1:アイスブレイクと目的の共有(5分)。 まずは雑談などで場の空気を和ませ、心理的安全性を確保します。 そして、「今日は過去の評価を伝えるだけでなく、次の半期で君がもっと活躍するための作戦会議をしたい」というように、この場が未来志向であることを明確に伝えます。
ステップ2:部下による自己評価のヒアリング(15分)。 上司から話し始めるのではなく、まずは部下自身に、この期間の自己評価とその根拠を語ってもらいます。 これにより、部下の自己認識と、会社からの評価とのギャップを把握することができます。 上司は、決して途中で話を遮らず、傾聴に徹することが重要です。
ステップ3:評価結果と具体的な事実の伝達(15分)。 ここで初めて、会社からの評価結果を伝えます。 準備しておいた具体的な「事実」を元に、ポジティブな点、改善が必要な点を、客観的に伝えていきます。
ステップ4:未来の話と成長プランの策定(20分)。 面談の中で最も重要な時間です。 評価結果を踏まえ、「この強みを、次はどう活かしていこうか」「この課題を克服するために、どんなサポートが必要か」といった、未来に向けた対話を行います。 部下のキャリアプランと、会社の期待をすり合わせ、具体的な次のアクションプランを共に創り上げます。
ステップ5:まとめと激励(5分)。 最後に、話し合った内容を要約し、部下の今後の活躍への期待を、あなた自身の言葉で伝えて、面談を締めくくります。
心を動かす伝え方の技術「SBI+Rモデル」とは
具体的なフィードバックを伝える際には、「SBIモデル」というフレームワークが非常に有効です。
これは、S(Situation:状況)、B(Behavior:行動)、I(Impact:影響)の3つの要素で構成されます。
例えば、「〇〇の会議で(S)、君が積極的に意見を発信してくれた(B)、そのおかげで議論が活性化し、良い結論に繋がったよ(I)」というように伝えます。
これにより、単に「積極的で良かった」と褒めるよりも、はるかに具体的で、説得力のあるメッセージになります。
しかし、私たちは、このモデルに、著者独自の「+R(Role/Request)」を加えることを推奨します。
「+R」とは、その行動が、会社の理念や、その人に期待される「役割(Role)」とどう結びついているのかを伝え、未来に向けた「依頼(Request)」に繋げる、という考え方です。
先ほどの例に付け加えるなら、「その行動は、我が社の『挑戦を称える』という理念を体現するものだ(Role)。だから、次のプロジェクトでも、ぜひ君のその力をチームに貸してほしい(Request)」となります。
この「+R」を加えることで、フィードバックは単なる行動の評価から、会社の理念と部下の未来を接続する、極めて戦略的なコミュニケーションへと昇華するのです。
これだけは避けろ!信頼を失うNGフィードバックワースト3
最後に、どれだけ準備をしても、たった一言で部下との信頼関係を破壊しかねない、絶対NGなフィードバックを3つご紹介します。
ワースト1は、「人格や性格の否定」です。 「君は、慎重すぎる性格だからダメなんだ」といった発言は、改善の余地がない人格そのものを攻撃するものであり、パワハラと受け取られても仕方がありません。 あくまで、評価の対象は「行動」であり「人格」ではありません。
ワースト2は、「他者との比較」です。 「同期の〇〇君は、もう課長なのに、君は…」といった発言は、部下のプライドを深く傷つけ、劣等感を植え付けるだけで、何のプラスにもなりません。 比較対象は、常に「過去の本人」であるべきです。
ワースト3は、「過去の失敗の蒸し返し」です。 すでに解決し、反省もしているはずの、何年も前の失敗を、評価のたびに持ち出すのは、部下の心を深くえぐる行為です。 フィードバックは、あくまで今回の評価期間内の出来事に限定すべきです。 これらのNG言動は、百害あって一利なし。 絶対に避けましょう。
【理念編】技術の限界。なぜ「正論」だけでは部下は動かないのか

ここまで、フィードバックを成功させるための具体的な「技術」について解説してきました。
これらの技術を実践するだけでも、あなたのフィードバックの質は格段に向上するでしょう。
しかし、断言します。 技術だけでは、人の心は、本当の意味では動きません。
なぜなら、部下は、上司の「言葉」を聞いているのではなく、その言葉の裏にある「想い」や「価値観」を感じ取っているからです。
ここからは、技術の限界を超え、部下の魂を揺さぶるための「理念」についてお話しします。
フィードバックは「社長の代理業」であると心得る
管理職としてフィードバックを行うあなたに、まず心に刻んでほしいことがあります。
それは、フィードバックの場において、あなたは単なる「一人の上司」ではない、ということです。
その場に社長がいなくても、あなたは、社長の理念やビジョンを代弁する「社長の代理人」なのです。
これは、非常に重い責任を伴います。
あなたの発する一言一句が、部下にとっては「会社の公式見解」として受け止められます。
あなたが、会社の理念と全く異なる個人的な価値観でフィードバックを行えば、部下は「この会社は、言っていることとやっていることが違う」と、会社そのものへの不信感を抱くでしょう。
逆に、あなたが会社の理念を深く理解し、それを自分の言葉で語ることができれば、部下は、あなたを通じて、会社の目指す方向性を理解し、共感を深めることができます。
フィードバックとは、会社の理念が、経営陣から管理職へ、そして管理職から一般社員へと、正しく伝播していくための、最も重要な「神経」なのです。
あなたは、その神経の末端を担う、極めて重要な役割を担っているのです。
あなたが語るべきは評価結果ではなく会社の「北極星」
評価面談の場では、どうしても評価シートに書かれた評価結果や、個別の業務の達成度といった、ミクロな話に終始しがちです。
しかし、部下が本当に知りたいのは、それだけではありません。
彼らは、自分の仕事が、会社の大きな目的の中で、どのような意味を持っているのかを知りたいのです。
そして、自分が進むべきキャリアの方向性が、会社の進むべき方向性と合っているのかを、確認したいのです。
だからこそ、管理職であるあなたが語るべきは、目先の評価結果という「足元の石ころ」だけではなく、会社全体が目指す「北極星」なのです。
「今期の君の評価はBだった。しかし、それは問題ではない。我が社が目指しているのは、〇〇という社会を実現することだ。その壮大な旅の中で、君の〇〇という強みは、今後ますます重要になる。だから、次の半期は、その強みを活かして、〇〇という役割に挑戦してみないか」
このように、会社のビジョンという大きな文脈の中で、部下の働きを位置づけ、未来の役割を提示する。
そうすることで、部下は、日々の業務に追われる中で見失いがちだった「仕事の意義」を再発見し、より高い視座で、自らの仕事に取り組むことができるようになります。
部下の「成長ストーリー」と会社の物語を重ね合わせる
全ての人間は、自分自身の人生という「物語」の主人公です。
仕事は、その物語を構成する、非常に重要なチャプターです。
優れたフィードバックとは、部下個人の「成長したい」という私的な物語と、会社が「成長していく」という公的な物語を、見事に接続させる対話です。
上司は、部下のキャリアプランや、将来なりたい姿に、真摯に耳を傾けます。
そして、その部下の個人的な願いを実現するための道筋が、会社の事業計画やビジョンの中に、確かに存在することを示してあげるのです。
「君が将来、〇〇のプロフェッショナルになりたいという夢は、我が社がこれから注力していく〇〇事業の成長に不可欠だ。君の成長が、会社の成長に直結する。だから、会社としても、君の成長を全力でバックアップしたい」
このように、部下の成長と会社の成長が、win-winの関係にあることを、具体的な言葉で伝える。
そうすることで、部下は、自分の仕事が、単なる「やらされ仕事」ではなく、自己実現に繋がる「自分ごと」であると、心の底から感じることができます。
この「物語の接続」こそが、部下の内発的なモチベーションに火をつける、最も強力なスイッチなのです。
【実践編】会社の理念を「最強の武器」に変える対話術

理念の重要性は理解できた。
では、それをどのように、日々のフィードバックという「対話」に落とし込んでいけば良いのでしょうか。
ここでは、会社の理念を、あなたの言葉という「最強の武器」に変えるための、具体的な対話術を解説します。
「社長の言葉」を「自分の物語」として語る
会社の理念やバリューは、多くの場合、社長の言葉として、抽象的に語られます。
「挑戦」「顧客第一」「チームワーク」。
これらの言葉を、そのままオウム返しのように部下に伝えても、その心には響きません。
重要なのは、それらの「社長の言葉」を、あなた自身の経験というフィルターを通して、「自分の物語」として語ることです。
例えば、会社のバリューに「挑戦」という言葉があるならば、あなたが過去に、その「挑戦」という価値観に助けられた経験や、逆に挑戦せずに後悔した失敗談を、具体的なエピソードとして語るのです。
「昔、俺も君と同じように、新しいプロジェクトを任されて、失敗を恐れて一歩が踏み出せない時期があった。でも、その時、社長が『失敗してもいいから、思い切りやってみろ』と背中を押してくれた。その経験が、今の俺の原点になっているんだ」
このように、あなた自身の血の通った物語として語られることで、会社の理念は、初めてリアリティと熱量を持ち、部下の心に深く刻まれるのです。
ネガティブフィードバックこそ理念を伝える絶好の機会
多くの管理職が、ネガティブなフィードバックを伝えることを苦手としています。
しかし、実はこの「厳しい指摘」をしなければならない場面こそ、会社の理念を伝える、またとないチャンスなのです。
なぜなら、会社の理念とは、言い換えれば「我が社における、行動の良し悪しを判断する『物差し』」だからです。
部下の行動を改善してほしい時、それをあなた個人の感情や、主観的な意見として伝えてはいけません。
「俺は、君のそういうやり方は好きじゃない」では、ただの個人的な批判です。
そうではなく、会社の理念という、誰もが納得せざるを得ない「公式な物差し」を使って、指摘するのです。
「君のその行動は、我が社が最も大切にしている『顧客第一』という理念に照らし合わせた時、少し違う方向に進んでいるように思う。なぜなら…」
このように、会社の理念を判断基準として示すことで、あなたのフィードバックは、個人的な感情論から、組織としての一貫したメッセージへと変わります。
部下も「上司に嫌われている」のではなく、「会社の価値観と、自分の行動がズレていたのだ」と、客観的に事実を受け止め、前向きな改善に繋げやすくなるのです。
まとめ
この記事の冒頭で、一つの問いを投げかけました。
「部下を動かすのは、技術か、理念か」
ここまで読み進めてくださったあなたなら、もうその答えは、お分かりのはずです。
部下を本当に動かすのは、その両輪です。
もっと言えば、「理念を伝えるための技術」であり、「技術の根底に流れる理念」です。
どちらか一方だけでは、車は前に進みません。
フィードバックのフレームワークや、面談の進め方といった「技術」は、あなたの想いを、部下に誤解なく、正確に伝えるための、非常に重要な道具です。
しかし、その道具を使って、何を伝えたいのか。
その根底に、会社の未来を良くしたい、部下に成長してほしいという、熱い「理念」がなければ、どんなに優れた技術も、ただの空虚なテクニックに成り下がります。
あなたのフィードバックは、単なる評価の伝達ではありません。
それは、社長の想いを、会社の理念を、あなた自身の物語を通して、部下の未来に接続させる、極めて創造的で、尊い仕事です。
あなたの言葉が、一人の部下の成長ストーリーを輝かせ、それがやがて、会社全体の文化を創り上げていくのです。
明日からのフィードバックが、あなたの会社にとって、より良い未来を創るための、希望に満ちた対話の場となることを、心から願っています。
人事評価制度にお困りの方は、お気軽に村井にご相談ください。
➖ 資料請求 ➖
資料請求は下記バナーより。

➖ 問い合わせ ➖
新規事業、DX、人事制度などの経営課題に関するご相談は以下よりお受けしております。