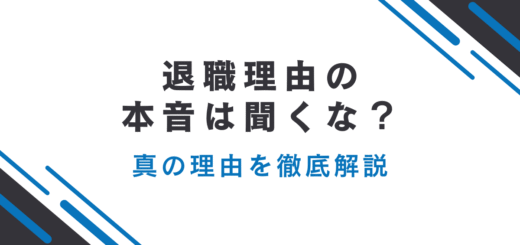採用を強化する前に、まず人事制度を見直すことが大事な3つの理由
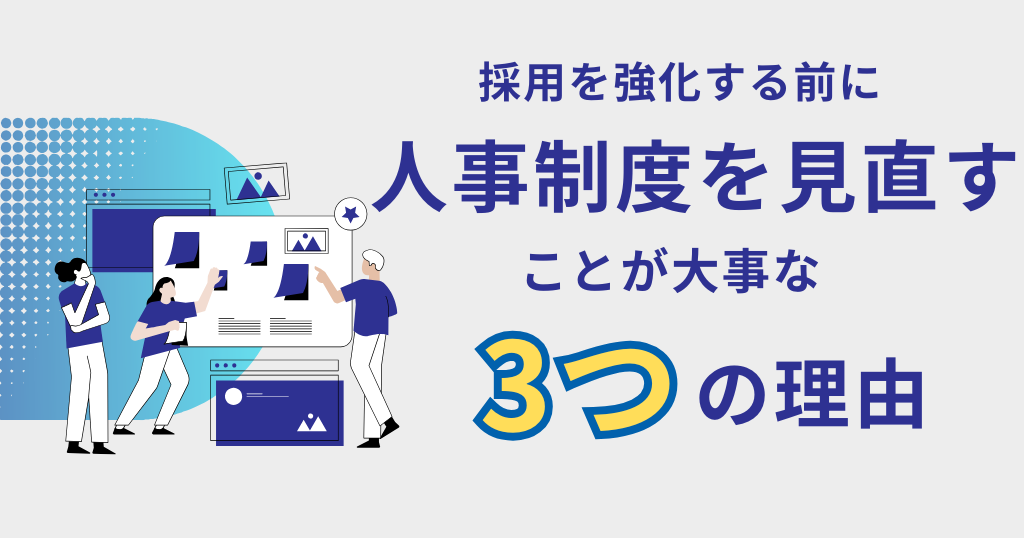
このコラムではクラフトビール会社の新規事業で年商1億円を達成してから1.5倍2倍へと成長させてきた村井が、その実践的なノウハウを紹介しています。
またコンサルティング会社として新規事業の立ち上げをサポートした、または大手の会社とのお仕事から培ってきた経験をお届けしています。
今回は採用を強化する前に人事制度を見直すことが大事な理由について解説していきます。

【村井 庸介(むらい ようすけ)】
大学卒業後は株式会社野村総合研究所に入社し通信業・製造業の経営コンサルティングに携わる。その後リクルート、グリー、日本IBMに転職。その中でグリー株式会社にて人事制度設計に携わった。
2015年に独立後は、社員30名のベンチャー企業から5,000名を超える大企業まで幅広く人事制度設計や導入伴走に携わる。顧客業種は製造業、サービス、IT企業が中心。経営理念・事業戦略から逆算した人事制度構築を得意とする。
すべての企業にとって、人材の採用と定着は重要な経営課題です。
しかし、採用市場の厳しさは増す一方であり、優秀な人材の確保に苦心する企業が後を絶ちません。
そんな時、採用活動に力を入れる前に、まずは自社の人事制度を見直すことが重要です。
本稿では、人事制度を見直すことで採用・定着の課題をどのように解決できるのか、具体的な方法と事例を交えながら解説します。
いま努力の延長では、採用も定着も改善しない3つの理由
「人が足りない」
「優秀な人材が集まらない」
「社員がすぐ辞めてしまう」
多くの中小企業の経営において社長から漏れる言葉です。
あなたの会社にも当てはまっているでしょうか。
中小企業が抱える「採用」と「定着」の課題は、どの企業も直面する重要な問題です。
「もっと人材が集まれば良いのに」と感じることが多いかもしれません。
しかし、採用予算を増やしたり、給与アップしたりしたとしても状況は改善されず、むしろお金を溶かしたと感じたご経験を持つ経営者の方も多いのではないでしょうか。
採用と定着の改善が思うように進まない根本的な理由は、以下の3点に集約されます。
・理由①:求職者は「あなたの会社」を知らない、興味をもっていない
・理由②:求職者に会社の魅力が伝わりづらい
・理由③:社員が「会社に在籍し続ける」理由がない

それぞれの理由について、詳しく見ていきましょう。
まず、理由①「求職者は「あなたの会社」を知らない、興味をもっていない」についてです。
多くの中小企業経営者は「採用に力を入れている」と考えていますが、実際には求職者の目に企業の存在自体が認知されていない場合がほとんどです。
求人広告を出稿しても、求職者があなたの会社の名前を検索もしなければ、その求人一覧の中であなたの会社の求人に目を留めることはありません。
有名企業でもない限り、求職者は企業名を見ただけでは、どのような会社なのか想像することもできません。
また、各社が自社への応募を増やそうと求人キャッチコピーに力を入れている中、自社の求人を見てもらう段階でも様々なハードルがあるのです。このように、採用市場における「企業の不可視性」が、採用の最初の大きな壁となっています。
次に、理由②の「求職者に会社の魅力が伝わりづらい」点です。
仮に求職者があなたの会社の存在を知ったとしても、その企業の魅力を適切に理解してもらうことは容易ではありません。
多くの企業の求人情報は、業務内容や求める人材要件は書かれていても、なぜその仕事が魅力的なのか、どのような成長機会があるのか、といった本質的な求職者への価値提案が欠けています。
また、給与や福利厚生といった条件面の記載だけでは、その企業で働くことの本当の魅力は伝わりません。
求職者は、その企業で働くことで自分がどのように成長できるのか、キャリアをどのように築いていけるのかを知りたいと考えています。
加えて、多くの会社では長年使い続けている人事制度であったり、士業の先生などに作成頂いた標準的な人事制度であったりを活用していることが多いため、評価や給与面で求職者を魅了する仕掛けが、今のままではできないというのもあります。
そして最も重要な理由③として、「社員が会社に在籍し続ける理由がない」という根本的な課題があります。
この課題を解決しないと、仮に採用数を増やしたとしても、穴のあいたバケツと同じで、単に待遇面だけの問題ではありません。
社員が長期的なキャリアビジョンを描けない、自身の成長を実感できない、会社の将来性に確信が持てない、といった本質的な問題が隠れています。
多くの企業では、日々の業務をこなすことに重点が置かれ、社員一人ひとりの成長やキャリア形成について、十分な対話や支援が行われていません。
その結果、社員は自身の将来に不安を感じ、より良い機会を求めて転職を選択することになるのです。
これらの課題は、従来型の採用活動の強化や、単純な待遇改善では解決できません。
なぜなら、これらは表面的な症状への対処に過ぎないからです。
本質的な解決には、企業の存在価値や魅力を明確化し、それを効果的に伝えるための仕組みづくり、そして何より、社員が長期的に活躍できる環境の整備が必要となります。
つまり、今必要なのは「努力の方向性を変える」ことです。
採用予算を増やしたり、給与水準を引き上げたりする前に、まずは変えるべきことがあるということです。それが人事制度になります。
「当社らしい」人事制度を構築している会社が得ている3つの効果

人事制度は、単なる従業員のルールブックではありません。
経営戦略を実現し、企業の持続的な成長を支える重要な経営ツールとして機能します。
自社の理念や価値観が反映された「自社らしい」人事制度を構築できている企業では、以下の3つの効果が表れています。
1:採用力の大幅な向上
2:社員の定着率と満足度の向上
3:「組織の質」の向上
それぞれ具体的に解説していきたいと思います。
第一の「採用力の大幅な向上」について、適切な人事制度が整っている会社では、採用活動が効果的に進みます。
なぜなら、自社らしい人事制度が構築されている会社は、自社の「ビジョン」や「ビジョンを実現しているときの組織の姿」を具体的に示すことができているからです。
企業のビジョンや成長戦略が人事制度を通じて明確に表現されることで、その実現に貢献したいと考える人材が自然と集まってくるようになります。
特に、成長意欲の高い優秀な人材は、自身のキャリアパスを具体的にイメージできる企業を選ぶ傾向があります。人事制度が整備されている企業は、そうした人材にとって魅力的な選択肢となるのです。
第二に、「社員の定着率と満足度の向上」について、これは単に社員が会社に留まるということではありません。
会社の理念や戦略にもとづく公平な評価基準と適切な報酬体系が整備されることで、社員は長期的な貢献意欲を持ちやすくなります。
特に重要なのは、評価基準の透明性と報酬の納得性です。自社らしい人事制度を持つ企業では、何がどのように評価され、どのような成果に対してどのような報酬が得られるのかが明確です。
この「透明性」と「納得性」により、社員は自身の将来を具体的に描くことができ、より主体的にキャリア形成に取り組むようになります。
また、人事制度がしっかりと機能すると業績の達成に向けて社員同士が連携とるようになり、コミュニケーションも自然と活性化します。結果、会社全体の雰囲気が良くなり、社員自身が周囲に入社を勧めるようになります。
つまり、リファーラル採用の土壌も自然と形成されていくのです。
そして第三に、最も重要な効果が「組織の質」の向上です。
質が高まる過程において、組織には健全な「デトックス作用」が働きます。これは、企業の価値観や方向性に合わない人材が自然と離れ、企業にフィットした人材が定着するという現象です。
注目すべきは、このプロセスが強制的なものではなく、自然な流れとして起こる点です。
明確な評価基準と期待される行動が示されることで、社員は自身と企業との適合性を自ら判断できるようになります。
その結果、企業文化に合わない人材は自然と他の機会を求めて離れます。そして、自社のビジョンや価値観に共感し、その実現に貢献したいと考える人材が残ることになります。
このデトックス作用は、一見すると優秀な人材の流出や組織力の低下のように見えるかもしれません。
しかし実際には、企業文化を強化し、組織の成長力を高める重要な機能を果たしています。なぜなら、価値観を共有する人材が集まることで、意思決定のスピードが上がり、判断がぶれず、戦略の実行力も高まるからです
実際に私が手掛けた上場準備中の企業(IT業界)の人事制度の見直しでは、古くから在籍していた社員が管理職に長年滞在していてポジションがあかないことがありました。
その影響により、複数名の優秀な若手の離職などに繋がっていました。
しかし、その管理職に対して合理的にポジションを変える合理的な説明ができなかったことや、若手を抜擢する制度がなかったため、その状態が放置されていた状態でありました。
そこで、私が人事制度の見直しに関わるようになったときに、この企業においてまず着手したのは、各等級の役割定義を明確に言語化したことでした。
それに加え、そして若手を報酬・ポジションの両面から抜擢昇格できる評価制度、且つ会社の人件費が肥大化しないように、昇給にメリハリをつけた報酬制度に変更しました。
その結果、管理職の方は他社に転職すると共に、入社5年目以内の若手が部長になったことで、営業戦略の実行力も上がり売上や営業利益が120%超の予算達成をしました。
効果はそれだけではありません。
活躍する先輩を見た若手が以前よりも頑張るようになり、離職率が低下、さらには新卒及び中途採用においても大手企業や外資系など採用競合企業とられていた人材層の採用もできるようになりました。
このように、人事制度を見直したことで、まずデトックス作用による組織の質の変化、そして離職防止の意味での量の維持、さらには優秀な人材の採用の成功による質・量の向上と、組織における採用や定着の課題に繋がったのです。
ここまで読んでいただけたあなたであれば、「企業の採用、定着の鍵は人事制度」にあることは、イメージ頂けたかと思います。すると、次の疑問が出てくるかと思います。
「どうやって、自社にあった人事制度を構築すれば良いのか?」
そこで、自社にあった人事制度の構築方法の全体像をお伝えして締めたいと思います。
人事制度の検討は、検討の順番が肝

人事制度というと、一見専門性が高く見えてしまうため、多くの企業ではその構築を外部の専門家に全面的に委託してしまいがちです。大
企業であれば人事部に、中小企業であれば社労士の先生に一任してしまい、経営陣の関与が限定的になってしまうケースが少なくありません。
しかし、これは人事制度構築における致命的な誤りといえます。
なぜなら、人事制度は単なる規則の集合体ではなく、企業理念や経営戦略を実現するための重要なツールだからです。
特に強い組織づくりを実現している企業ほど、人事制度と企業理念・戦略が密接に連動していることが分かります。
この連動の重要性を理解するために、プロスポーツチームの例を見てみましょう。
優れた成果を出しているプロスポーツチームでは、単に優秀な選手を集めるだけではありません。必ず監督の方針に沿って、どのような選手が評価され、どのような行動が求められるのかが明確に定められています。
そのため、監督が代わればチームの色も大きく変わることがあります。これは、方針と評価基準が密接に結びついているからこそ起こる現象です。
企業経営においては、監督のように経営者が頻繁に交代することは稀ですが、強い組織づくりに求められる本質は同じです。
企業理念、経営戦略、そして人事制度、この3つが有機的に連携していてこそ、組織は真の力を発揮できるのです。
では、具体的にどのような順序で人事制度を検討していけばよいのでしょうか。重要なのは、以下の3ステップを順序立てて進めることです。
- 経営者自身による「企業理念」の明確化
- 企業理念を実現するための「経営戦略」の策定
- これらを実現するための「人事制度」の設計
このように、人事制度は検討の最後の段階で具体化されるべきものです。
しかし現実には、この順序が逆転していることが少なくありません。
人事制度の細部の設計から始めてしまい、後から理念や戦略との整合性を図ろうとする。あるいは、他社の制度を参考に作ってしまい、自社の独自性が失われてしまう。
こうした本末転倒な進め方が、人事制度が機能しない大きな原因となっています。
正しい順序で検討された人事制度は、社員の行動指針としても機能します。
企業理念と戦略が人事制度を通じて具体的な行動レベルまで落とし込まれることで、社員は自分の役割や目標を明確に理解できます。その結果、戦略の適切な実行や改善が促進され、年度予算や中期経営計画の目標達成にもつながっていきます。
このように、人事制度の検討において最も重要なのは、その「順序」なのです。
理念、戦略、制度の順で検討を進めることで、はじめて真に機能する人事制度が構築できるのです。
今回は「採用・定着の改善の鍵は人事制度」にあることを繰り返しお伝えしました。
そして、制度設計の肝は検討の順番であることをお伝えしました。
つまり、いきなり制度の細部を検討するのではなく、まず経営者の想いや事業戦略を深く理解し、それを制度に落とし込んでいく必要があります。
そのプロセスで大事になるのが、社長(経営者)の本音をしっかり解きほぐすということです。企業理念・戦略との連動の重要性はお伝えした通りであり、これを担うのはまさに社長であるからです。つまり、人事制度の起点は社長の想いから始まるのです。
問い合わせ
新規事業、DX、人事制度などの経営課題に関するご相談は以下よりお受けしております。