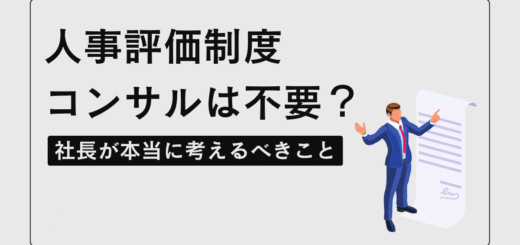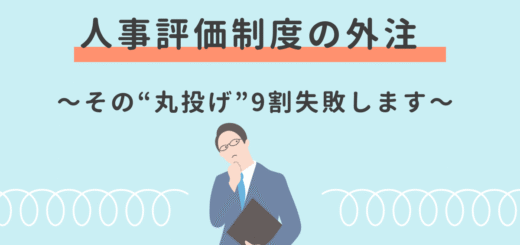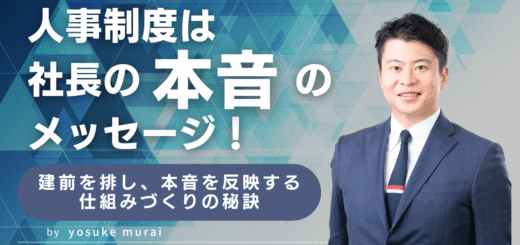人事評価制度のメリット・デメリット|社長の法律、ありますか?
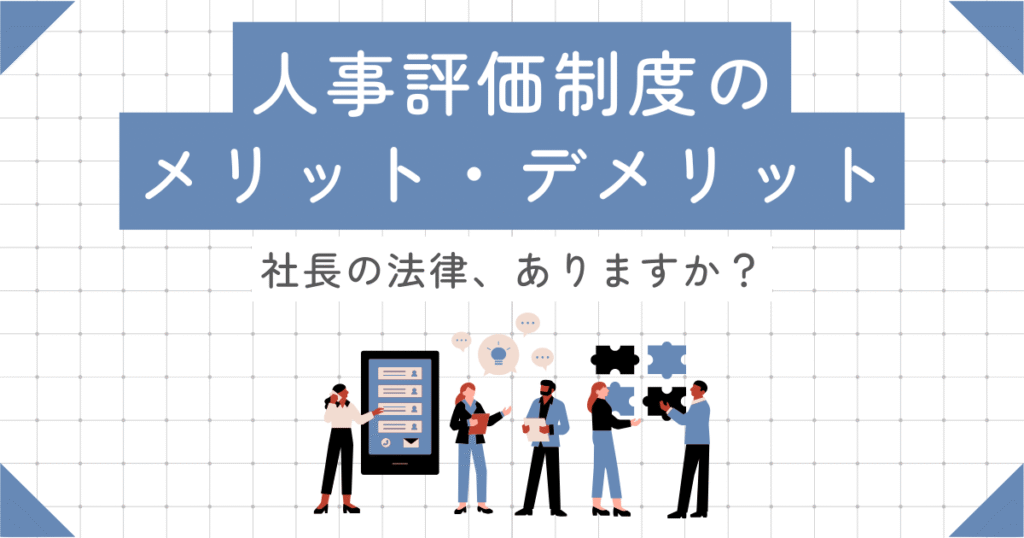
人事評価制度の導入を検討する時、多くの経営者が「メリット・デメリット」を考えます。
もちろん、その光と影を知ることは重要です。
しかし、もしあなたが知識だけで制度導入の判断をしようとしているなら、その時間は無駄になるかもしれません。
なぜなら、人事評価制度がもたらすメリットとデメリットは、制度そのものにあるのではなく、それを導入するあなたの会社に「法律」があるかどうかで、そのすべてが決まってしまうからです。
この記事では、巷で語られるメリット・デメリットを網羅的に解説した上で、なぜ多くの会社でメリットが絵に描いた餅で終わり、デメリットばかりが現実になるのか、その根本原因を解き明かします。
ぜひ、最後までお読みください。

【村井 庸介(むらい ようすけ)】
大学卒業後は株式会社野村総合研究所に入社し通信業・製造業の経営コンサルティングに携わる。その後リクルート、グリー、日本IBMに転職。その中でグリー株式会社にて人事制度設計に携わった。
2015年に独立後は、社員30名のベンチャー企業から5,000名を超える大企業まで幅広く人事制度設計や導入伴走に携わる。顧客業種は製造業、サービス、IT企業が中心。経営理念・事業戦略から逆算した人事制度構築を得意とする。
人事評価制度を考える前に

本格的な議論に入る前に、まず一つの、しかし最も重要な問いを投げかけたいと思います。
あなたの会社には、社員の働き方を正しく導くための、明確な「法律」がありますか?
この問いの意味が、これから明らかになります。
なぜメリットが消えデメリットだけが残るのか
多くの経営者が、人事評価制度を導入すれば「社員のモチベーションが上がる」「公平な評価ができる」といった輝かしいメリットを享受できると期待します。
しかし現実はどうでしょう。
導入後に聞こえてくるのは、「評価に納得できない」という社員の不満の声。
増大する評価業務に疲弊する管理職の嘆き。
そして、期待していた業績向上には全く繋がらないという、厳しい現実です。
なぜ、期待したメリットは泡のように消え、予期せぬデメリットばかりが大きく膨らんでしまうのでしょうか。
その理由は、制度設計の巧拙にあるのではありません。
もっと根深い、制度導入の「前提条件」が抜け落ちているからです。
答えは「誰をえこひいきするか」という法律の不在
結論から申し上げます。
人事評価制度が失敗するたった一つの理由は、あなたの会社に「誰を、どのような行動をした人材を、えこひいきするのか」という明確な「法律」が存在しないからです。
「えこひいき」というと、不公平な響きに聞こえるかもしれません。
しかし、優れた会社とは、会社が大切にする価値観を体現した人材を、正しく「えこひいき」できる会社のことです。
その「えこひいきの基準」こそが、会社の理念であり、ビジョンに他なりません。
この「法律」がないまま制度という「仕組み」だけを導入することは、六法全書がないまま裁判所を建てるようなものです。
どの行動が正しく、どの行動が間違っているのかを裁く基準がないため、現場は混乱し、不信感が渦巻くだけなのです。
会社の「憲法」を創る設計図
もし、あなたの心に「自社の法律は、まだ言語化できていないかもしれない」という思いが少しでもよぎったなら、どうかご安心ください。
この記事は、まさにそのためにあります。
一般的なメリット・デメリットの解説に留まらず、あなたの手で、あなたの会社の理念という名の「憲法」を創り上げるための、具体的な思考のプロセスと実践的なワークを提供します。
この記事を読み終える頃には、あなたはもう、他社の事例や一般的なノウハウに惑わされることはありません。
自社の進むべき道を照らす、確固たる「法律」を手にしているはずです。
人事評価制度のメリットとデメリット

まずは、あなたの現在地を確認するために、一般的に語られる人事評価制度の光と影、メリットとデメリットを網羅的に見ていきましょう。
これらは、あなたの会社がこれから手にするかもしれない「理想」と、直面するかもしれない「現実」です。
経営者が夢見る「メリット」
人事評価制度が理想的に機能した時、会社は計り知れないほどの恩恵を受けます。
最大のメリットは、会社が目指す方向と、社員一人ひとりの目標が、明確に連動することです。
会社が「何をすれば評価されるのか」という基準を明確に示すことで、社員は日々の業務の中で、迷うことなく力を発揮できます。
これにより、組織全体の生産性は飛躍的に向上するでしょう。
また、評価基準が明確になることで、評価の「公平性」と「透明性」が高まります。
上司の個人的な感情ではなく、定められたルールに基づいて評価されるという安心感が、社員の会社に対する信頼を育みます。
これは、エンゲージメントの向上や、優秀な人材の離職防止に絶大な効果を発揮します。
さらに、個々の社員の強みや弱みが可視化されるため、戦略的な人材育成や、適材適所の人員配置が可能になります。
社員一人ひとりが、自らのキャリアパスを描きやすくなることも、大きなメリットと言えるでしょう。
9割の会社が直面する「デメリット」
しかし、これらの輝かしいメリットの裏には、導入した企業の9割が直面するとも言われる、深刻なデメリットが潜んでいます。
最も顕著なデメリットは、評価者である管理職の負担が、爆発的に増大することです.
部下一人ひとりの目標設定から、期中の面談、評価シートの作成、フィードバック面談まで、その業務は多岐にわたります。
本来のマネジメント業務が疎かになるほど、評価業務に時間を取られてしまうケースも少なくありません。
また、どれだけ精緻な制度を作っても、評価に対する社員の不満をゼロにすることは不可能です。
むしろ、評価が給与や賞与に直結するからこそ、「なぜ同期より自分の評価が低いのか」といった、社員間の無用な競争や対立を生み出す温床にもなり得ます。
結果として、チームワークが阻害され、組織の一体感が失われる危険性もあります。
言うまでもなく、制度の導入と運用には、少なくないコストと時間がかかります。
これらのデメリットを乗り越えてでも、導入する価値があるのか。
全ての経営者が、この厳しい問いに直面するのです。
自社にとって「毒」か「薬」か
ここまで見てきたように、人事評価制度は、会社に素晴らしい効果をもたらす「薬」になる可能性を秘めている一方で、組織を蝕む「毒」にもなり得る、諸刃の剣です。
では、あなたの会社にとって、それは「毒」になるのでしょうか、それとも「薬」になるのでしょうか。
その運命を分けるたった一つの判断基準こそが、冒頭から繰り返しお伝えしている「社長の法律」の有無なのです。
次の章で、その理由を詳しく見ていきましょう。
なぜ「社長の法律」なき制度は組織を蝕む「毒」になるのか
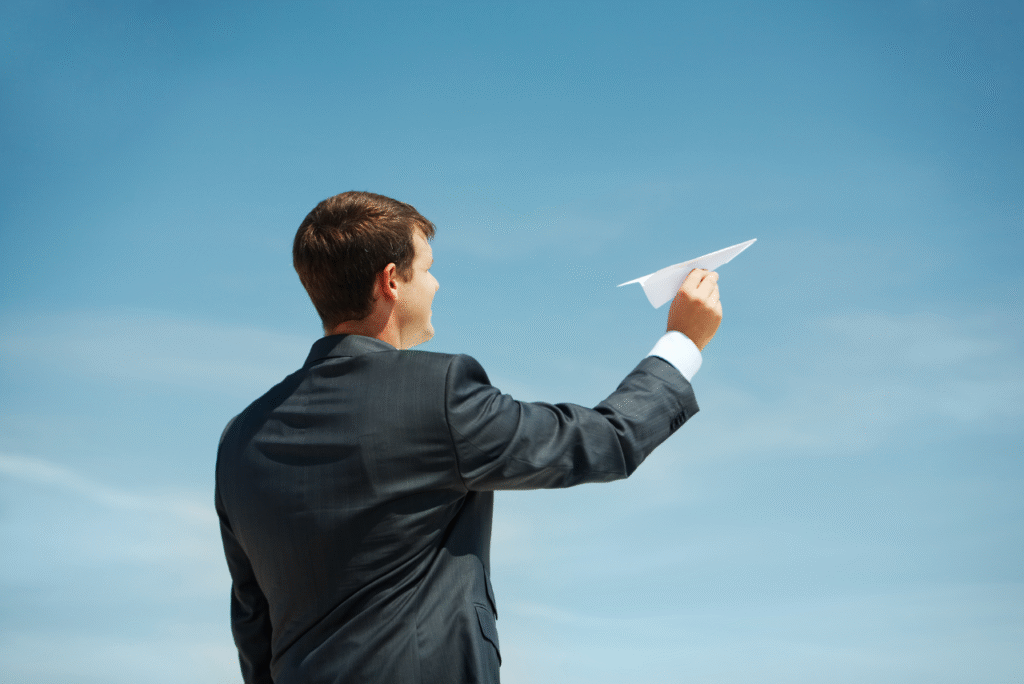
人事評価制度の導入が失敗する根本原因は、「社長の法律」がないまま、仕組みという名の「毒」を組織に注入してしまうことにあります。
なぜ、法律がないだけで、輝かしいメリットは消え去り、制度は組織を蝕む猛毒へと変貌してしまうのでしょうか。
メリットとは「良い法律」がもたらす副産物
そもそも、先ほど挙げた「公平性の担保」や「モチベーション向上」といったメリットは、制度そのものが自動的に生み出すものではありません。
それらはすべて、明確な「法律」が存在して初めて得られる「副産物」に過ぎないのです。
例えば、「公平性」というメリット。
これは、「評価項目が公平である」ということではありません。
社長が定めた「我が社は、挑戦した者を評価する」という法律が全社員に共有されていて、その法律に基づいて評価が行われるからこそ、「公平だ」という納得感が生まれるのです。
法律がなければ、何を基準に評価しても「不公平」になります。
「モチベーション向上」も同様です。
社員のやる気を引き出すのは、評価制度という仕組み自体ではありません。
「この会社は、自分が信じる価値観(=会社の法律)と同じ方向を向いている」「ここで頑張れば、自分の目指す未来に近づける」と、社員が感じられるからこそ、内発的なモチベーションが湧き上がってくるのです。
メリットとは、社長の理念という名の「法律」が、組織の隅々にまで浸透した結果、自然と生まれてくる果実なのです。
デメリットとは「法律の不在」
一方で、デメリットのほとんどは、「法律の不在」そのものが直接的な原因となって発生します。
考えてみてください。
評価者の負担が増大するのはなぜでしょうか。
それは、評価の基準となる「法律」がないため、管理職が「自分個人の価値観で、部下の人生を左右する重い判断を下さなければならない」という、過剰な精神的負担を強いられるからです。
社員から不満が噴出するのはなぜでしょうか。
それは、判断の拠り所となる「法律」がないため、評価結果が全て「上司の好き嫌い」に見えてしまうからです。
制度が形骸化するのはなぜでしょうか。
それは、そもそもその制度を通じて達成したい目的、つまり「法律」の存在意義が、誰にも理解されていないからです。
このように、デメリットとは、制度の欠陥なのではなく、「法律の不在」という病が引き起こす、必然的な症状なのです。
この根本原因を治療しない限り、どんなに高価な薬(=最新の評価制度)を投与しても、病状は悪化の一途をたどるでしょう。
【実践ワーク】会社の「法律」を制定する3ステップ

では、どうすれば、あなたの会社の「法律」を制定できるのでしょうか。
それは、コンサルタントに作ってもらうものでも、他社から借りてくるものでもありません。
社長である、あなた自身の心の中から、見つけ出すものです。
ここでは、そのための具体的な3ステップの実践ワークをご紹介します。
STEP1:「社長のえこひいき」を言語化する魔法の質問リスト
まず、あなたの「本音」と向き合います。
ペンと紙を用意し、以下の質問に、思いつくままに答えを書き出してみてください。
・質問1:これまでの経営で、どんな成果を出した社員を、最も褒め称えたいと思いましたか?
・質問2:逆に、どんな行動を取る社員を見ると、許せない気持ちになりますか?
・質問3:業績が絶好調な時、その利益を、どんな働きをしたチームに最も多く分配したいですか?
・質問4:会社が経営危機に陥った時、誰一人リストラせずに済むなら、誰に給与を一番多く払い続けたいですか?
・質問5:あなたが引退する日、社員から「社長は〇〇を大切にする人でした」と言われたいですか?
綺麗事や建前は一切不要です。
あなたの心の奥底にある、生々しい「えこひいき」の基準を、正直に言語化することが、全ての始まりです。
STEP2:会社の「北極星」となる価値観を決める
STEP1で書き出した、あなたの「本音」を眺めてみてください。
そこには、いくつかの共通するキーワードや、価値観が見えてくるはずです。
「挑戦」「誠実」「チームワーク」「顧客貢献」「スピード」。
様々な言葉が浮かんでくるでしょう。
次のステップは、その中から、あなたの会社が、どんな困難な状況にあっても、絶対に譲れない「たった一つの価値観」を選び抜くことです。
これは、会社の進むべき道を照らす、揺るぎない「北極星」となります。
例えば、リクルート社における「お前はどうしたい?」という言葉のように、シンプルで、力強く、全ての行動の判断基準となるような、あなた自身の言葉を見つけ出すのです。
この「北極星」こそが、あなたの会社の「憲法」の根幹をなす、最も重要な価値観となります。
STEP3:法律を等級・評価・報酬の三権分立へ
最後に、定めた「北極星」という憲法を、具体的な人事制度のルール、つまり「法律」の条文に落とし込んでいきます。
人事制度は、大きく分けて「等級(役割)」「評価(基準)」「報酬(分配)」という、三つの要素で成り立っています。
これは、国家における「立法・行政・司法」の三権分立のようなものです。
例えば、あなたの会社の「北極星」が「挑戦」だと決まったなら、
・等級制度(役割):より高い等級に上がるための要件に、「前例のない課題に挑戦した経験」を加える。
・評価制度(基準):評価項目の中に「挑戦度」という項目を設け、たとえ失敗しても、そのプロセスを評価する。
・報酬制度(分配):賞与の一部に、最も果敢な挑戦をしたチームや個人を表彰する「チャレンジ賞」を設ける。
このように、憲法である「北極星」が、全ての法律(等級・評価・報酬)の土台となり、一貫性を持って運用される仕組みを創り上げるのです。
まとめ

人事評価制度のメリットとデメリット。
その議論の本質は、制度の良し悪しを比較検討することではありません。
それは、社長であるあなた自身が、自社の「法律」、つまり「理念」と、どれだけ真剣に向き合えるか、という一点に尽きます。
明確な法律なき制度は、組織を蝕む「毒」となります。
しかし、社長の熱い想いが込められた法律に基づく制度は、社員を成長させ、会社を飛躍させる「最高の薬」となり得るのです。
この記事を読み終えた今、改めて問います。
社長、あなたの会社に「法律」はありますか?
もし、まだその答えが明確でなくとも、何も心配することはありません。
あなたの会社の「法整備」は、今、この瞬間から、始めることができますよ。
人事評価制度にお困りの方は、お気軽に村井にご相談ください。
➖ 資料請求 ➖
資料請求は下記バナーより。

➖ 問い合わせ ➖
新規事業、DX、人事制度などの経営課題に関するご相談は以下よりお受けしております。