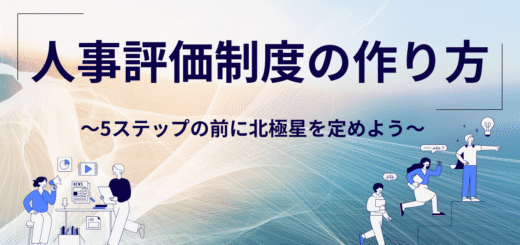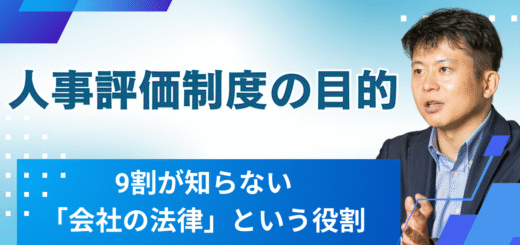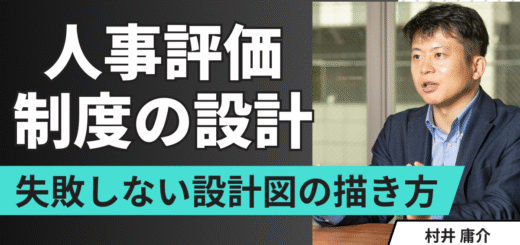会社の業績を伸ばす評価制度 ~成果を引き出す評価の仕組みと運用~
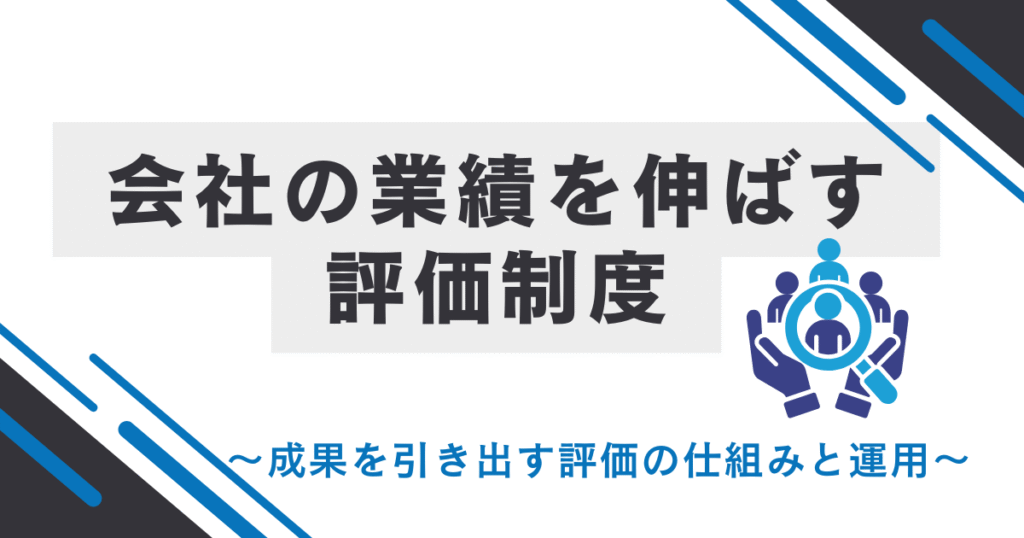
このコラムではクラフトビール会社の新規事業で年商1億円を達成してから1.5倍2倍へと成長させてきた村井が、その実践的なノウハウを紹介しています。
またコンサルティング会社として新規事業の立ち上げをサポートした、または大手の会社とのお仕事から培ってきた経験をお届けしています。
今回は、その中でも特に成果や行動に直結しやすい「評価制度」に焦点を当てます。
評価制度は単に査定を下す仕掛けではなく、会社の価値観と戦略を社員一人ひとりへ波及させ、業績を伸ばす原動力にもなる極めて重要なテーマです。

【村井 庸介(むらい ようすけ)】
大学卒業後は株式会社野村総合研究所に入社し通信業・製造業の経営コンサルティングに携わる。その後リクルート、グリー、日本IBMに転職。その中でグリー株式会社にて人事制度設計に携わった。
2015年に独立後は、社員30名のベンチャー企業から5,000名を超える大企業まで幅広く人事制度設計や導入伴走に携わる。顧客業種は製造業、サービス、IT企業が中心。経営理念・事業戦略から逆算した人事制度構築を得意とする。
評価制度が企業を動かす

これまでの記事では、人事制度が「採用・定着」に及ぼす大きな影響や、社長の本音を反映した設計の必要性、そして失敗しないための導入プロセスについて解説してきました。
これらの要素を統合し、最終的に大きな効果を発揮する仕組みの一つが「評価制度」です。
評価制度というと、多くの企業では
「給与や賞与を決めるための仕組み」
「社員間の優劣を決める査定」
として捉えられがちです。
しかし、本質的には「会社が社員に求める行動や成果を示し、それらを報酬や昇格と結びつけることで、組織として望ましい方向を促す」ための導線と言えます。
これは社員の採用や定着にも深く結びついており、評価制度の是非が企業の成長を左右しうるのです。
前回お伝えしたように、人事制度には
「社長(経営陣)の本音」
「企業理念や戦略との連動」
「管理職教育と運用」
が欠かせません。
評価制度においてもこの三つの軸は同様に当てはまります。
評価は、最終的に「人を誘導する」ニュアンスが生じる仕組みであるため、
社長・経営陣の理念や戦略が曖昧だと、結果として社員に“誤った方向性”を示してしまいかねません。
さらに、理念や戦略との整合性が取れずに曖昧な評価基準となれば、社員から不満や不信を招き、優秀な人材ほど離れてしまうリスクがあります。
管理職の理解不足による運用ミスが起きれば、せっかくの制度が機能しなくなる危険すらあるのです。
そこで今回は、「会社の業績を伸ばすための評価制度」として捉え直し、盛り込むべきポイントを段階的に解説していきます。
単なる査定で終わらず、経営戦略を具体的な行動に落とし込むための手段として評価制度をどう設計するかを考えていきましょう。
評価制度設計の基本構造

評価制度は、その中心に「会社が大切にしている価値観」や「これから目指す方向」が組み込まれてこそ意味が生まれます。
ここで私がお客様によく伝えるフレームワークが「Why・What・How」です。
すなわち「なぜ(Why)評価するのか」「何を(What)評価するのか」「どのように(How)評価するのか」を明確にし、評価制度全体を一本の筋として通していくわけです。
1. Why(なぜ評価するのか)
評価制度を設計する上で、最初に考えるべきは「会社として、どんな行動や成果を重視したいのか」。
これは会社の理念、そして経営戦略と強く関係します。
例えば、短期的な売上拡大を至上命題とする時期ならば、業績指標を重視する仕掛けが必要かもしれません。
一方、イノベーションや新規開発に力を入れたいのならば、失敗を恐れずチャレンジした社員を高く評価する文化が求められます。
ここを曖昧にしてしまうと、経営陣が期待する行動と社員が実際に行う行動にズレが生じ、評価制度が「とりあえず成果が出た人を並べ替えるだけ」の仕組みに陥りがちです。
とりわけ中小企業においては
「とにかく業績を伸ばしたいのか」
「組織力を強化して社内の結束を高めたいのか」
「顧客との長期的な関係性を重視するのか」
といった優先度の確認を丁寧に行うことが重要です。
社長自身が抱えるビジョンと社員が感じている現実との間にズレがあると、いくら評価制度を刷新しても狙い通りには機能しません。
前回の連載で述べたように、「社長の本音」から出発しない人事制度は建前で終わりがちなのです。
2. What(何を評価するのか)

会社が重視する価値観や戦略が明確になったら、次は「評価項目をどう設定するか」が鍵を握ります。
成果そのもの(売上や利益など)を重視するのか、
過程(行動や取り組み姿勢)を重視するのか、
あるいは能力(スキルセットや専門知識など)を重視するのか、
その配分次第で社員が力を注ぐポイントが変わってきます。
大切なのは、評価したい項目を闇雲に増やさないこと。
あれもこれもと網羅的にすると、結果的に社員の意識が分散され「何を頑張れば高い評価になるのか」が不明瞭になってしまうからです。
特に「顧客満足度」「チームワーク」「挑戦意欲」といった定性的な要素を取り入れる場合は、
定量的な業績指標とどうバランスを取るかを慎重に検討しなければなりません。
評価項目が多いほど評価表の作成や面談にかかる工数も増大し、管理職が形だけのチェックをして終わってしまうリスクが高まります。
本来、社員一人ひとりに丁寧な面談を実施し、行動・成果を具体的にフィードバックするには、管理職の時間と社員ひとりひとりの観察が不可欠ですが、
あまりにも多くの評価項目に対応しようとすると、面談やその前の情報収集自体が形骸化します。
結局は「現場の状況をしっかり見た評価」にならず、
離職率が高まる要因にも繋がります。
だからこそ、会社の戦略を実現するうえで特に重要な指標や行動特性を厳選し、それらに的を絞ることが望ましいと言えます。
また、評価項目を設定する際には、会社が掲げるKPI(重要業績評価指標)や戦略ターゲットとの整合性をチェックすることが欠かせません。
理念で「お客様第一」を強調しているならば、実際の顧客満足度アンケートの結果やリピート率、顧客からの声を取り入れる等の仕掛けを作り、評価項目として組み込むことを検討してみると良いでしょう。
会社が期待する具体的な行動や成果を「評価項目」という形で示すことで、社員の行動が企業理念と戦略へと一直線につながるのです。
3. How(どのように評価するのか)
評価の基準や項目が決まったら、次は評価のプロセスそのものを設計します。
大きくは「絶対評価」と「相対評価」が有名ですが、実際にはこの2つを組み合わせることも多いです。
そのほか、評価の手順やスケジュール、評価者トレーニングなど細部に気を配る必要があります。
まず、絶対評価と相対評価のそれぞれの内容を見ていきましょう。
- 絶対評価:
あらかじめ設定された基準に対して、個々の社員がどの程度達成できたかを判定。個人の成長促進や、協力し合う文化を醸成したい場合に向いています。業務プロセスや学習成果なども評価する場合、評価者の主観が入りやすいので「基準の明確化」と「評価者教育」が必須となります。
- 相対評価:
社員同士を比較し、上位何%を高評価とするなど、順位づけを行う仕組み。組織内の競争を活性化しやすい一方、協力し合う文化との両立は難しくなる可能性があります。導入の際には「なぜ相対評価が必要なのか」を社員に丁寧に説明しないと、納得感を得づらい場合があります。
評価手法が決まったとして、次に考えるのが、評価プロセスです。
評価プロセスは「評価者がなぜその評価を下したかを社員と面談する機会」を設けるかどうかで大きく変わります。
社員が自身の評価結果を理解し、次の行動に活かすためのフィードバックこそが、評価制度の真価を発揮する場です。
単にスコアを通知するだけでは社員が「次もっと良い評価を得られるためには、どのようにすればいいのか」わからず、
評価制度そのものが形骸化するリスクがあります。
とくに管理職が面談の場で「どの行動が良く、何を改善すべきか」をしっかり伝えられるようになると、
社員は自分の努力が会社のビジョンと繋がると実感しやすくなり、組織力の強化につながります。
Whyを深掘りする意義
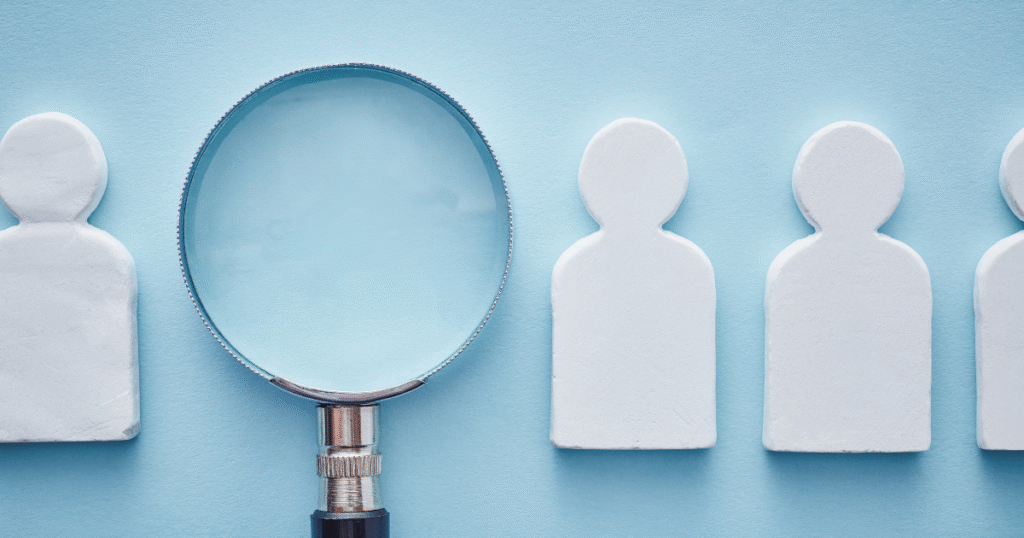
ここで改めて強調したいのが、最初の段階である「Why」をしっかり深掘りすることの意義です。
制度設計の要は社長の“本音”です。
評価制度においても同様で、「どのような人材や成果」を重要視しているのか、その真意を徹底的に明らかにしておく必要があります。
たとえば「企業として新規事業を強化したい」と口では言いつつ、実際には既存事業の売上を最優先としている場合、
評価項目や報酬決定の仕組みも売上成果に偏りがちになり、新規事業の種がなかなか育たないという矛盾が生じます。
こうしたブレを避けるためにも「社長の本音がどこにあるか」を丁寧に洗い出し、
評価の目的をぶれなく定義することが欠かせません。
さらに、経営の方向性が変われば、評価の重心も変わります。
急成長期には成果を重視し、成熟期には安定運用や次世代育成を重視するなど、
同じ企業でも時期によって必要な行動特性は変化するものです。
その変化に合わせて評価制度をアップデートしていく際にも
「最初のWhyが何だったのか」をはっきり把握していれば、
スムーズに見直しや修正が行えます。
もし経営陣が明確に認識・言語化できていない段階で評価制度を作ってしまうと、
社員も混乱に陥ってしまいます。
評価制度の品質を高めていく細部の工夫
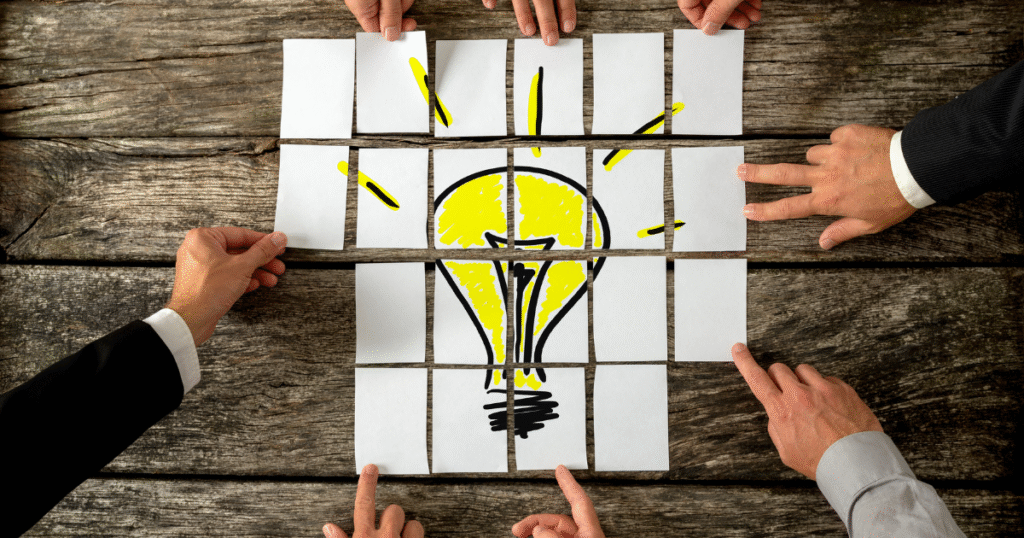
評価制度を最終的に形に落としこむうえで、最後の設計は、以下の3点です。
評価回数、評価者の設定、面談方法などの一連の具体的な運用内容
何回実施するか、誰が評価するか、いつ結果を開示するか、面談はどのように行うか、といった運用の設計。
評価面談は社員にとっても「自分が会社からどう見られているか」を知る貴重な場です。
この場を活用して、次の行動目標を一緒に設定できると社員の納得感が増します。
年に1度だけではなく、四半期ごとや半期ごとに短いサイクルで面談を行う手法も増えており、
それぞれの企業文化や、評価者の日々の業務負荷、事業サイクルに応じた運用を検討しましょう。
評価者トレーニング
評価者となる管理職が評価の目的や基準をどれほど理解し、自分の言葉で語れるかが制度の浸透に直結します。
研修やロールプレイを通じて「評価基準をどう説明するか」「どのように建設的なフィードバックを行うか」などを学ぶことが欠かせません。
特に、評価結果を社員に伝える面談では、単なる最終評価結果や個別点数の説明だけではなく、
具体的な行動に落とし込むアドバイスや成長の方向性を示すことが大切です。
昇格や報酬への反映ルールの明文化
評価結果が昇給や賞与など報酬にどの程度反映されるのか、どのようなロジックで算定するのかを明確に示すことが必要です。
特に絶対評価を採用する場合、評価が甘くなって人件費が膨らむリスクをコントロールする仕組み(例えば昇給上限や賞与原資の設定など)を持たないと、
制度が形骸化する可能性が高まります。
一方で相対評価を導入するなら、一定割合が必ず低評価になる仕組みが社員に与える心理的影響を踏まえ、
経営陣がそのメリットとデメリットを理解して、社員に説明できることが大切です。
これらに加え、評価結果を集計・分析し、次年度以降の経営戦略や人材配置計画に生かす仕掛けも重要になってきます。
評価制度は過去を振り返るだけではなく、未来へ投資する指標としても活用できるため、評価データの管理や活用体制を整えるとより効果的です。
例えば、異動前と異動後の部署での評価の変化を見て、
どの能力が発揮できると成果がでやすいか、上司との相性など、業績に大きく寄与した要因が何か分析すれば、
今後の研修計画や採用ターゲット、配置の見直しにも役立ちます。
また、評価者同士の情報共有の仕組みづくりも重要です。
実際の運用では、想定外の課題が表面化することも少なくありません。
こうした課題を事前に織り込み、導入~運用フェーズを見据えた準備を行うことで、
評価制度が社内にスムーズに根付き、企業文化と経営戦略を結びつける重要な役割を担うようになるのです。
まとめ

人事制度の中でも「評価制度」が会社の業績や社員の行動に及ぼす重要性を解説し、
設計時に押さえておきたい「Why・What・How」の視点を中心に、深掘りしてきました。
- なぜ評価するのか(Why)を経営陣の本音に基づいて定義しなければ、どれだけ立派な制度を作っても、社員の行動は思うように変わらない。
- 何を評価するのか(What)は戦略との一貫性を持ち、評価項目を絞ることが肝要。項目が多すぎるほど形骸化のリスクが高まる。
- どのように評価するのか(How)は、絶対評価と相対評価の組み合わせや評価プロセス、管理職のトレーニング、報酬連動の設計など多角的に検討が必要。
人事制度を経営視点で捉えなおすことは、採用と定着の課題解決のみならず、長期的に会社を強くしていく上で不可欠です。
特に評価制度は、企業理念を社員の行動に落とし込む極めて強力なレバーと言えるでしょう。
評価の結果をもとに社員が更なる高みを目指したり、
組織全体が同じ目標意識を共有したりすることで、経営戦略の実行力が一段と高まります。
人事評価制度にお困りの方は、お気軽に村井にご相談ください。
➖ 資料請求 ➖
資料請求は下記バナーより。

➖ 問い合わせ ➖
新規事業、DX、人事制度などの経営課題に関するご相談は以下よりお受けしております。