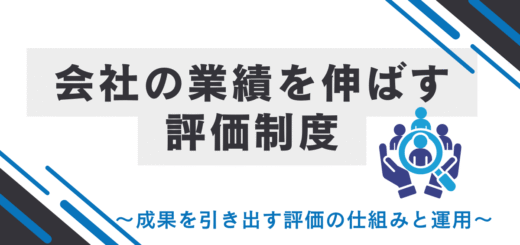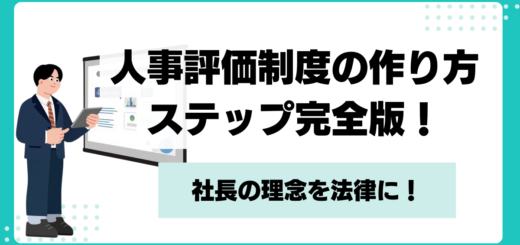人事評価制度の見直しは無駄?9割が知らない本当の課題

人事評価制度に社員から不満の声が上がれば評価項目を修正し、世の中のトレンドに合わせて評価手法を変え、管理職向けに研修を繰り返す。
しかし、なぜでしょう。
あれほど時間と労力をかけて見直しを行ったはずなのに、しばらくすると、また同じような課題が浮上してくる。
根本的な問題は、何も解決していない。
もし、あなたがそんな感覚を抱いているのなら、それは当然のことなのです。
なぜなら、世の中で語られる人事評価制度の見直し方法のほとんどは、残念ながら、9割が失敗するという宿命を背負っているからです。
この記事では、なぜ多くの見直しが無駄に終わってしまうのか、その根本にある「9割が見落とす本当の課題」を徹底的に解き明かします。
ぜひ、最後までお読みくださいね。

【村井 庸介(むらい ようすけ)】
大学卒業後は株式会社野村総合研究所に入社し通信業・製造業の経営コンサルティングに携わる。その後リクルート、グリー、日本IBMに転職。その中でグリー株式会社にて人事制度設計に携わった。
2015年に独立後は、社員30名のベンチャー企業から5,000名を超える大企業まで幅広く人事制度設計や導入伴走に携わる。顧客業種は製造業、サービス、IT企業が中心。経営理念・事業戦略から逆算した人事制度構築を得意とする。
なぜ人事評価制度の見直しは9割失敗するのか

人事評価制度の見直しは、多くの企業にとって、時間と労力がかかる、非常に骨の折れるプロジェクトです。
それにもかかわらず、なぜ、その努力のほとんどが報われずに終わってしまうのでしょうか。
その背景には、多くの企業が陥っている、深刻な「負のループ」が存在します。
見直しを繰り返す「負のループ」に陥っていませんか
あなたの会社では、こんな光景が繰り返されていないでしょうか。
まず、社員アンケートやヒアリングで「評価基準が曖昧だ」「評価に納得感がない」といった不満が噴出します。
それを受けて、人事部が中心となり、評価項目を細分化したり、評価基準をより具体的に書き直したりします。
そして、新しい制度を導入し、「これで公平になったはずだ」と一安心。
しかし、数ヶ月もすれば、今度は「評価項目が多すぎて、評価者の負担が大きい」「基準が細かすぎて、かえって本質的な評価ができない」といった、新たな不満が生まれます。
そして、また次の見直しが始まる。
この、終わりなき「見直し疲れ」こそが、多くの企業が囚われている「負のループ」の正体です。
このループに陥っている限り、どれだけ見直しを繰り返しても、組織が疲弊していくだけで、根本的な問題は何も解決しません。
9割が見落とす「本当の課題」とは
なぜ、このような「負のループ」が生まれるのでしょうか。
それは、9割の企業が、見直すべき「本当の課題」を見落としているからです。
彼らは、評価項目や評価基準といった、制度の「表面的なパーツ」ばかりに目を奪われています。
しかし、本当に問題なのは、そこではありません。
人事評価制度がうまく機能しない、たった一つの、しかし最も重要な理由。
それは、その制度が「何のために存在するのか」という、土台となるべき「会社の理念」が、不在であるか、あるいは完全に形骸化してしまっていることです。
この「理念の不在」という、本当の課題から目を背けている限り、どんなに巧妙な見直しを行ったとしても、それは砂上の楼閣を建て増ししているに過ぎないのです。
失敗のループを断ち切るための本質的な視点
では、この失敗のループを断ち切るためには、何が必要なのでしょうか。
それは、評価項目を眺めるのをやめ、視点を上げることです。
制度の「HOW(どう見直すか)」を議論する前に、制度の「WHY(なぜ見直すのか)」、そして、そのさらに根源にある「WHAT(我々は何者で、どこへ向かうのか)」を、問い直すこと。
つまり、人事評価制度の見直しを、単なる人事の仕事としてではなく、会社の理念やビジョンそのものを見直す、極めて重要な「経営の仕事」として捉え直すこと。
この「本質的な視点」の転換こそが、あなたの会社を、失敗する9割から、成功する1割へと導く、唯一の道なのです。
一般的な人事評価制度の見直し方法と手順

本質的な話に入る前に、まずは、世の中で「正しい」とされている、一般的な人事評価制度の見直し方法と手順について、網羅的に確認しておきましょう。
これらは、見直しを進める上での基本的なフレームワークであり、知っておいて損はありません。
しかし、同時に、これらが「9割が陥る罠」にもなり得ることを、心の片隅に留めておいてください。
見直しのタイミングと目的を明確にする
人事評価制度の見直しのタイミングとして、最も一般的なのは、経営方針や事業戦略が大きく変わった時です。
あるいは、社員から、現行制度に対する不満や形骸化を指摘する声が、顕著に高まってきた時も、見直しの重要なサインです。
見直しを始めるにあたり、まず最初に行うべきは、「今回の見直しを通じて、何を達成したいのか」という目的を明確にすることです。
「人材育成の促進」「公平性の確保による納得感の醸成」「業績向上への貢献」など、目的を言語化し、経営陣と社員の間で共有することが、見直しの第一歩となります。
現状分析から課題を抽出する方法
次に、現行制度が、なぜうまく機能していないのか、その原因を特定するための「現状分析」を行います。
具体的な方法としては、全社員を対象としたアンケート調査や、役職や部署ごとのヒアリング、あるいは過去の評価データや離職率などの定量的な分析が有効です。
これらの分析を通じて、「評価基準が曖昧である」「評価者のスキルにバラつきがある」「フィードバックが機能していない」といった、具体的な課題を抽出していきます。
新しい評価項目・評価手法の検討ポイント
抽出された課題に基づき、新しい制度の設計に入ります。
ここでは、「評価項目」と「評価手法」の見直しが、中心的なテーマとなります。
評価項目については、会社の理念や行動指針(バリュー)と、より強く連動するものへと見直すことが重要です。
また、評価手法についても、MBO(目標管理制度)やOKR、360度評価、コンピテンシー評価など、様々な手法の中から、自社の目的や文化に最も合ったものを選択、あるいは組み合わせて検討します。
導入後のモニタリングと再改善
新しい制度を導入して、終わりではありません。
導入後も、その制度が意図した通りに機能しているか、新たな課題は生まれていないかを、定期的に「モニタリング」する必要があります。
そして、モニタリングで見つかった課題に対しては、迅速に「再改善」を行っていく。
この、PDCAサイクルを回し続けることこそが、制度を形骸化させないための、重要なポイントであると、一般的には言われています。
なぜ一般的な見直し方法だけでは不十分なのか

ここまで見てきた「一般的な見直し方法」は、一見すると、非常に論理的で、正しい手順のように思えます。
しかし、なぜ、この手順に忠実に従っても、9割の見直しは失敗に終わるのでしょうか。
その理由は、これらの方法が、病気の「根本原因」ではなく、「症状」にしかアプローチしていないからです。
評価項目の見直しはただの対症療法
例えば、「評価基準が曖昧だ」という課題に対して、「評価項目をより具体的にする」という対策を講じるのは、一見すると正しいように見えます。
しかし、これは、熱が出たから解熱剤を飲む、という「対症療法」に過ぎません。
なぜ、評価基準が曖昧になってしまうのか。
その根本原因、つまり「会社として、何を大切にし、何を評価したいのか」という、熱の源である「理念」そのものにメスを入れない限り、いくら評価項目をいじっても、またすぐに別の場所から、新たな不満という熱が噴き出してくるだけなのです。
「社長の法律」なき見直しは必ず形骸化する
著者の思想の根幹には、「人事評価制度は、会社という王国の法律である」という考え方があります。
そして、その法律の最上位に位置し、全ての条文の拠り所となるのが、会社の理念という名の「憲法」です。
この「憲法」を制定できるのは、社長、ただ一人です。
一般的な見直し方法は、この「憲法」の存在を無視して、下位の法律である「条文(評価項目や運用ルール)」ばかりを修正しようとします。
最上位の憲法が曖昧なまま、下位の法律だけをいくら修正しても、そこに一貫性は生まれず、国民(社員)からの信頼も得られません。
「社長の法律」という、確固たる土台なき見直しは、遅かれ早かれ、必ず形骸化するという宿命を背負っているのです。
本当の課題を解決する本質的な見直し方法

では、失敗する9割から抜け出し、成功する1割の仲間入りを果たすためには、私たちは、何をすべきなのでしょうか。
その方法は、驚くほどシンプルですが、しかし、極めて本質的です。
それは、制度の「表面」からではなく、その「根幹」から、見直しを始めることです。
見直しとは制度ではなく「会社の法律」を改正すること
まず、言葉の定義から変えましょう。
私たちがこれから行うのは、単なる人事評価制度の「見直し」ではありません。
それは、会社のあり方そのものを規定する「会社の法律」、つまり「社長の理念」を、時代の変化や会社の成長に合わせて「改正」する、極めて重要な経営行為なのです。
この「法改正」という視点を持つことで、私たちは、枝葉である評価項目の修正といった、矮小な議論から解放されます。
そして、もっと大きく、本質的な議論へと、意識を向けることができるのです。
まず見直すべきは評価項目ではなく会社の「北極星」
「法改正」の第一歩は、評価シートを眺めることではありません。
夜空を見上げ、自分たちが進むべき道を照らす「北極星」を、再確認することです。
「我々は何のために、この事業を行っているのか」 「どんな価値を、お客様と社会に提供したいのか」 「5年後、10年後、我々は、どんなチームになっていたいのか」
社長であるあなた自身が、そして経営チームが、この「北極星」に対する答えを、明確に、そして共通の言葉で語れるか。
この「北極星」の輝きを取り戻すことこそが、全ての見直しの、絶対的な出発点となります。
社長が「誰をえこひいきするか」を再定義する
そして、「北極星」の光の下で、社長がやるべき、最も具体的で、最も重要なアクション。
それは、あなたの会社の「えこひいき」の基準を、改めて定義し直すことです。
「北極星」という目的地に向かう、この会社という船の上で、今、最も賞賛され、報われるべきは、どのような価値観を持ち、どのような行動をする「船員(社員)」なのか。
その基準を、社長が、自らの覚悟を持って、全社員に宣言すること。
この「えこひいきの再定義」こそが、新しい法律の魂となり、見直しプロジェクト全体を貫く、力強い背骨となるのです。
まとめ:あなたの会社は成功する1割になれる

人事評価制度の見直し。
その成否は、コンサルタントが提示する最新の手法や、他社の成功事例にあるのではありません。
それは、社長であるあなた自身が、どれだけ深く、自社の「理念」と向き合い、それを「法律」として改正する覚悟を持てるか。
ただ、その一点にかかっています。
明日から始めるべき最初のステップ
本質的な見直しを成功させるための、明日から始めるべき最初のステップ。
それは、評価制度の見直しプロジェクトチームを招集することではありません。
まず、社長であるあなたが、たった一人で、静かに考える時間を確保することです。
そして、自問してください。
「私が、本当に創りたい会社とは、どんな会社だろうか?」 「私が、心から『えこひいき』したい社員とは、どんな社員だろうか?」
その問いに対する、あなたの心の奥底からの答えこそが、あなたの会社を、失敗する9割から、成功する1割へと導く、全ての始まりです。
本質的な制度見直しの個別相談のご案内
もし、あなたが、自社の「北極星」を見つめ直し、それを「生きた法律」へと昇華させるプロセスにおいて、信頼できるパートナーを必要としているならば、ぜひ、私たちにご相談ください。
私たちは、あなたの会社の「理念」を言語化し、それを組織の隅々にまで浸透させる、本質的な制度見直しの、具体的なお手伝いをすることができます。
あなたの会社が、失敗のループを断ち切り、新たな成長への航海へと、力強く漕ぎ出す、その第一歩を、共に踏み出せることを、心から楽しみにしています。
人事評価制度にお困りの方は、お気軽に村井にご相談ください。
➖ 資料請求 ➖
資料請求は下記バナーより。

➖ 問い合わせ ➖
新規事業、DX、人事制度などの経営課題に関するご相談は以下よりお受けしております。