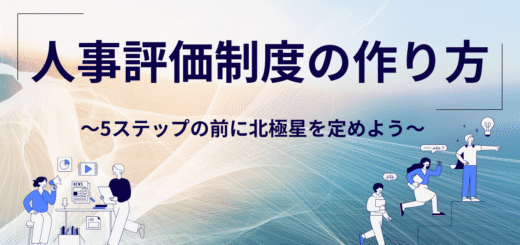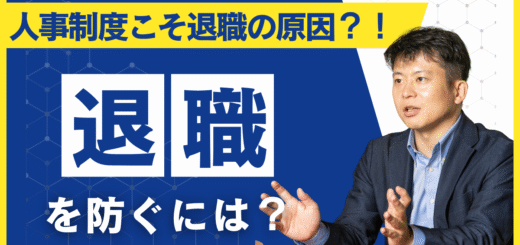人事制度は社長の本音のメッセージ!建前を排し、本音を反映する仕組みづくりの秘訣

このコラムではクラフトビール会社の新規事業で年商1億円を達成してから1.5倍2倍へと成長させてきた村井が、その実践的なノウハウを紹介しています。
またコンサルティング会社として新規事業の立ち上げをサポートした、または大手の会社とのお仕事から培ってきた経験をお届けしています。
今回は「社長の本音を反映すること」がなぜ組織を強化し、持続可能な成長を促すのか、その理由についてお話しします。
更に、建前が陥りがちな落とし穴とは何か、本音を探るためのアプローチについても、掘り下げて解説します。

【村井 庸介(むらい ようすけ)】
大学卒業後は株式会社野村総合研究所に入社し通信業・製造業の経営コンサルティングに携わる。その後リクルート、グリー、日本IBMに転職。その中でグリー株式会社にて人事制度設計に携わった。
2015年に独立後は、社員30名のベンチャー企業から5,000名を超える大企業まで幅広く人事制度設計や導入伴走に携わる。顧客業種は製造業、サービス、IT企業が中心。経営理念・事業戦略から逆算した人事制度構築を得意とする。
良い人事制度と悪い人事制度を分ける前提条件

組織に良い影響を与える人事制度の「重要な前提条件」についてお話をしていきます。
結論を先に伝えると、「建前ではなく社長の本音が反映されている」ことです。
ここで言う本音とは、仕事のプレッシャーを感じる日々の中で下す判断や行動習慣を指します。
後ほど、建前については解説しますが、例えば、著名経営者の講演を受け、高尚な理念や考え方に影響を受けていることがあります。
しかし、社長も人間なので、日々の現実に直面すると長続きしません。
これも建前の一種です。
では、なぜ建前が人事制度に入り込んではいけないのか、具体的な理由から見ていきます。
建前で人事制度を作ると社長が苦しむことになる
「評価は公平に行います」
「成果を出した人材はどんどん登用します」
「地域や社会への貢献を重視します」
これらの言葉を、企業の制度方針として一度は目にしたことがあるのではないでしょうか?
これらが社長の本音に基づいていれば、企業の理念として組織全体を支える柱になるでしょう。
しかし、これらが「建前」である場合、社長自身を苦しめる結果となります。
実際に、ある店舗サービス業の例を見てみましょう。
この会社では、当時のビジネス界で流行していた成果主義型の人事制度を導入しました。
具体的には、客単価、入会率といった数値化しやすい成果指標を評価基準の中心に据えました。
この制度の導入後、社員たちは明確な指標に基づいて動き、自身の成果を追求しました。
その結果、数年間は業績が右肩上がりに伸びるという目覚ましい成果を上げました。しかし、この制度には隠れた問題がありました。
社長が大切にしていたのは、社員同士が協力し合い、部門間の壁を超えて困っている同僚を支援する文化や、日々の業務の中で自然と若手にアドバイスを行うような『気配り』の精神でした。
一方で、導入された成果主義型の人事制度では、個人の売上や客単価といった数値目標の達成度のみが評価され、チーム貢献や若手育成の取り組みは評価項目に含まれませんでした。
その結果、評価される行動にのみ社員の関心が集中し、本来重視すべき協力や育成の文化が急速に失われていきました。結果的に、社長が重要視していた縁の下の力持ち的な社員たちが次々と退職する事態に陥りました。
さらに、この過程で発生した問題を解決しようと、社長は退職を止めるために個別対応として賞与を増額するなどの裁量的な措置を講じました。
一見するとこれらの対応は問題解決に寄与しそうですが、実際には評価基準の不透明性を高め、他の社員の不信感を招く結果となりました。
この不信感から、成果を上げていた人材までもが離職し、会社全体の業績は次第に停滞するようになりました。
この状況をさらに深刻化させたのは、社員間の信頼関係の崩壊です。
成果主義の評価基準では個人の業績が強調されるため、協力よりも競争が優先される風潮が強まりました。
その結果、チームで協力し合う文化が薄れ、短期的な成果を求めるあまり、長期的な視点での人材育成が後回しにされました。
これにより、新人育成や組織全体のスキル向上が停滞し、さらに離職率が高まるという悪循環が生じました。
状況を打開しようと、社長は社員に向けて組織全体で協力することを呼びかけましたが、すでに制度が社内に深く根付いており、社員の行動様式を変えることは容易ではありませんでした。

このように、建前を基にした人事制度は、大切にしたかった社員を失うだけでなく、既存の社員の行動に悪影響を及ぼし、企業全体を袋小路に追い込む悪循環を引き起こしてしまうのです。
建前の人事制度の問題点は、それが一見すると正しい方向性に見えるため、導入時のリスクが見過ごされがちな点です。
さらに、建前による制度設計は、企業文化と矛盾したメッセージを組織に送り込みます。
例えば、「成果主義」と言いながらも、特定の社員に裁量的な対応を行うと、公平性が損なわれるだけでなく、社員間の不満が増幅します。
これにより、組織全体が短期的な成果を追求するあまり、長期的な成長機会を見失うリスクが高まります。
健康な身体づくりには身体によいものを取る前に、まず悪いものを取らないことが重要であるように、人事制度の設計においても「建前」を排除することが最初のステップになります。
建前はしばしば社会常識やトレンド、他社の成功事例などの形で企業に入り込んできますが、それらを無批判に取り入れることは、組織に深刻な矛盾をもたらす可能性があります。
「建前」の中でも特に注意が必要なのが、「社員の声を大事にする」という考え方です。
一見、社員の声に耳を傾けることは正しい経営姿勢のように見えますが、これがいかにして企業を苦境に陥れる要因となるのかを次に説明します。
社員の声を拾うと人事制度は機能しなくなる

「社員の声を聴く」という活動には構造的な欠陥があります。
まず、「誰が声を上げているか」の問題です。
一般的に、自身の処遇に不満を持つ社員ほど、声を上げやすい傾向にあります。そして、その内容は往々にして「プロセスで評価をすべきだ」「報酬の上げ幅を増やすべきだ」という、個人の要望に偏ります。
これに加え、こうした声が評価基準に反映された場合、その効果は長続きしないことが多いのです。
例えば、特定の社員の声を受け入れる形で評価制度を変更した場合、他の社員からの新たな不満が生じる可能性があります。
また、特定の個人やグループが得をしていると感じる社員が増えることで、組織全体の士気が低下する恐れもあります。このような状況では、いくら声を反映しても、組織全体の安定には寄与しません。
また、こうした社員の多くは「自社の強みは何か、その強みを支える業務・組織は何か」を言語化できません。
そのため、彼らの要望は企業戦略と整合性を欠いたものが多くなります。結果として、短期的な改善には役立つかもしれませんが、長期的なビジョンにはつながりません。
また、社員の声を拾いすぎると、公平性のワナにはまり、あれもこれも採用する結果、社員から見ても何が評価されているのかわからない不明瞭な人事制度が出来上がります。
さらに、声を採用した社員が辞めない保証もありません。
過去の事例では、自分の提案が制度に反映されたにもかかわらず、結局辞めてしまった社員も少なくありません。
これは、制度に意見を述べる行為とその結果の責任を社員が感じることがないためです。
その結果、人事制度の不安定さだけが残り、企業の根幹を揺るがすことにもつながりかねません。
では、「誰の声を拾えばいいのか」という疑問が湧いてくるかと思います。
その答えは、「社長をはじめとする経営陣」です。
彼らは経営責任を負う立場にあり、組織の長期的なビジョンを描き、それを実現する責務を負っています。
そのため、経営陣の視点に基づいて設計された人事制度は、組織全体の成果創出を後押しします。このような制度は、結果的に業績を向上させるだけでなく、組織全体の持続可能性を高めるものとなります。
経営陣の声を拾うことで、ビジョン実現や戦略実行に必要な行動や考え方、チームワークなどの価値観を明確化し、それらを推進する制度設計が可能になります。
例えば、「社員にして欲しい行動」を具体的に人事制度に反映することで、それを行う社員が適切に評価され、組織文化として根付くようになります。これにより、個々の行動が組織全体の目標に直結する形で統合され、人事制度がその潤滑油として機能するのです。
では、そうした人事制度を作るにはどうしたらよいのでしょうか。等級、評価、報酬などの仕組みを検討する前に、まず踏むべき第一歩があります。
それが「経営陣のインタビュー」です。
人事制度作りの第一歩は経営陣のインタビューから

このインタビューは単なる意見収集ではありません。
経営陣一人一人が描く未来像を引き出し、その共通点と相違点を明らかにすることで、会社として目指す共通のゴールを具体化していく重要なプロセスなのです。
私が人事制度設計をする際には、以下の3つの質問を必ず投げかけます。
「5年後、10年後、会社はどのような成長をしていますか?」
「その時はどんな組織、人材が集まっていますか?」
「10年後も会社として残したい大事な文化は何ですか?」
これらの質問は、経営陣のビジョンを明確にするための出発点に過ぎません。しかし、このプロセスの進め方や雰囲気作りも非常に重要です。
インタビューの場では、ただ質問をぶつけるだけでなく、リラックスした空間を作り出すことで、経営陣が自身の考えを深く掘り下げて語る環境を整える必要があります。
話が脱線した方が本音も見えやすく、組織を考える上でのヒントも出てくるので、インタビューを進行表通り行うことよりも、自然な対話を楽しむことを意識してください。
また、事前の準備も大事です。
インタビューの目的を共有し、回答に正解はなく、あくまで個々の視点を尊重するものであることを強調することで、回答することへの身構えなどインタビュー時間時間のロスを減らします。
さらに、出来るのであれば、業務スペースから離れた空間で行うことで、経営陣が自身の回答やビジョンに集中できるようにします。
インタビューは以下の3段階で構造化することが効果的です。
まず導入として10分程度、コーヒーを共にしながら、経営者個人の経歴や価値観について自由に語っていただきます。
次の30分で、先ほどお伝えした3つの核となる質問について深掘りしていきます。最後の20分では、具体的な事例を通じて本音を引き出します。
例えば「最近昇進させた社員の具体的な理由は何でしたか?」、「逆に、昇進を見送った社員についてはどういった判断でしたか?」といった実際の判断事例を通じて、経営者の持つ評価軸を明確にしていきます。
こうしたインタビューを通じて、興味深い発見があります。
同じチームであっても、各役員が描く未来像が異なるのです。この違いは決して悪いことではありません。
それぞれが持つ専門分野や経験に基づいて、同じ未来像でも異なる角度からの見え方や表現が生じるためです。三角錐を上から見るのか、下から見るのか、横から見るのかの違いと同じです。
しかし、この違いがそのまま現場に落とし込まれると、社長の意図とは異なる解釈や認識が組織に広がる可能性があります。
そのため、共通の未来像づくりが不可欠となるのです。共通の未来像づくりについては、第3回の連載にて詳細をお伝えします。
これらのインタビュー情報は、人事制度の設計だけでなく、組織運営全般にも役立つ貴重なデータとなります。
たとえば、特定の役員がリーダーシップ開発に重きを置く一方で、別の役員が技術革新に焦点を当てている場合、これらの視点をどう統合するかが組織の課題となります。
このそれぞれが持つ想いや課題感が、人事制度づくり基礎材料となります。単なる理想論ではなく、現実的な課題や経営陣の価値観を反映するため制度が高い実効性を持つものとなります。
まとめ
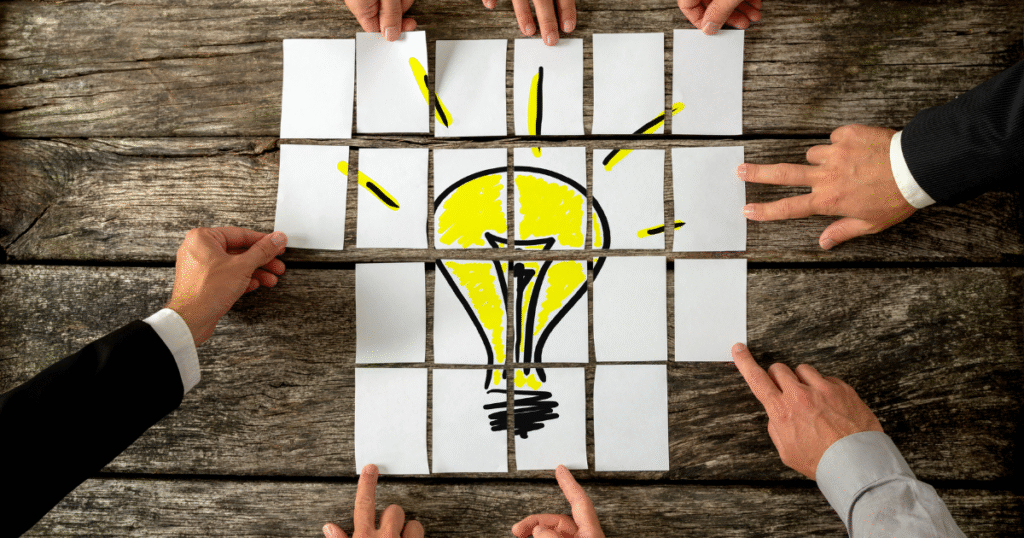
人事制度設計において、建前の落とし穴を避けることが、第一のステップです。
一見、正しいように見える建前に基づいた制度設計は、導入後に組織を混乱させ、社長や経営陣を苦しめる結果を招きます。
建前に依存した方針では、社長が取ってほしい社員への行動や組織の持続可能な成長と整合性を欠き、不必要な複雑化や公平性の欠如といった問題を引き起こす可能性があります。
こうした危険性を理解し、建前を取り除くことこそが、健康な組織を構築する第一歩です。
その上で、経営陣の本音を引き出し、会社としての共通の未来像を描くことが不可欠です。この未来像を明確にするプロセスは、単なる意見収集ではなく、経営陣それぞれの価値観や視点を丁寧にすり合わせ、組織全体を一つの方向に導くための基盤を築く重要なステップです。
また、こうして描かれた未来像は、社員の行動指針として具体化され、人事制度を通じて実行可能になることで、組織の持続的な成長を支えるものとなります。
今回ご紹介したインタビューの進め方や雰囲気作りのポイントを踏まえれば、経営陣の意見を最大限に活用し、一貫性のある制度を設計するための基礎が構築できます。
経営陣の声を中心に据えた制度設計こそが、組織文化を支え、社員の納得感を高める鍵となります。
人事評価制度にお困りの方は、お気軽に村井にご相談ください。
➖ 資料請求 ➖
資料請求は下記バナーより。

➖ 問い合わせ ➖
新規事業、DX、人事制度などの経営課題に関するご相談は以下よりお受けしております。