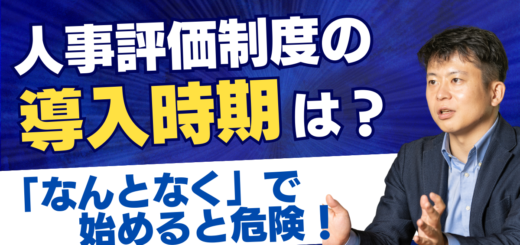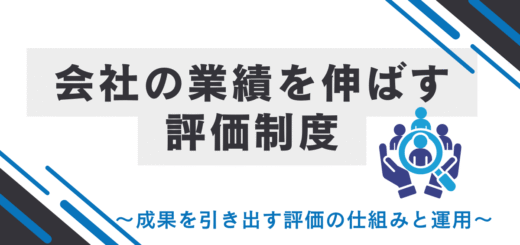スタートアップの人事評価のコツ|その導入、本当に必要ですか?

スタートアップの人事評価にお困りではないですか?
急成長を目指す組織にとって、避けては通れないテーマです。
「そろそろウチも人事評価制度を導入すべきか」
そう考えている経営者の方も多いのではないでしょうか。
しかしその導入ちょっと待ってください。
その決断あなたの会社の成長を加速させる特効薬になるでしょうか。
それとも勢いを削ぎ組織を蝕む劇薬になってしまうのでしょうか。
この記事は単なる人事評価制度の導入マニュアルではありません。
巷で語られる一般的なメリットや作り方を網羅した上で、
なぜ9割ものスタートアップが人事評価で失敗するのかその根本原因を解き明かします。
そしてあなたの会社が「大企業ごっこ」の罠に陥ることなく
本当に価値のある制度を創り上げるための本質的な視点を解説します。
きっとあなたの会社にとっての羅針盤となるはずです。

【村井 庸介(むらい ようすけ)】
大学卒業後は株式会社野村総合研究所に入社し通信業・製造業の経営コンサルティングに携わる。その後リクルート、グリー、日本IBMに転職。その中でグリー株式会社にて人事制度設計に携わった。
2015年に独立後は、社員30名のベンチャー企業から5,000名を超える大企業まで幅広く人事制度設計や導入伴走に携わる。顧客業種は製造業、サービス、IT企業が中心。経営理念・事業戦略から逆算した人事制度構築を得意とする。
スタートアップの人事評価 その導入本当に必要?
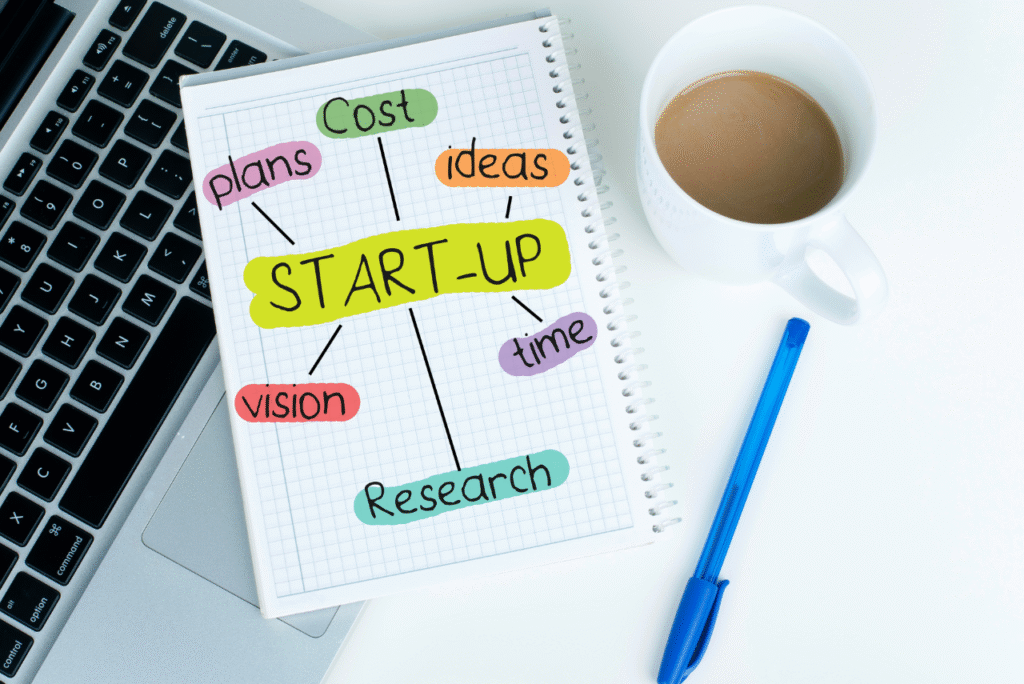
変化の激しいスタートアップの世界では、人事評価制度の導入は諸刃の剣となり得ます。
多くの成功事例が語られる一方で、導入によって組織が停滞し崩壊へと向かうケースも少なくありません。
なぜでしょうか。
なぜ9割のスタートアップは人事評価で失敗するのか
驚かれるかもしれませんが、私が見てきた限り多くの場合スタートアップの人事評価制度導入は失敗に終わります。
その理由は非常にシンプルです。
ほとんどの企業が制度導入の「本当の目的」を理解しないまま、ただ「仕組み」だけを真似て導入してしまうからです。
特に成長を急ぐあまり本質的な議論を省略し、他社の成功事例やテンプレートに飛びつくケースが後を絶ちません。
魂のない制度は人を動かしません。
大企業ごっこになっていないか
「有名企業が導入しているOKRをウチも導入しよう」
「しっかりした評価制度があれば採用で有利になるはずだ」
こうした体裁を整えるためだけの制度導入を、私は「大企業ごっこ」と呼んでいます。
スタートアップにはスタートアップならではの強みがあります。
それは社長と社員の距離が近く理念やビジョンがダイレクトに伝わることです。
この最大の武器を自ら捨て去り、形だけの「大企業ごっこ」に走ることは会社のスピード感を失わせ組織を弱体化させる危険な選択です。
あなたの会社は大丈夫でしょうか。
スタートアップ特有の人事評価の難しさとは
スタートアップの人事評価が難しい理由はいくつかあります。
まず事業フェーズの変化が激しく求める人材像や役割が短期間で変わること。
次に評価基準となる過去のデータや前例が乏しいこと。
そして評価制度の設計や運用に十分なリソース(人手や時間)を割けないこと。
さらに創業メンバーと後から加わったメンバー間での意識や貢献度に対する認識のズレが生じやすいこと。
これらの特有の難しさを理解せず安易に制度を導入すれば必ず歪みが生じます。
よくある導入メリットと評価手法

本質的な議論に入る前に世の中で一般的に語られている人事評価制度のメリットと主な評価手法について確認しておきましょう。
これらは導入を検討する上での基本的な知識となります。
公平性・モチベーション・人材育成
人事評価制度が理想的に機能すればスタートアップは多くのメリットを享受できるとされています。
第一に、評価基準やプロセスが明確になることによる「公平性・透明性の確保」。
これにより社員の納得感を高め不公平感を減らす効果が期待されます。
第二に、目標設定と達成への評価を通じた「従業員のモチベーション向上」。
自分の貢献が認められると感じることが仕事への意欲に繋がります。
第三に、評価とフィードバックによる「人材育成と定着」。
社員の強みや課題を把握し成長を促すことで組織全体のレベルアップと人材の定着を図ります。
これらは確かに魅力的なメリットに見えます。
主な評価手法
次に、代表的な評価手法をいくつか紹介します。
MBO(目標管理制度)は社員が自ら目標を設定しその達成度を評価する手法です。
OKR(目標と主要な結果)は、会社の挑戦的な目標と連動した目標を設定し高い頻度で進捗を確認する手法でスタートアップで人気があります。
コンピテンシー評価は、高い成果を出す人材に共通する行動特性を評価基準とする手法です。
360度評価は、上司だけでなく同僚や部下など多角的な視点から評価を行う手法です。
これらの手法を単独でまたは組み合わせて自社に合った制度を設計することが一般的です。
導入ポイント
スタートアップが制度を導入する際のポイントとしては「早期導入」が推奨されることがあります。
初期段階から公平な組織文化を醸成できるという考え方です。
また「組織文化との適合」も重要です。
協調性を重んじるか成果主義を徹底するかで、適切な評価段階数などが変わってきます。
さらに「評価基準の明確化と周知徹底」、そして「継続的な運用と改善」が不可欠とされています。
これらの一般的なメリットや手法、ポイントを踏まえた上で私たちは次の章でより本質的な問いへと進みます。
なぜ50名未満のスタートアップに制度は不要なのか

さて、ここからが私の経験に基づく核心的な主張です。
私はこれまでの経験から、「従業員数50名未満のスタートアップにおいては人事評価制度はむしろ導入しない方が良いケースが多い」と考えています。
これは早期導入を推奨する一般的な意見とは異なるかもしれません。
その理由をご説明します。
社長の言葉こそ最強の評価制度
従業員が50名未満の規模であれば、多くの場合社長は全社員の顔と名前そして働きぶりを直接把握できます。
誰が今最も事業に貢献しているか、誰がチームのために汗をかいているか誰が壁にぶつかっているか。
社長であるあなたの「肌感覚」がそれを教えてくれるはずです。
そしてその肌感覚に基づいてあなたが直接かける、「ありがとう」「よくやった」「期待しているぞ」「次はこうしてみないか」という生の声。
それこそがどんな精緻な評価シートよりも、社員の心を奮い立たせる「最強の評価制度」なのです。
この時期に形式的な制度を導入することは、社長と社員の間の人間的な繋がりを希薄にし組織のダイナミズムを失わせるリスクがあります。
無理な導入が招く3つの悲劇
この「社長の言葉」というスタートアップならではの武器を捨ててまで、無理に人事評価制度を導入すると多くの場合3つの悲劇が起こります。
一つ目は「スピード感の喪失」です。
これまで社長の一声で決まっていたことが評価期間や目標設定といった制度のプロセスに縛られ意思決定が遅くなります。
二つ目は「社員のモチベーション低下」です。
社長との直接的な関係性の中で評価されていた状態から冷たい評価シートの上で点数を付けられる状態へと変わることは、特に初期メンバーにとって大きなストレスと不信感を生みます。
三つ目は「本業へのリソース圧迫」です。
ただでさえリソースの限られるスタートアップが制度の設計や運用に多大な時間と労力を費やすことは、プロダクト開発や顧客獲得といった本来集中すべき事業活動を圧迫します。
制度より先に社長がやるべきこと
もしあなたの会社が50名未満でかつ組織に大きな問題を感じていないのであれば、あなたが今やるべきことは人事評価制度の導入ではありません。
もっと社員一人ひとりと対話することです。
もっと顧客の声に耳を傾けることです。
そして何より、社長であるあなた自身が「この会社を通じて何を成し遂げたいのか」「どんな仲間と働きたいのか」という自らの理念をより深く見つめ直しそれを熱く語り続けることです。
制度という「仕組み」に頼る前に、まずあなたの「想い」をあなたの「言葉」で社員に届け続けること。
それが50名未満のスタートアップにおける最も本質的な人事施策なのです。
本当に必要なのは「50名の壁」を超えたスタートアップ

ではどんなスタートアップに人事評価制度は本当に必要になるのでしょうか。
その答えは極めてシンプルです。
それは社長であるあなたの「目」がもはや全社員に届かなくなった時です。
導入のタイミングは50名の壁
多くの企業でその限界点つまり「社長の目が届かなくなる」のが従業員数50名前後であると私は考えています。
これを「50名の壁」と呼んでいます。
社員数が50名を超えると、社長はもはや全社員の働きぶりを直接肌感覚で把握することは物理的に不可能になります。
社長の目が届かない部署では、社長が大切にしてきたはずの理念や文化がいつの間にか歪んで伝わり始めます。
初期メンバーと新メンバーの間にも見えない溝が生まれてきます。
この「50名の壁」こそが、人事評価制度の導入を本気で検討すべき唯一のタイミングなのです。
導入の唯一の目的 社長の理念浸透
そしてこのタイミングで導入する人事評価制度の目的は、一般的な「公平性の確保」や「モチベーション向上」ではありません。
そのたった一つのしかし最も重要な目的。
それは社長の目が届かない場所隅々にまで、社長の理念や価値観を浸透させることです。
評価制度は社長の理念を言語化し、組織の隅々まで届けるための「仕組み」でなければなりません。
評価制度は社長の分身を創る仕組み
言い換えれば、人事評価制度とは社長の代わりに、社長の理念や価値観を伝え判断を下してくれる「社長の分身」を創り出す仕組みです。
この制度があるからこそ会社が大きくなっても、組織のベクトルがずれることなく社長が目指す方向に全社員が一丸となって進むことができるのです。
評価制度は単なる評価ツールではなく、社長の理念を組織にインストールするためのOSなのです。
スタートアップ人事評価の設計のコツ

では「社長の分身」となる魂のこもった人事評価制度をスタートアップは、どのように設計すれば良いのでしょうか。
他職種との違いも踏まえながらそのコツをお伝えします。
コツ① 理念から始める設計思想が全て
最大のコツは評価項目や手法といったテクニックから入らないことです。
まず社長が「何を大切にしどんなチームを創りたいのか」という理念=「会社の法律」を明確に言語化すること。
全ての設計は、この理念からドミノ倒しのように始まります。
この設計思想なくして成功はありません。
コツ② シンプルさと柔軟性が命
スタートアップの制度はシンプルであるべきです。
大企業のような複雑な評価項目やプロセスは変化のスピードを妨げます。
理念の核心を突く数個の重要な評価軸に絞り込みましょう。
そして変化に対応できる「柔軟性」も不可欠です。
事業フェーズに合わせて半期や一年ごとに制度を見直すことを前提とした設計が必要です。
一度作ったら終わりではないのです。
まとめ 安易な導入をやめ理念を定めよう
スタートアップの人事評価制度導入は、決してゴールではありません。
むしろ理念なき導入は、組織崩壊の始まりです。
あなたの会社は制度が必要なステージか
まず自問してください。
「私の目はまだ全社員に届いているか?」
「私が本当に伝えたい理念は何なのか?」
もしあなたの会社が50名未満で社長の言葉が隅々まで届いているならば、制度はまだ必要ないかもしれません。
もし50名の壁を超え理念の浸透に課題を感じているならば、今こそ「社長の分身」を創る時です。
スタートアップ向け人事評価制度の個別相談
もしあなたが自社のステージを見極めあなたの会社の理念、つまり「魂」のこもった唯一無二の人事評価制度を本気で創りたいと願うならば、ぜひ私にご相談ください。
私は単なる制度の作り方を教えるのではありません。
社長であるあなたの「想い」を言語化し、それを組織の隅々にまで浸透させる血の通った制度設計をゼロから共に行います。
あなたの会社の未来を創るその第一歩を、共に踏み出せることを心から楽しみにしています。
人事評価制度にお困りの方は、お気軽に村井にご相談ください。
➖ 資料請求 ➖
資料請求は下記バナーより。

➖ 問い合わせ ➖
新規事業、DX、人事制度などの経営課題に関するご相談は以下よりお受けしております。